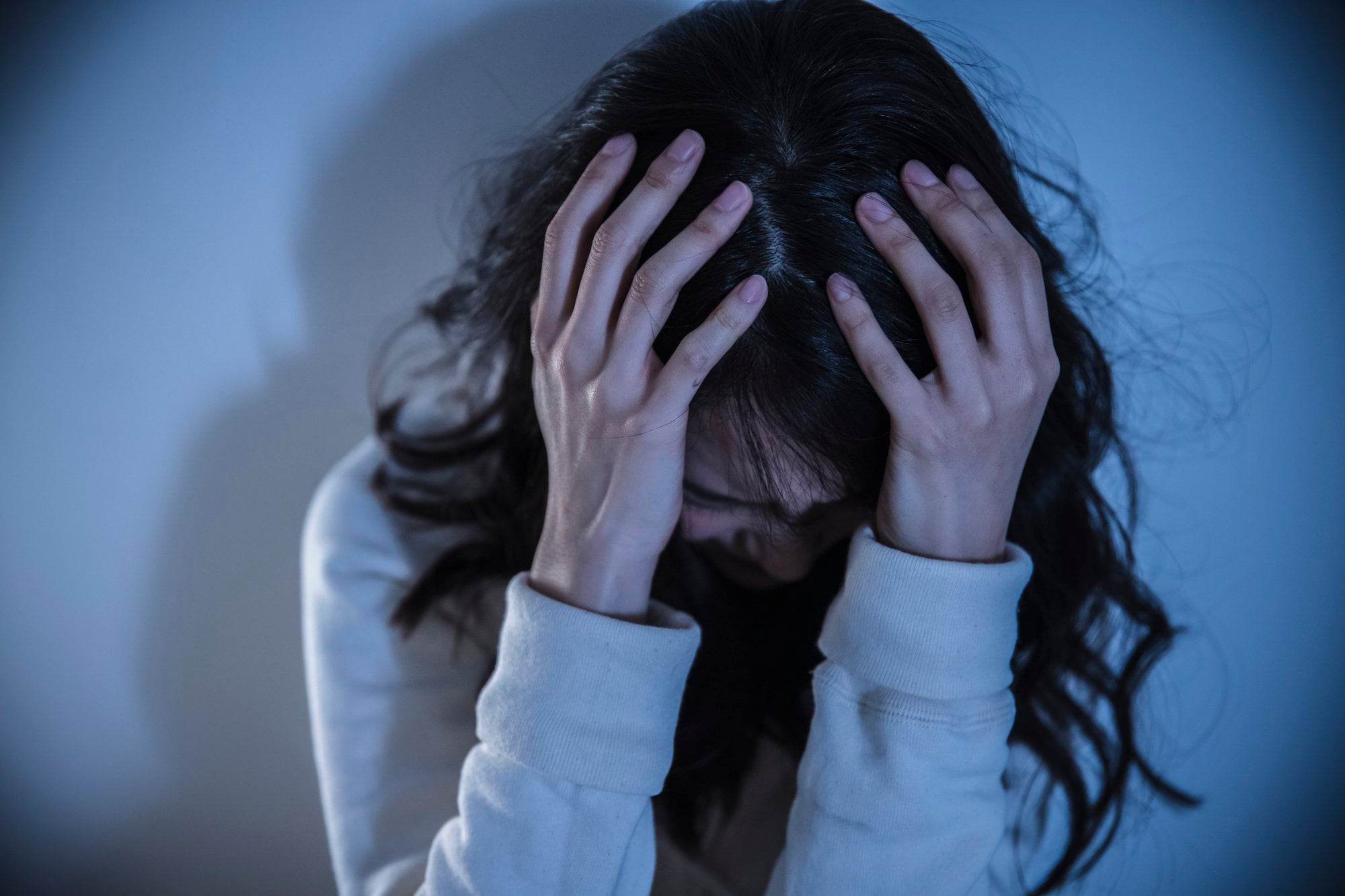診察室で起きた予想外の展開
一通りの話を聞き終えた医師は大きく頷きました。
「なるほど。そのような事情で受診を中断されていたのですね」
さらに医師からは意外な言葉が発せられました。
「更新の時にもご本人がそこまで日常生活に困難さを抱えているということが分かっていれば、もう少し重めに診断書を書いたかもしれません」
そう話す主治医からは、こちら側の話もしっかり聞いてくれるような雰囲気を感じ取ることができました。
そこで筆者は次のようにお願いをしました。
「本日お渡しした資料には、哲夫さんの現在の日常生活の様子が記されています。そちらをご参考いただき、新たな診断書を作成いただけないでしょうか」
すると医師は真摯な眼差しをこちらに向けたあと、哲夫さんに向かって言いました。
「分かりました。ですが、新たに診断書を作成するためにも、あと2~3回は受診して欲しいところです。それができたら、すみやかに診断書を書くようにします。それでもよろしいでしょうか」
哲夫さんは小さく頷き、主治医の指示に従うことになりました。
奇跡の復活、家族に訪れた希望の光
その後、哲夫さんは受診を続け、診断書を作成してもらうことができました。診断書を入手した筆者は、すみやかに日本年金機構に受給再開の手続きをしました。
手続きから3カ月が経った頃。母親から「無事に障害基礎年金の再開が認められた」との報告を受けました。
その報告を聞いて、筆者もやっと安堵することができました。
今回の哲夫さんのように、長い受診の間に主治医が変わってしまうこともあるでしょう。新しい主治医に本人の障害状態や日常生活の困難さがうまく伝わっていないと、思わぬ結果を招いてしまうこともあります。
それを避けるために、例えば次のような対策を取ってみるとよいでしょう。
①障害年金が受給できた当時の診断書のコピーを主治医に見てもらう
障害状態に変化がないようであれば「現在も当時と同じような障害状態にあります。こちらの診断書のコピーをご参考いただき、更新用の診断書の作成をお願いします」と伝えてみましょう。
②日常生活の困難さの文書を作成する
障害年金を請求した当時の診断書のコピーが手元に無いようであれば、更新時期における日常生活の困難さをまとめた文書を作成してみましょう。
もし、これらの対策を行っても障害年金の更新がうまくいかず支給停止してしまったら、専門家である社会保険労務士に相談することも検討してみましょう。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。