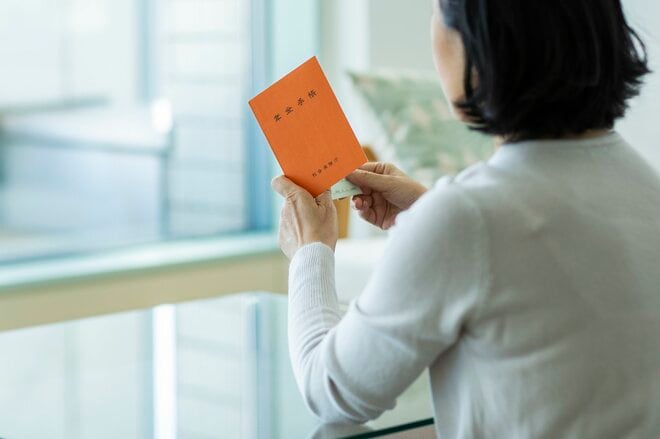浮かび上がった死後離婚の選択肢、遺族年金への影響は?
そんな中で、郁夫さんが突然病気により亡くなります。郁夫さんは40年以上会社員をしていたため、顕子さんは遺族年金を受け取れるということを聞きます。顕子さんは喪主として郁夫さんの葬儀や死後の手続きで慌ただしくなります。
しかし、郁夫さんの葬儀や納骨の件で再び義母をはじめとする親族と意見が合わず、揉めることになります。そして、これまでは郁夫さんがいたからどうにか我慢できていたものの、郁夫さんの死後はその我慢も限界に達します。このことが決定打になり、「もうこれ以上は無理」と夫の親族とは縁を切りたいと思うようになります。そして、そんな中で知った「死後離婚」についても考えます。これは市区町村への姻族関係終了届の提出により、亡き配偶者の親族(=姻族)との姻族関係を終了させる手続きになります。
郁夫さんの死後の手続きがたくさんあり、死後離婚も考える顕子さんはまず遺族年金の手続きで年金事務所に行きます。
ここで窓口の担当職員から「顕子さんは郁夫さんが亡くなったことにより、遺族年金のうちの遺族厚生年金が支給されます」と言われます。まず、65歳までの間、遺族厚生年金105万円に中高齢寡婦加算63万円も加算され、年間168万円の年金が受給できることになりました(※遺族厚生年金の受給により、65歳前の顕子さん自身の特別支給の老齢厚生年金については支給なし)。そして、65歳以降の年金は、顕子さん自身の老齢基礎年金として年間75万円、老齢厚生年金として年間20万円受け取り、遺族厚生年金については中高齢寡婦加算がなくなった105万円から老齢厚生年金20万円を差し引いた年間85万円が支給され、それらの合計で年間180万円を受け取ることになりそうです。
今後の年金額や内訳について詳細な説明を受けた顕子さん。「65歳前は168万円で、65歳からは180万円ならそれなりの額かな」と思って安心します。ここで顕子さんは「ところで、死後離婚っていうのを聞いたことがありますけど、死後離婚したら遺族年金には影響ありますか?」と尋ねます。これについて職員は「死後離婚をしただけでは影響なく、遺族年金は支給されますよ」と回答します。どうやら、死後離婚をしても遺族年金は支給され続けることになり、顕子さんはさらに安心します。職員は続けて、遺族年金がなくなってしまうケースについても説明をします。
●遺族年金への影響がないことを知った顕子さんは、その後どのような決断を下すのでしょうか。後編【長年の悩みを「死後離婚」で解消し新たな人生へ…夫を亡くした60歳女性が、義家族との関係についに終止符を打てたワケ】で詳説します。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。