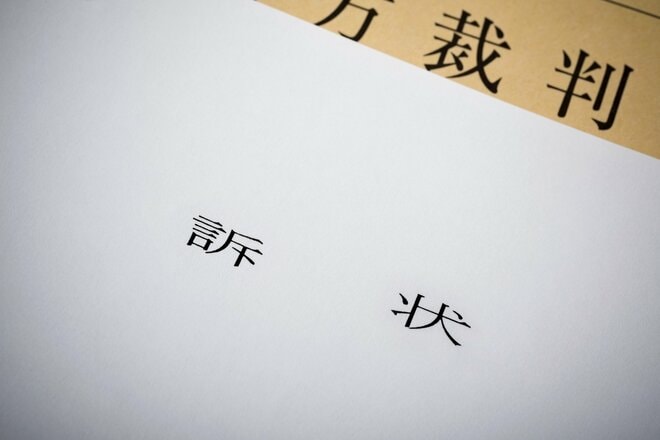<前編のあらすじ>
転勤を終え2年ぶりに実家に帰った長野さん(仮名・40代男性)は、父親の宗司さん(仮名)が住む家の雰囲気に違和感を覚える。机上に置かれた見慣れない起業資料に不審を抱き、父のパソコンを確認すると、ある若者に対して数カ月おきに数十万円を振り込んでいる履歴を発見。その総額は500万円にも上っていた。
詐欺を疑った長野さんが父に問いただすと、宗司さんは「仮にそうだとしても、それはそれで俺の責任だ。俺は、誰かの夢を信じたいだけなんだ」と予想外の返答。父がだまされている可能性を理解した上でなお支援を続けていることを知った長野さんは、深い絶望感に襲われる。
●前編:【「彼は立派な若者だよ」2年ぶりの再会で40代息子が絶句…謎の若者へ500万円も送金していた父の“真意”とは】
親の判断力がある限り、子にできることはない
これまでの経緯を話した上で、長野さんはようやく当事務所を訪れた理由について話し出す。
「このままじゃ父のお金が全部なくなる。どうにか若者に警告したい。内容証明を送って、今すぐ父の送金をやめさせたいんです」
だが、私は説明した。
「お気持ちはよく分かります。ただ、若者とお父様が“合意の上”でやり取りしている以上、法的に有効な方法で強制的に『止める』ことはできないでしょう。これはいわば贈与契約です。明確な詐欺の証拠もない現状、そこへ内容証明を送るのはおすすめできません。」
「でも……」
食い下がる長野さんに私は強く語りかける。
「いいですか? お父様には判断力があります。自分の意思で動いているんです。認知症を患われていたり、加齢や病気などがあり言動も目に見えておかしいなど、判断能力の低下が明らかであれば『成年後見制度』などの利用も考えられますが、今の段階ではそれも難しいでしょう」
その後、長野さんはうなだれた。
「じゃあ、僕には何もできないんですか?」
「厳しいようですが、そういうことになります」
いくら親子であっても、親の財産を法的に制限するのは非常に難しい。
日本の民法では、本人が自発的に行った贈与や出資行為は、その正当性が認められる。たとえ内容が子どもから見て不合理であっても、それだけでは無効にできないのだ。
仮にだまされていることに本人が気付いていたとしても、判断能力がある以上は「だまされても本人が納得している」こと自体が、相手に対する一種の“免罪符”のようなものになってしまうのだ。