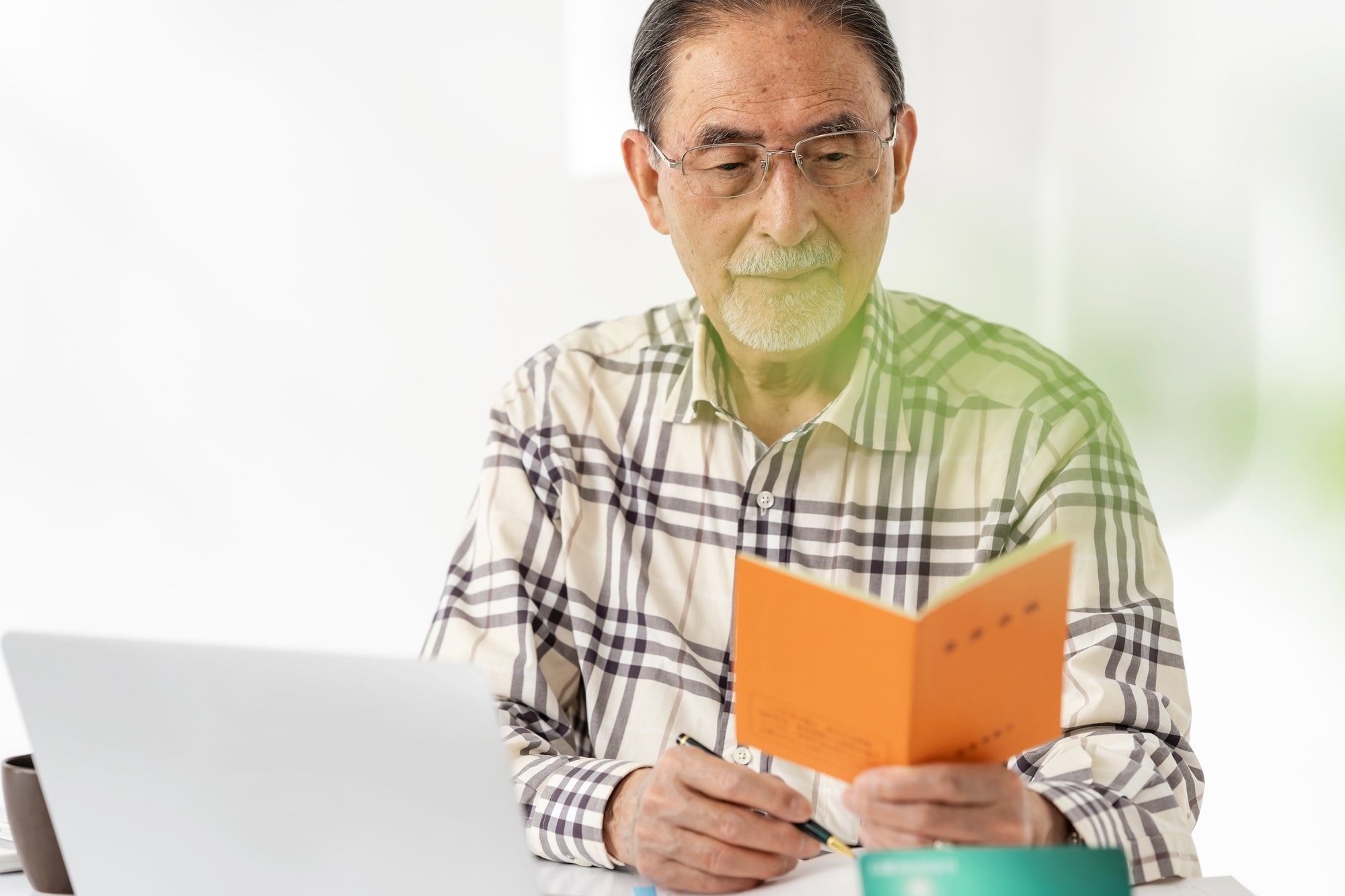老齢年金の障害者特例とは
では、代わりに受けられる老齢年金の特例とはどのようなものでしょうか。特別支給の老齢厚生年金(特老厚)は芳美さんの場合、63歳から65歳までの2年間受給でき、原則はその報酬比例部分の年金として受給できます。芳美さんの報酬比例部分は年間40万円程度と計算され、まず、こちらを2年分受給できることになっています。
しかし、障害等級1級~3級に該当する場合は障害者特例制度によって、報酬比例部分以外の年金も支給されることになり、障害等級3級相当の芳美さんも該当することになります。障害者特例の場合、障害厚生年金のように、障害についての初診日時点で厚生年金に加入していることは条件となっていません。
この特例により、まず、定額部分が支給されます。芳美さんの年金記録上は合計21年7カ月(259月)厚生年金に加入していました。定額部分は厚生年金加入1月につき年額1734円(2025年度)。1734円×259月で計算すると年間約45万円となります。そして、芳美さんは厚生年金の加入期間が合計20年以上あり、同居している年下の夫・雅史さんは年収850万円未満となっていることから、さらに配偶者加給年金も年間41万5900円(2025年度)加算されることになります。
芳美さんの特老厚は、報酬比例部分のみではなく、報酬比例部分、定額部分、配偶者加給年金を合計した額(年間約127万円)となり、これが2年分となります。なお、障害者特例は特老厚の制度であるため、65歳で特老厚がなくなって65歳以降の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が受けられるようになると障害者特例はありません。
早めの手続きが大事
こうして、芳美さんは障害年金の対象にはならなかったものの、2年間特例が受けられることで通常より多い老齢年金が受けられることになりました。障害者特例による定額部分や配偶者加給年金は原則、請求した月の翌月分からしか受けられないため、63歳になったらすぐに障害者特例も含め老齢年金の請求をすることにしました。
年金の支給開始年齢の引き上げによって、特老厚が受けられる人は将来的にはいなくなりますが、特老厚の対象となる場合で障害がある場合は、障害者特例制度や障害年金との違いについても確認しておくとよいでしょう。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。