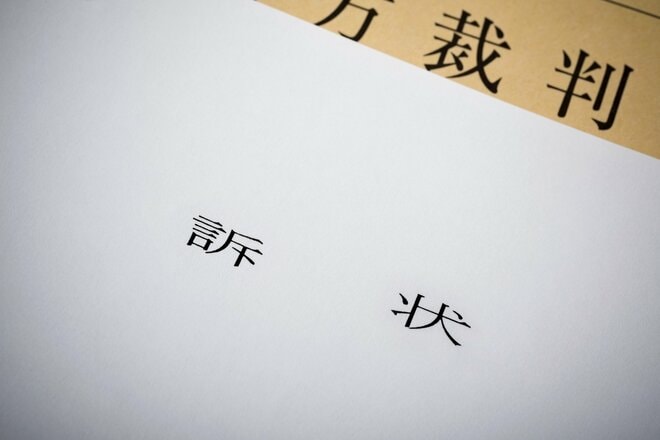開封後、次男が見せた複雑な表情
遺言の作成から9カ月後。寿子さんは入院し、半月後には帰らぬ人となった。
時が来て、遺言が開封される。開封後、次男は無言だった。しばし間があってからぽつりとつぶやいた。
「俺のこと、ちゃんと見てくれてたと思ってたけどな」
一方で、長男と長女は「話し合った結果なんだから」と言いつつも、後ろめたい部分もあったようでどこか申し訳なさそうな表情をしていた。
次男は寄与分の主張を検討し、弁護士に相談までしたという。しかし、実際の財産額はそこまで大きくなく、裁判を起こしても手間と費用ばかりがかさむ可能性が高いと分かったようだ。結局、裁判には至らず相続は遺言書どおりに行われた。
寿子さんは遺言の内容について「家族でちゃんと話してから決めたい」と望んだ。思いは善意だったし、間違ってはいなかった。
だが、家族が話し合う中で感情的な対立が表面化し、「なぜ私だけ」「なぜあの子が」といった不満が膨らんでしまうこともある。
相続というものは単に財産を分けるだけでなく、「人生の評価」や「親との距離感」までが問われる場でもある。それが遺言書という形で表現されるとあればなおさらだ。
皮肉にもきょうだいをぎくしゃくさせた遺言書
相続の結論が出た後、きょうだい3人は必要以上に連絡を取らなくなった。
「仲良くしてほしい」。そう願って作られた遺言書が、皮肉にもきょうだいたちの関係をぎくしゃくさせる結末になってしまったのだ。
遺言書は法律的に正しくても、感情的に受け入れられるとは限らない。介護や看護の貢献を評価する制度はあるが、それを遺言にどう反映させるかは最終的に本人の判断に委ねられる。そのため、遺言書の作成者が自らの考えを記載するにとどめれば、相続人たちは納得することも珍しくはない。
しかし、「家族と話し合ってから決めたい」と話し合いの場を設けてしまうことで、かえって争いを生んでしまうこともあるのだ。
相続は単なる財産分配ではない。「親の人生」「子どもの思い」「家族の関係」が複雑に絡み合う。あなたが遺言書の内容を決める時、内容について話し合いを望むなら、それが本当に必要であるか、全員にとって“納得できる対話”として実施できるか、いま一度考え直してほしい。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。