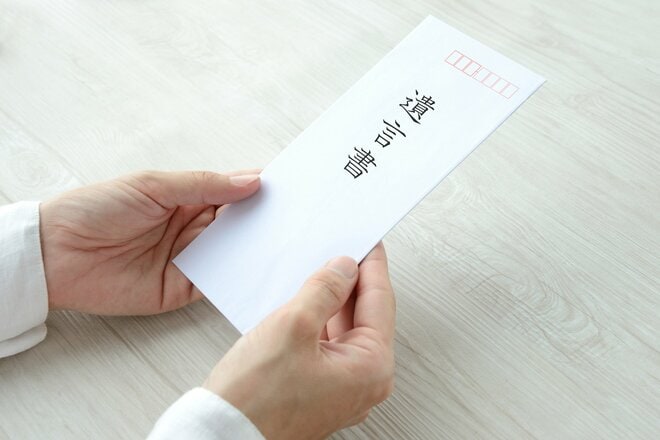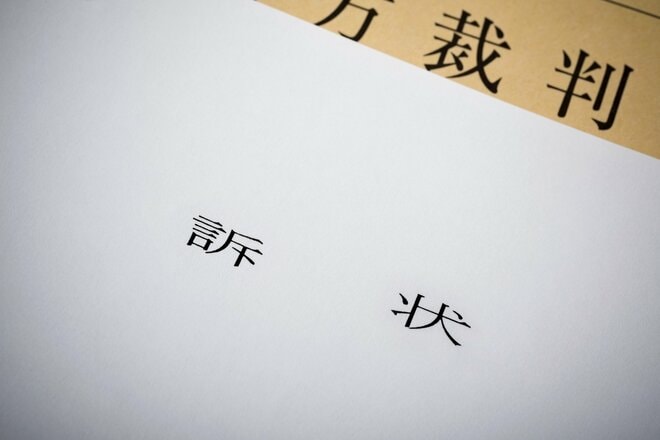<前編のあらすじ>
78歳の寿子さん(仮名)は「相続で子どもたちに揉めてほしくない」という善意から、専門家である筆者に遺言書の作成を依頼した。しかし、遺言内容を家族との話し合いで決めようとしたところ、思いがけず家族の溝を深めることになってしまう。
寿子さんが家族会議を開き、3人の子供たちに遺言内容を相談したところ、長年にわたり寿子さんの介護を担ってきた次男が反応。「俺が一番近くで世話してきたことは、みんな分かってると思う。だから、それなりの分け前があってもいいんじゃないか」と主張した。一方、長男と長女は財産は平等にすべきと反発し、話し合いは「誰がどれだけ貢献したか」を巡る論争へと発展した。
●前編:「相続で子どもたちに揉めてほしくない」78歳母が開いた家族会議が、思いがけずきょうだい分裂を招いた「まさかの理由」
「寄与分」制度があっても実現は困難
ここで話を法制度の方に変えよう。法律上、親の介護や看護などに特別に貢献した相続人には「寄与分」という制度がある。寄与分が認められた相続人はその働きが評価され、遺産を他の相続人よりも多く相続することが認められる。
だが、これを実現するのは容易ではない。対象となるには「相続財産の維持や増加に寄与した」と認められる必要がある。ただ単に介護をしただけでは足りず、それによって財産に対する一定の効果がなければ相続においては評価がなされないのだ。
さらに、実際に寄与分を実現させるには相続人間でそのことについて合意があるか、家庭裁判所の調停を経るといった過程が必要になる。相続手続きは各自が勝手に行えるというものでもないからだ。
寿子さんはこの仕組みの存在を知った上でこう語った。
「確かに、次男はよくしてくれた。でも……だからって他の子を冷遇するわけにもいかない。きょうだい仲良くしてほしい、それが一番の願いなんです」
そうして寿子さんが作成した遺言書は、子ども3人に平等に相続させるという内容となった。家族会議で話し合っていたため一応の納得はあるものの、相続する財産の金額で見れば、次男の正樹さんの相続分はその貢献に見合わないものとなってしまった。