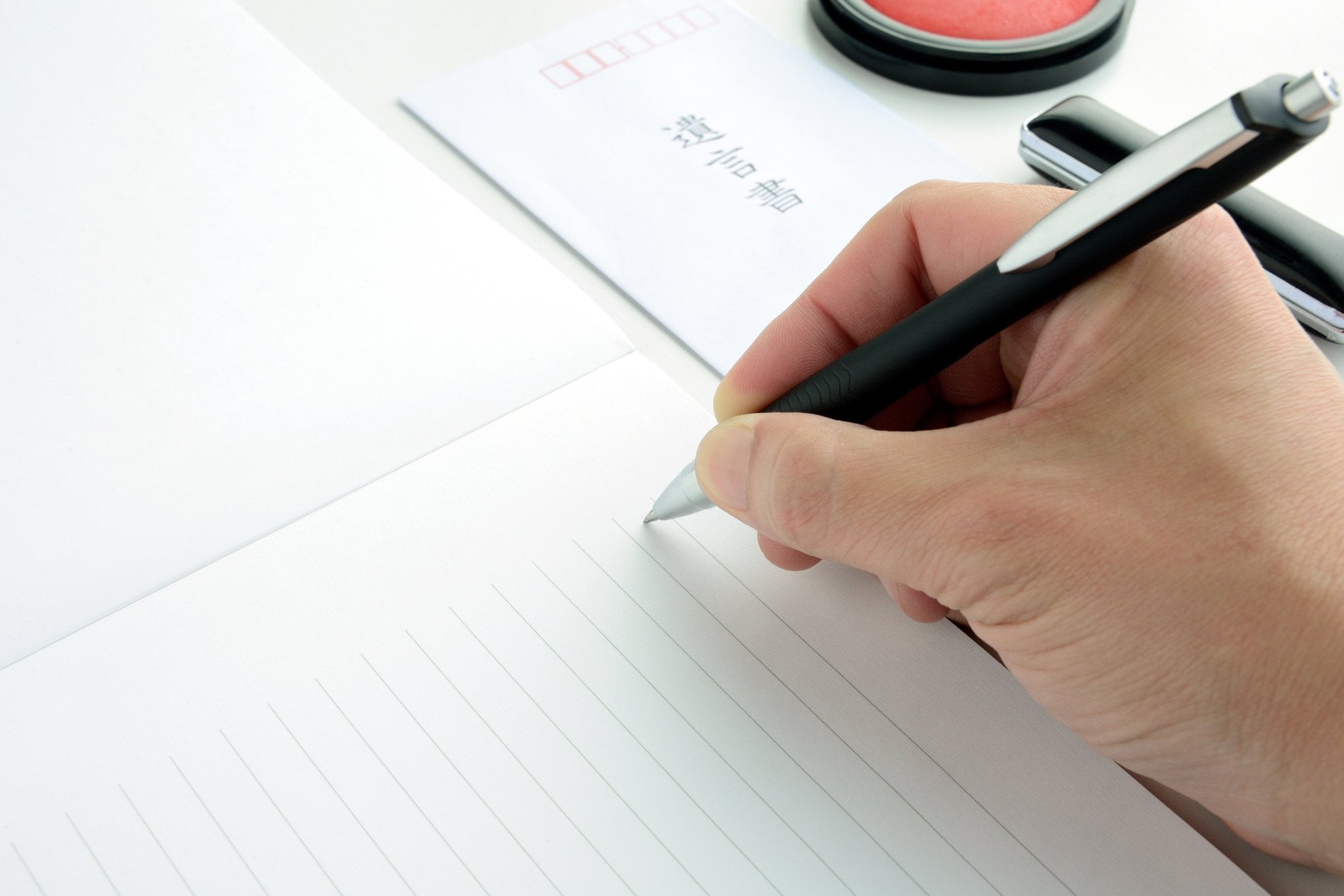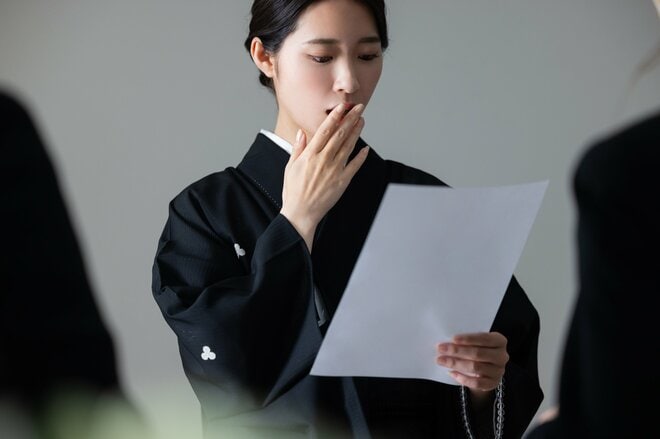「兄貴が全部取るつもりだったんだろ?」決裂した兄弟の絆
「結果として、最初に作成された遺言書が有効と判断されました。新しい遺言書は遺言者の真意が明確でなく、信頼性が低いことなどが理由だと言われたんです」
兄の一郎さんが私にそう語りかける。
こうして、兄・一郎さんがすべての遺産を相続する形で手続きは完了。しかし、弟・徹さんとの関係は完全に決裂したようだ。
一郎さんに頼まれて一度だけ弟の徹さんと会って話をしたのだが、「結局、兄貴が全部取るつもりだったんだろ?」と最初から疑ってかかり、「こうなるのは分かってたんだ」と取り付く島もない状態だ。
それ以降、私も一郎さんも、徹さんとは一度も会っていない。
遺言書は“死後の最後のメッセージ”
今回紹介した事例は、「遺言は自分で書ける」という事実の裏に潜む危険性が如実に感じられるものである。
遺言書はたとえ形式上は有効な自筆証書遺言であっても、内容に矛盾があれば、それが争いの火種になる。
遺言者はすでに亡くなっているため、その真意を誰も確認できないのだ。
特に遺言書の書き換えは、前の遺言書との整合性や処分についてまで考えて作成しないと、相互に矛盾する2通の遺言書が存在することになってしまう。
遺言書の作成は必ず専門家に相談するべきだ。
遺言書は“死後の最後のメッセージ”であり、家族への思いやりが詰まっているべきものだ。その思いが形として正しく伝わらなければ、それは遺言者の意に反して簡単に“争族”の引き金となってしまう。
もしあなたが遺言書の作成、特に書き換えを考えているなら——たった一言、「遺言書について相談したい」と、専門家に相談することから始めてほしい。それが、真に家族のための遺言書を遺すのに必要な第一歩になるのだから。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。