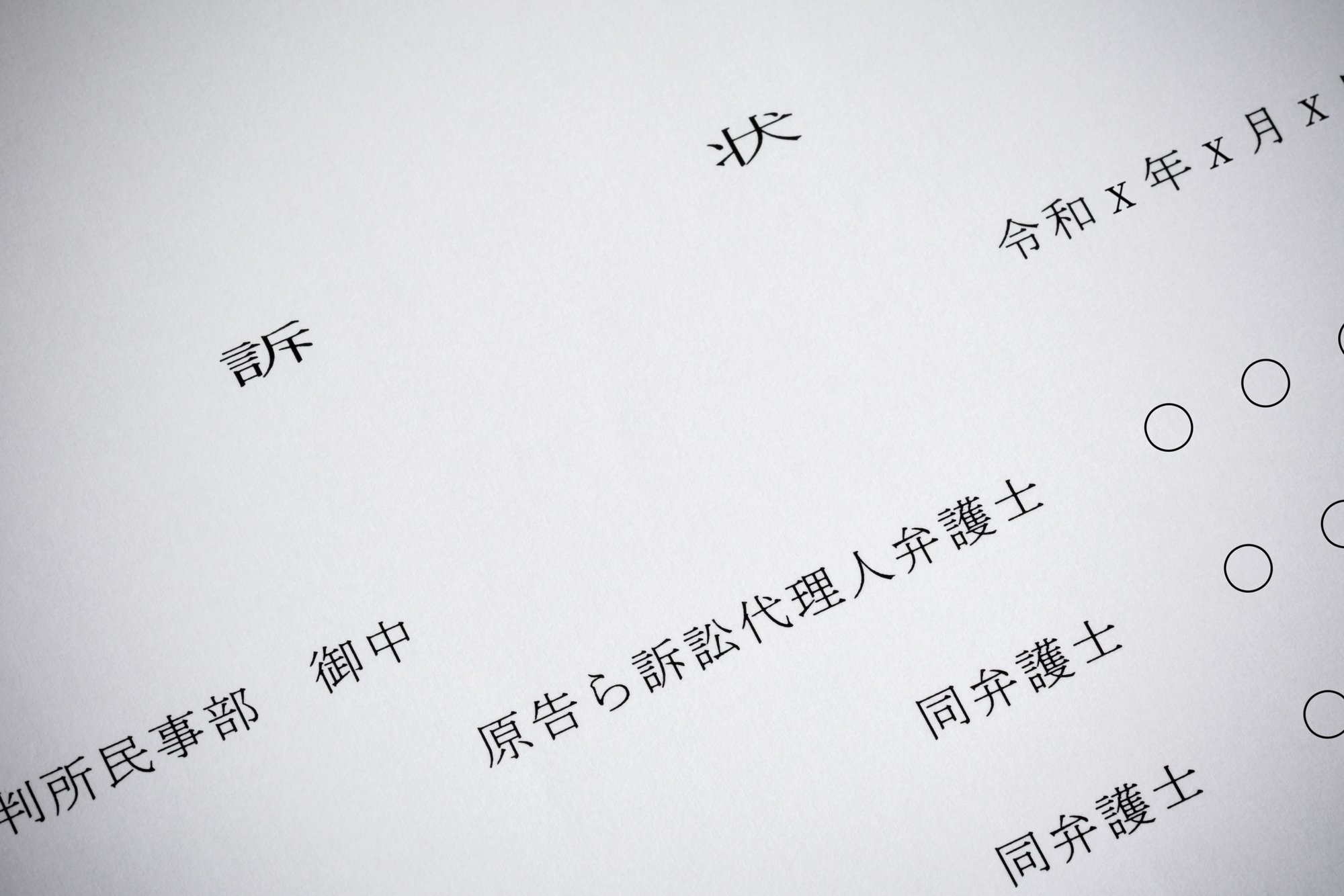どうせ打てないから
そのあと、勇悟は2球ほど見送り、ボールカウントは2-2になる。どうやらボールが4つでフォアボールというやつらしく、勝負は優の負けになるらしい。
「優、落ち着いていこう。勇悟はどうせ打てないから」
「おい、兄さん、馬鹿にするなよ。絶対に打つ」
勇悟の表情は真剣だった。素振りは相変わらず立派だが、日頃の運動不足のせいか、その鋭さはさっきよりもだいぶ鈍くなったように見えた。
「優、あと1球だよ!」
栄子もマウンドへエールを送る。優はうなずき、投球モーションへと入った。
果たして、投じた渾身の5球目も山なりのボール。勇悟は全力でバットを振り抜いた。
――ごっ。
と、鈍い音がした。「お母さん!」と叫ぶ優の声がした。ボールは栄子の左手側に高く浮き上がっていた。
栄子はボールを追いかけて斜め左前に走った。事前にフライだったら捕ればそのままアウトになると、将吾に説明を受けていた。だから左手にはめたグローブをボールに向かって伸ばした。しかし左手に何かが収まった感触を得た瞬間、太もものあたりに何かがぶつかって、栄子の見ていた世界はぐるりと1回転した。
「お母さん!」
「栄子!」
いくつもの声が重なって聞こえた。頭を打ったのか、起き上がっているはずなのに視界がぐわんぐわんと揺れた。けれど駆け寄ってくる3人の姿だけははっきりと見えていた。
「お母さん、大丈夫?」
「栄子、頭打ったんじゃないか?」
どうやら栄子はベンチに激突して転んだらしかった。勇悟と優は同じ顔をしながら栄子のことを覗きこんでいて、その必死な様子がだんだんおかしくなってきて、栄子は込み上げる笑いを抑えておくことができなくなった。
「どうしよう、お母さんがおかしくなった……」
「やっぱり頭を打ったんじゃないか?」
「大丈夫。2人がそっくりな顔でこっち見てるから、おかしくなっちゃって」
笑いすぎで潤んだ目元を拭いながら、栄子は大事なことを思い出す。
「そうだ、ボール。私、ちゃんと取れてた?」
栄子は左手にはめたままのグローブを見た。ボールはまだ、グローブのなかにちゃんと収まっていた。
「ファールフライでアウトだ。栄子ちゃんのファインプレーでゲームセット。優の勝ち」
将吾が目を丸くしながら、拍手をした。優はガッツポーズをして喜んだ。
「もう1回だ、もう1回」
「いやいや、勇悟。勝負は1打席。優の勝ちで野球始めるのは決まりだろ」
「そんなことは分かってる。でも、父親として負けたままじゃ終われないだろ。ほら、優。もう1回勝負だ、勝負」
勇悟はバットを振りながらバッターボックスに戻っていく。優はどうしたものかと、その場で戸惑っている。
「優、お母さんは平気だから、お父さんと遊んでおいで。こてんぱんにやっつけてきて」
「分かった!」
優は走ってマウンドに戻っていく。栄子はベンチに腰かけて、その様子を眺めている。
やっぱり、プロだとか甲子園だとか、そんな目に見える成果だけがスポーツの価値じゃないじゃない。真剣な表情でバットを構える勇悟と、嬉しそうにボールを投げる優を見ていれば分かることだった。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。