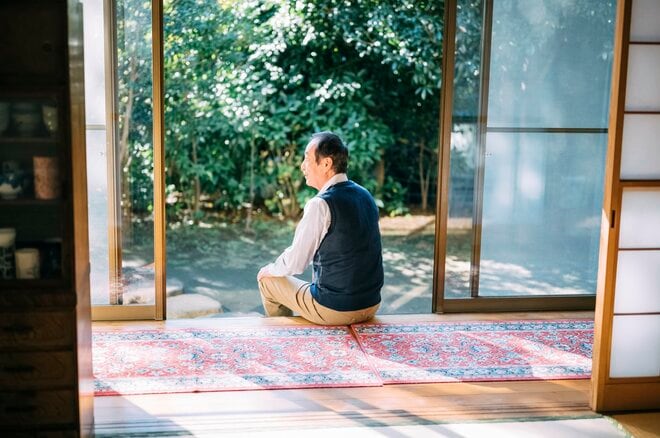認知症で資産が凍結という現実と、家族が取れる対策
今回の事例のように、認知症により資産が凍結し自由に使えなくなってしまうケースは珍しくありません。
特に、近年ではNISAブームによりシニア世代の投資信託、株式投資が増えていますが、その弊害として今回と同様に「家族であっても手続きできない」ということになってしまう可能性もあります。
ですので、こういった事態を避けるためには認知症になる前に、まだまだ判断力があり元気なうちに対策を行うことが重要です。
例えば、家族信託や任意後見制度の利用、生命保険の活用等の選択肢があります。
生命保険は「指定代理請求人」を指定しておくことで家族が給付金を請求したりできる制度や、契約者に代わって解約手続き等を行うことができる制度があり、高齢期での生活資金や介護資金を準備することはとても便利です。
リタイア時の資産運用を考える際には、まだ早いと思っても先々のこういったリスクを見越して、何の資産をどの商品で運用するか、自分に判断能力がなくなった場合にはどう管理するかを事前に考え、対策しておきましょう。
資産は「使える状態」にしておく
認知症や介護状態は長生きの時代、すべての人に起こりうることで、今回のように家族が困ってしまうことも考えられます。
いざそうなってしまってからでは手遅れですので、まだ元気なうちに、何のためのお金を、どうやって管理するか、もし判断能力が失われたら誰にそれを任せるか、介護費用はどう準備するかを計画しておくことが重要です。
資産がいくらあっても、「使える状態」でなければ意味がありません。
老後の安心は、資産の大きさだけでなく、家族が困らない仕組みづくりが大事です。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。