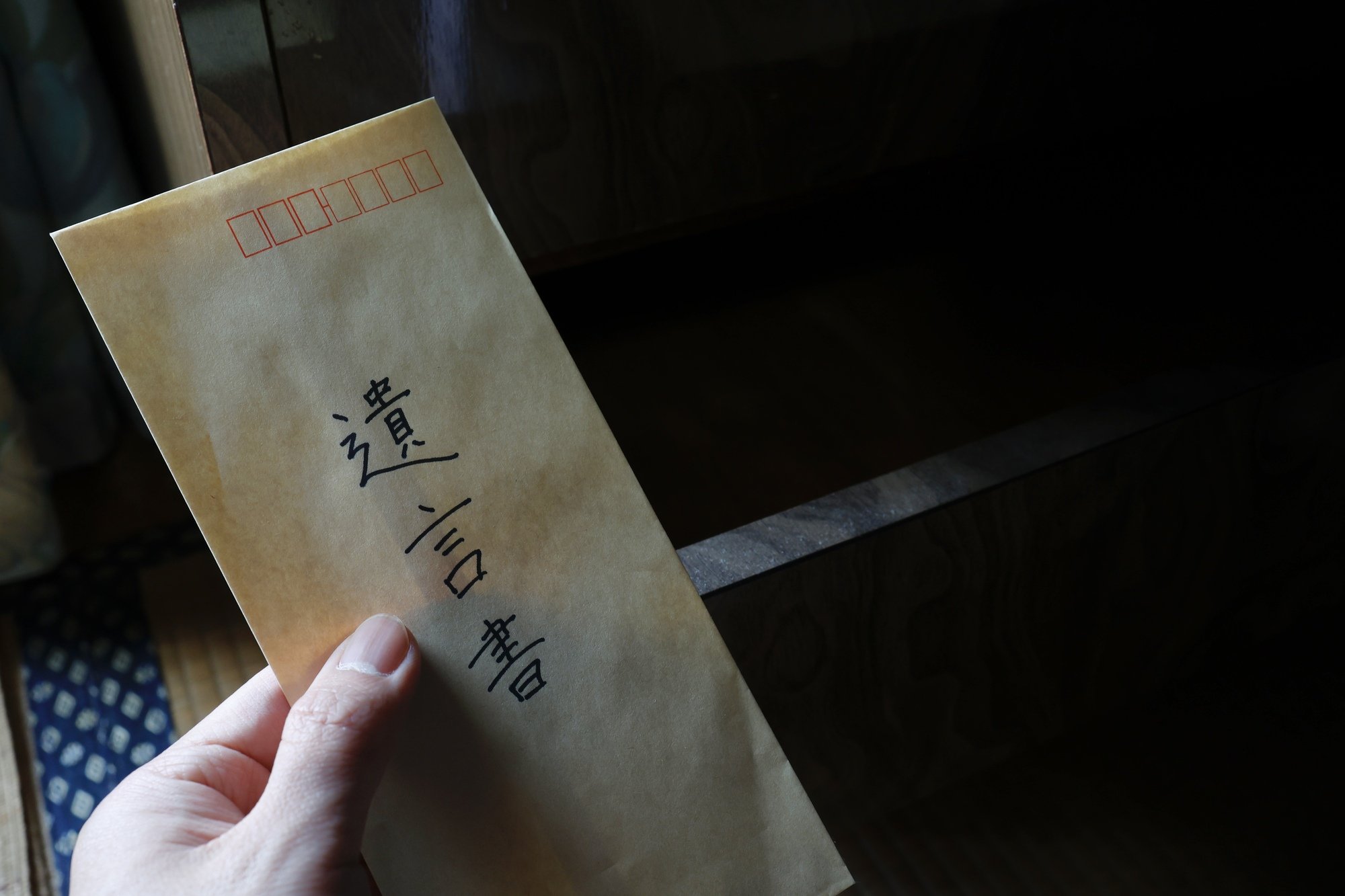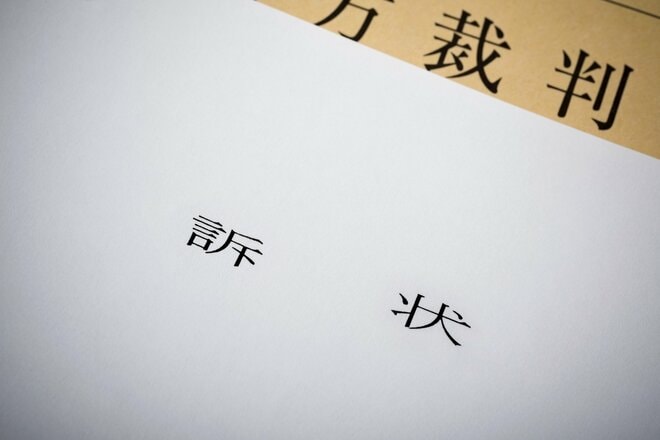間違った請求には毅然とした対応が必要である
すべての話を聞き終わった後に私は彼女にこう切り出す。
「本件は事故物件ではないでしょう。内容証明で納得できない旨をはっきり主張しましょう」
里見さんの母親の死は事件性も社会的インパクトもなく、亡くなった直後に発見された。つまり“ごく自然な最期”であり、物件の評価に法的観点からマイナス影響を与えたとは言い難いからだ。
そして私は次のような内容で書面を送付する。
「母親の死因は老衰であり、自然死と確認されています。遺体は死後翌日に発見され、室内に損傷や異臭はなく、特殊な清掃等の必要もありませんでした。このような場合、事故物件に該当せず、貴殿が主張する損害賠償義務は発生しないと考えます」
さらに、過去の判例をいくつか提示し、「自然死や病死で事故物件とされた例は極めて限定的である」ことも丁寧に説明した。
すると、それ以降大家さんからの連絡は数年たった現在もない。あるとすれば送付から数日後に、文字にするのもはばかられるような捨て台詞が里見さんの留守電に入っていたくらいだ。
その後の里見さんは…?
私は本記事を書くにあたり久方ぶりに里見さんにコンタクトを取った。
当時について彼女は「静かで穏やかな旅立ちだった母の表情がかき消えるほどの衝撃がありました」と振り返る。
家族の死という大きな喪失の直後に、「事故物件」「損害賠償」といった言葉を突きつけられるのは、遺族にとってあまりに酷な現実だ。
近年、高齢者の一人暮らしが増える中で、自然死であっても過敏に反応するオーナーや不動産業者が少なくない。
事故物件の定義について正しい知識を持ちながら、その言葉が持つインパクトから金銭の請求に悪用されている事件もある。
そういった事件から身を守るために重要なのは、「自然死は原則事故物件には該当しない」という法的な解釈があるという事実を知り、理不尽な請求には毅然と対応する姿勢だ。
今回の事件を振り返り、里見さんはこう語る。
「親が亡くなった後にトラブルが起こる可能性もあります。それに備え正しい知識と準備を持っておくことが重要だと感じました」
彼女の発言に私は全面的に同意する。高齢者の一人暮らしにあたっては、生きている今のことだけを考えるのでは足りないのだろう。死後のことまで考えておくことが現代の終活や介護に求められる新たな視点かもしれない。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。