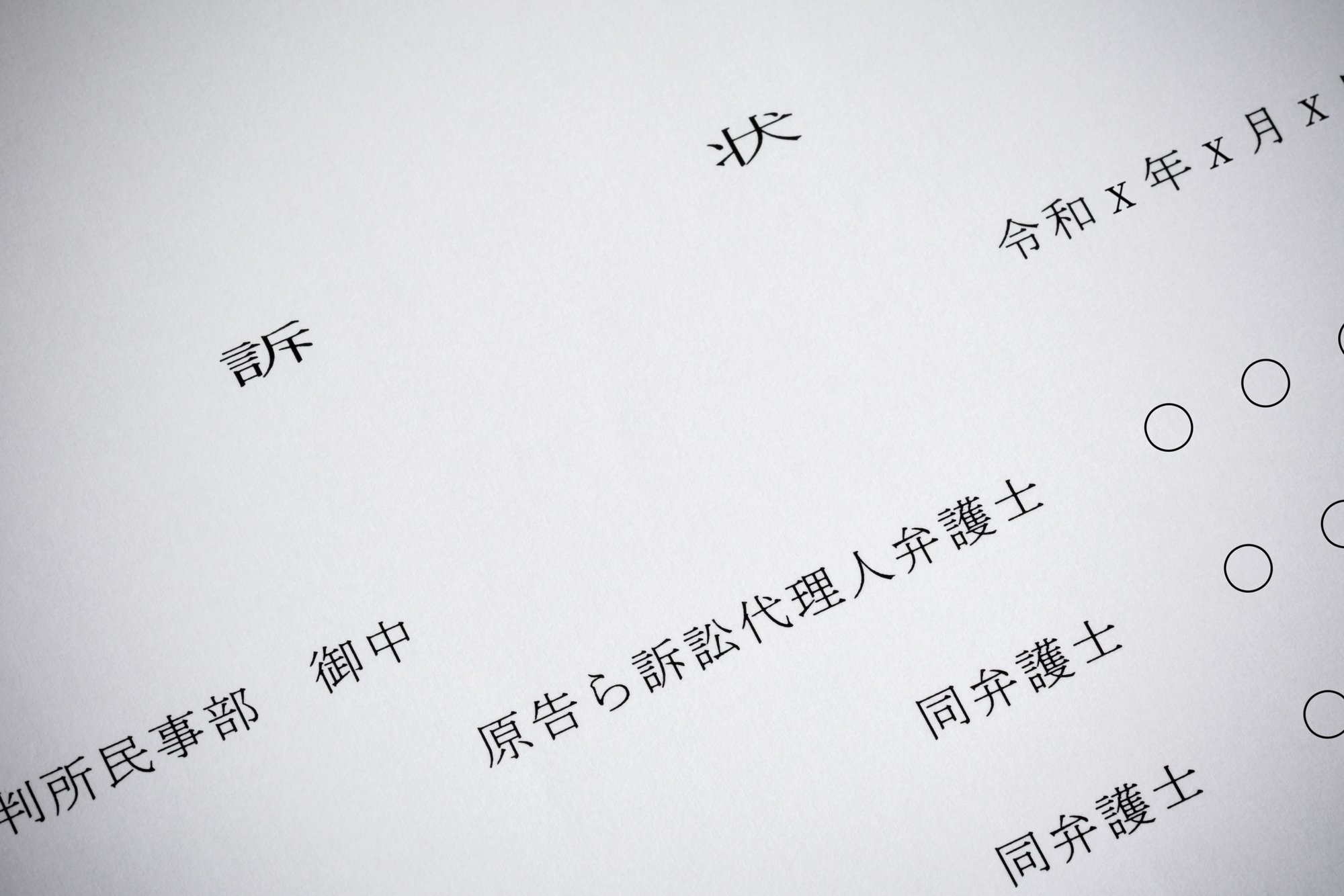なぜ娘はラウンジにいたのか?
有希は黙っていた。夏子はテーブルに運ばれてきたお冷で唇を湿らせ、小さく息を吸って切り出した。
「静香ちゃんから、連絡がつかないし家にもいないって連絡もらったよ」
「そう……」
「家、帰ってないの?」
「……」
「大学も、行ってないの?」
「……」
「何で黙ってるの?」
有希は黙りこんだままだった。高校のときとは見違えるような丁寧なメイクをしているはずの顔はテーブルやソファの紺色を反射しているのか、心なしか青白く見えた。
夏子は胸のうちにあった不安を、お冷で流し込んだ。無事なことは分かった。
「別にね、連れ戻そうっていうんじゃないの。悪いことしてるんじゃないんだから。心配はしたけどひとまずは無事だって分かったし」
「連れ戻しに来たんじゃないの?」
「なんでそんなことするのよ」
「え」
顔を上げた有希がばっちりとアイラインが引いてあるおかげでくっきりとした存在感を主張する目をさらに大きく見開いた。
「こういう仕事って、時給もいいもんね。それに、こういうところで色んなお客さんの話聞くのが面白いのも分かる。私も短大に通ってたときはスナックで働いてたことあるから、なんとなくだけど」
「お母さんも?」
「私はこんな豪華な店内の綺麗なお店じゃなかったけどね」
「そうなんだ」
有希はほっとしたように息を吐いた。頭ごなしに叱りにきたわけではないと分かって安心したらしい。だが夏子は「それで」と語気を強めた。
「別にお金に困って働いているとかじゃないのよね?」
「……うん、友達に誘われて体入してみて、時給もいいし、仕事も面白くて」
「そう。今、どこに泊ってるの?」
「お店の近くの、先輩のマンション……」
夏子はため息を吐く。
「別に犯罪とかに巻き込まれなければ、どんなことしてたって文句は言わない。でも大学にはちゃんと行くこと。家にもちゃんと帰ること。学費とか仕送りとかしてるんだから、これくらいは要求させてもらうからね」
「じゃあ、辞めなくていいの?」
「そのふたつが約束できるならね。もちろんお父さんには言えないから、内緒にしておく」
「お母さん、ありがとう……」
「あと、それと、連絡はちゃんと返すことと、静香ちゃんに迷惑かけないこと。すごく心配してたから、あとでちゃんと謝っておきなさいよ」
夏子はそれだけ言って立ち上がった。有希はもう帰るのかという顔をしていたが、これ以上話しても説教臭くなるだけだったし、それ以上に昨日から不安で生きた心地がしなかったこともあり、夏子はひどく疲れていた。
「あ、だけど最後にひとつ。いくら稼げるからって、お金の使いすぎは気をつけなさいよ。部屋の段ボール、散らかしっぱなしなんてありえないからね」
「見たの⁉」
夏子は驚いている有希を置いて歩き出す。入口へ続く廊下にはさっきのスーツの男と黒服が立っていて、深々とお辞儀をしてきた。
「うちの子、浮ついててご迷惑をおかけすることもあると思うんですが、よろしくお願いいたします」
夏子は彼らに頭を下げ、店を後にした。東京の夜はまぶしいくらいに明るく、夏子は思わず目を細めたが、肌を撫でていく風は住む町と変わらない春のにおいがする。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。