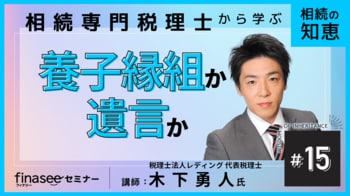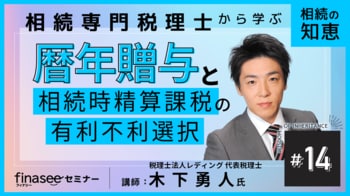親子水入らず
茜は母に事の経緯を説明し、母は茜に何度もお礼を言っていた。私は何もしてなくてと恐縮しきってしまった茜は「じゃ、後は親子水入らずで」とみやびの気も知らずに帰っていった。
様子を見に来た医者が病室を出て行ってしまうと、みやびと母親は病室で2人きりになった。
「……来なくて良かったのに」
みやびはぶっきらぼうにつぶやいた。レースカーテン越しに、夕焼けが見えた。燃えるようなグラデーションの赤は、私の親不孝を罰しようとしているのかもしれないと思えた。
「足、しんどいんでしょ?」
「まあそうなんだけどねぇ。でもクラゲに刺されるよりはましよ。それに過度な年寄り扱いはだめなのよ。甘えてダメになるでしょ」
痛むのか、母は膝をなでていた。
甘えたらいいじゃないか、とは言えなかった。母がどれだけ頑張ってきたか、みやびはよく知っている。もう頑張る必要なんてないと、母に伝えてあげたかった。
「お母さん……ごめんなさい」
みやびはあの日以来、ずっとため込んでいた心の澱(おり)を絞り出す。母は目を丸くして、ほほ笑む。
「なんで謝るのよ。クラゲに刺されたのは、みやびのせいじゃないでしょ」
「そうじゃなくてさ」
言いかけたみやびの言葉を遮って、小さくうなずいた母はみやびに向けて手を伸ばした。
「立派になった。でも、目の下のクマ。あんた、ちゃんと寝てる? みやびは私に似て、根詰めすぎるところがあるから、気を付けないとダメよ」
母はみやびの髪をなでた。いつもあかぎればかりで痛々しく、しかしたった1人で自分を育て上げてくれた、この世界で何より頼もしい、母の手。
みやびの目から、いつの間にか大粒の涙があふれていた。
「……ありがとう、お母さん」
「いいのよ。母親っていうのはさ、娘が元気にやってたら、それだけで幸せになれるんだから」
「何それ……後悔してないの?」
「後悔? 何に後悔しなくちゃなんないのさ」
「私を、産んだこと」
ためらいがちにつぶやいた言葉を、母は笑って蹴とばした。
「バカだね。そんなわけないだろ。みやびが生まれたおかげで、私の人生は最高だったんだから」
母の手がみやびの頰を優しくつねる。小さいころ、いたずらをしたみやびを母がそうやってしかってくれたことをふいに思い出す。
「どこで何をしてたって、みやびは大切な娘だよ。後悔なんてとんでもない。いつも感謝してたくらいなんだから」
後はうまく言葉にならなかった。
みやびのすすり泣きだけが響く静かな病室の中で、少ししわの増えた母の手はいつまでもみやびのことをなでてくれていた。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。