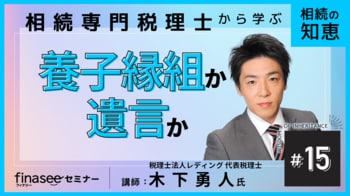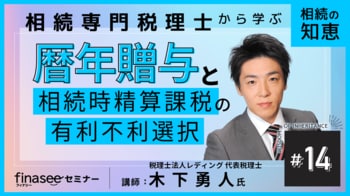みやびはこの日のためにわざわざ買ったビーチサンダルを履いて、焼けつくような砂浜の上に立っていた。海に反射した太陽の光は、容赦なくみやびの目の奥を突き刺した。
「みやびちゃーん! こっちだよー!」
「早く早くー!」
しばらく立ち止まって海を眺めていたみやびは、元気な子供たちの声でわれに返った。
「はーい! 今行くよー!」
声を張り上げたあと、みやびはゆっくりと声の方へ歩き始めた。
晴れやかな天気とは裏腹に、みやびの心は重く沈んでいた。
今日は大学からの友人である香里と茜と一緒に海水浴に来ているのだが、みやびは憂鬱(ゆううつ)だった。すでに彼女たちは結婚や出産を経験しており、今日も当然のように子連れでの海水浴になっていることが原因だった。
「騒がしくてごめんね。佑都は、みやびのこと大好きだからさ」
「うちのも慶介もおんなじ。『早くみやびちゃんに会いたい!』って駄々をこねてたよ」
砂浜にパラソルを設置しながら、2人が声をかけてくる。
もともとは大学時代のサークル仲間で、思い返せば当時はいつも一緒に行動していた。卒業して就職したり、2人が家庭を持ったりしてからも、ときどき集まってはとりとめのない話をする関係が続いている。
「本当? 2人とも懐(なつ)いてくれてうれしいわぁ。ついに私にもモテ期が来たかも」
みやびは明るさを装って冗談を言いながら、胸の奥ではサボテンを触ってしまったときのような鋭い痛みを感じていた。
ちょうど茜が、海の家に食べ物を買いに行ってくれているので、みやびと香里は2人きり、波打ち際ではしゃぐ子供たちを眺めながら、パラソルの下に敷いたレジャーシートの上に座った。
「みやび、最近どう?何か変わったことあった?」
「まあ……普通かな。仕事が忙しくて、毎日帰って寝るだけの生活だよ」
みやびは簡単に答えたが、心の中では違うことを考えている。
立派に母親をやっている彼女たちを見ると、どうしても後ろめたさを感じてしまう。もうここ何年も、そんな風に母の顔へ変わっていってしまった友人たちとの距離感を、みやびはうまくつかめずにいた。
「そうなんだ。私も毎日子育てが大変でさ。でも、子供の笑顔を見ると疲れも吹き飛ぶよ」
「そうだね、子供たちの笑顔は本当に癒やされるよね」
「みやびはどう? いい相手いないの?」
「そういうのは全然かな」
「まあ、結婚も良しあしあるからね。今は結婚するのが幸せ、なんて時代でもないし」
香里はそう言って笑ってくれたが、実際に結婚して子育てをしながら幸せそうな顔をしている彼女の言葉に説得力はなかった。
みやびはほほ笑んでみるが、自分でも笑顔がぎこちないのが分かる。
母の赤くひび割れた手を思い出す。白くなった髪は染めなきゃねという割にいつまでたっても染められることはなかった。