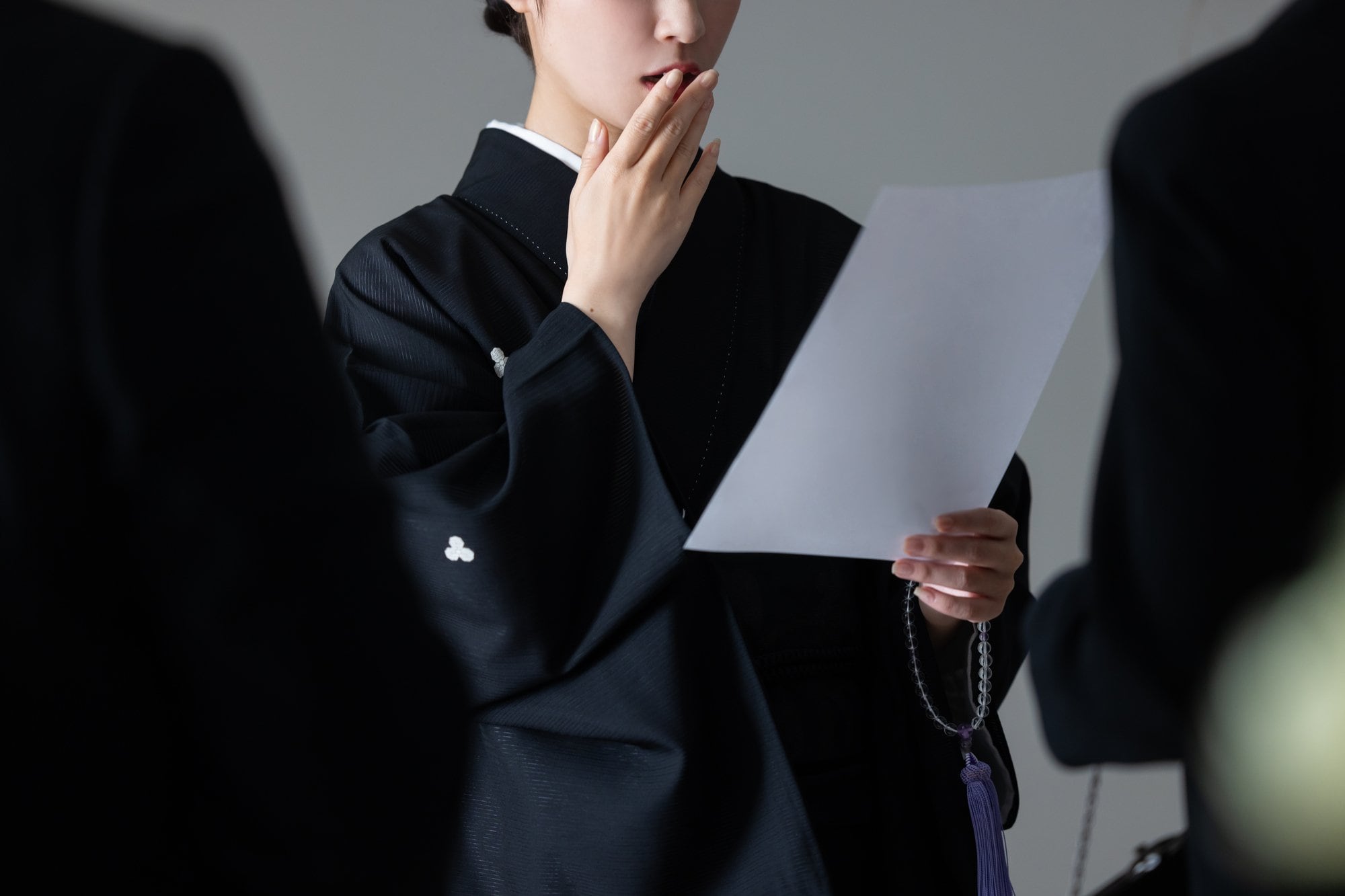思ってもいない「言葉」
「……何の用だ」
昭一は目を細める。ジャンパーのチャックを一番上まで上げた。
晃だと名乗る男は昭一を見下ろしていた。出て行ったときはまだ高校に上がったばかりで小柄だった息子とは似ても似つかなかったが、右のこめかみに残る縫い痕は、たしかに昭一の暴力がかつて息子に負わせたけがだった。
「寒いから入れてくれよ」
晃は昭一を押しのけるようにして家のなかへと入ってくる。昭一はされるがまま晃の侵入を許してしまう。
「ひどい臭いだな。掃除とかしてないだろ。大丈夫なの?」
「お前には関係ないだろう」
「まあそうだけどさ」
晃はつま先立ちで歩きながら、脱いだまま床に放置している洋服を足で脇へとどかしていった。「うっ」と小さくえずくような声を漏らしていた。昭一はだんだんと恥ずかしくなり、ゴムの伸びた寝間着の太もものあたりを強く握った。
「もしさ、あんたがいいなら、一緒に暮らさないか? 嫁も構わないって言ってくれてる。息子は京都の大学だし。あんたを養うくらいの蓄えはある。さすがにこんな生活、みじめだろう」
どうしてこの男は突然現れて、自分のことを辱めるのだろうか。
どうして顔も名前も知らない赤の他人の女から勝手に住むことを許されなければいけないのか。
どうして今の生活がみじめだと決めつけるのか。
どうして、どうして、どうして――。
「あいつが、芳美がいるだろう……」
「母さんは死んだよ」
座るところがないと諦めたらしい晃は、昭一のほうを見ることなく言った。昭一は喉の奥がひくりと音を立てたような気がした。
芳美が死んだ。判然としない頭のなかで、その事実を何度も繰り返してかみ砕こうとした。
「もう葬儀とかは終わってて、先週四十九日も終えたとこ。せめて報告くらいはしてやろうと思ってさ」
「なにを今更。あいつは……あれだ、もう35年前に死んだようなもんだろう。俺の家から出て行ったんだからな。どうでもいい」
混乱しているのに、言葉だけははっきりとこぼれた。一体自分のどこから、こんな思ってもいない言葉がこぼれたのか、昭一には分からなかった。
「それ、本気で言ってんの?」晃が目を細める。「やっぱろくでもねえ男だな、あんたは。失望したよ。こんなゴミためみたいなところで暮らして、人として終わってるよ」
晃は舌を打ち、やはり昭一を押しのけるようにして玄関へと向かっていく。肩と肩が交差する瞬間、「来なきゃよかったわ」と晃が吐き捨てた。
「じゃあな。もう二度と会うこともないだろうけど」
扉が勢いよく閉まる。入り込んだまま出口を見失っていた冬の冷気は、あっという間によどんだ空気にのみ込まれていった。
晃が立ち去ったあとも、昭一はしばらくその場に立ち尽くしていた。
羞恥心といら立ちが胸中でとぐろを巻き、芳美が死んだという事実がかろうじて保たれていた何かに亀裂を入れていく。
「あああああああっ!」
声を荒らげる。壁を殴りつける。しかしかつてのように穴は開かず、壁を打った拳だけがひたすらに痛んだ。心臓が脈打つ。皮膚が怒りにあわ立っている。
「——っ」
突如襲い掛かった痛みに、昭一は胸を押さえてうずくまった。息ができなかった。
必死に床をはい、ちゃぶ台の上の芳美の写真に手を伸ばす。
カーテンの隙間から差し込む光が、昭一の世界を穏やかな金色に染めていった。
●決別してしまった昭一と晃はふたたび分かり合う事ができるのか? 後編「ゴミまみれの部屋で孤独死をした父… 遺品整理で見つけた“意外な”モノ」にて、詳細をお届けします。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。