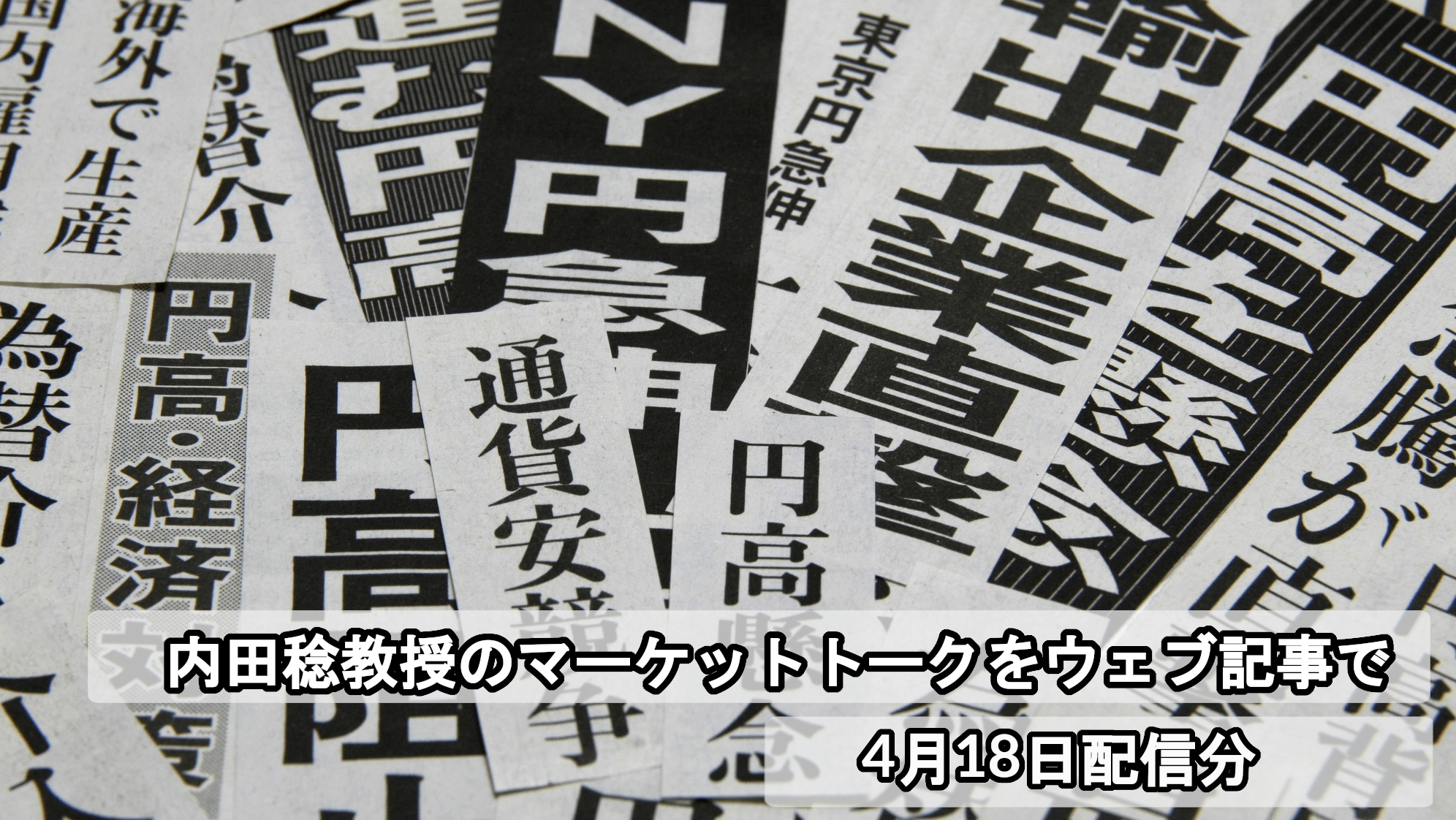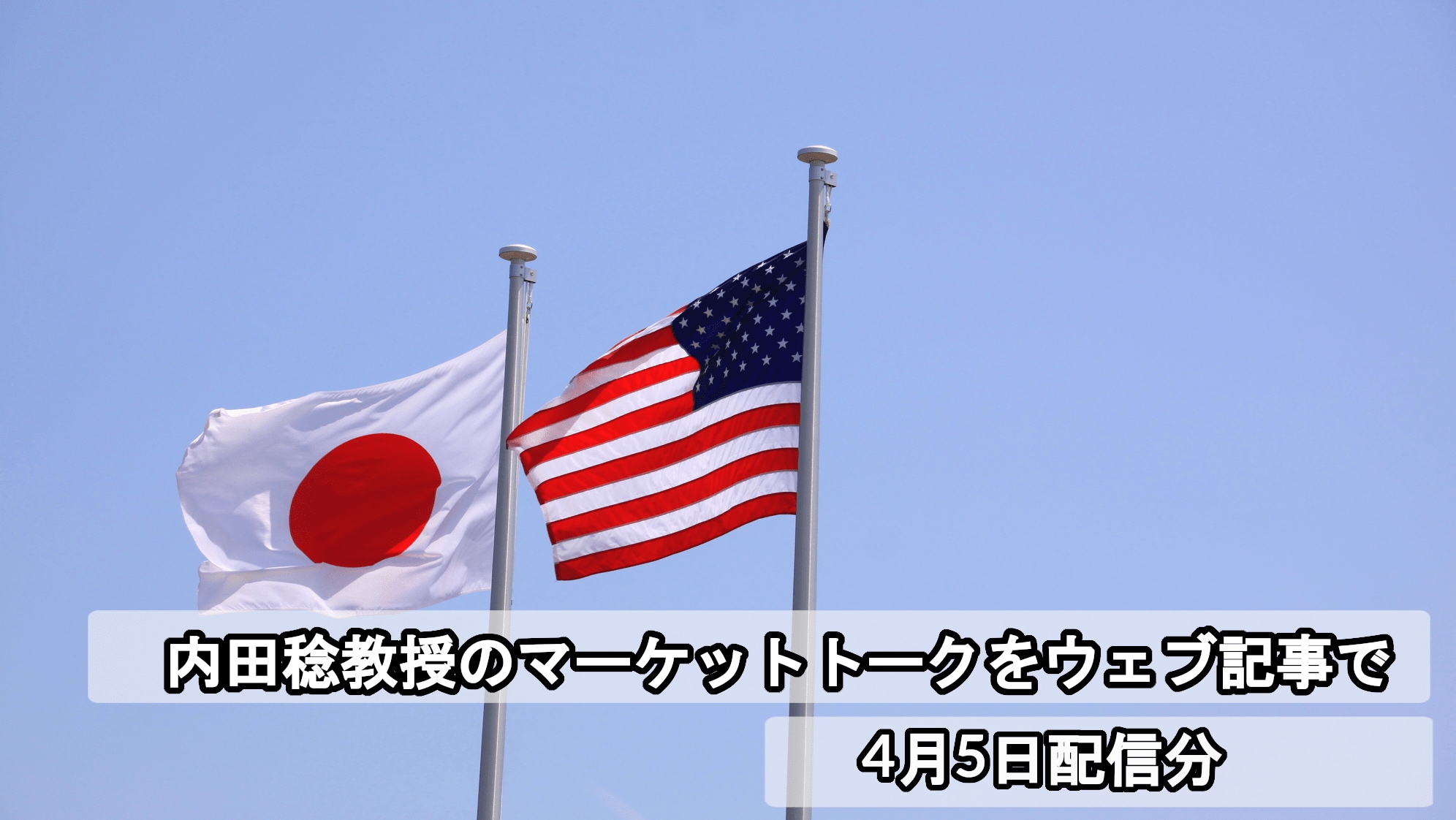現在の米・貿易赤字相手国は

では昨年の米国から見た貿易赤字相手国10カ国を見てみます。最大の貿易赤字相手国は中国でした。国別でみると2番目はメキシコ、ベトナムが3番目です。また、アイルランド、ドイツといったユーロ圏の国々の貿易赤字を足し合わせると2番目になります。また、メキシコとカナダを足し合わせたUSMCAは3番目になります。つまり米国から見ると中国、ユーロ圏、USMCA、そして国別では3番手のベトナムが重要な交渉相手と言えそうです。
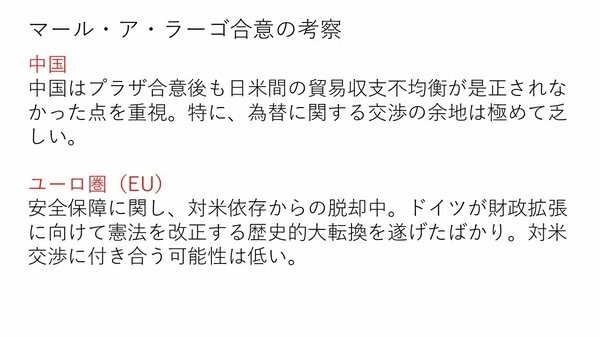
まず、中国の状況をみてみましょう。そもそもプラザ合意後の円高にもかかわらず、日米間の貿易収支の不均衡は是正されませんでした。さまざまな視点から日本を研究している中国は通貨に関しても特にこの点を重視しているようです。したがって、こと為替に関して米国と中国が何らかの合意に至る可能性はゼロに近いと考えられます。
次に、ウクライナをめぐる米国とのやりとりを見るにユーロ圏を含む欧州連合と米国の間にもかなりの溝ができています。そのため安全保障に関して対米依存から脱却を図る動きが見られており、ドイツの財政拡張に向けた憲法改正の歴史的大転換もこの動きの一つです。特に、ドイツ経済にとって通貨高は避けたいものです。ユーロ圏に関してもユーロ高ドル安方向の合意形成を得ることは困難でしょう。
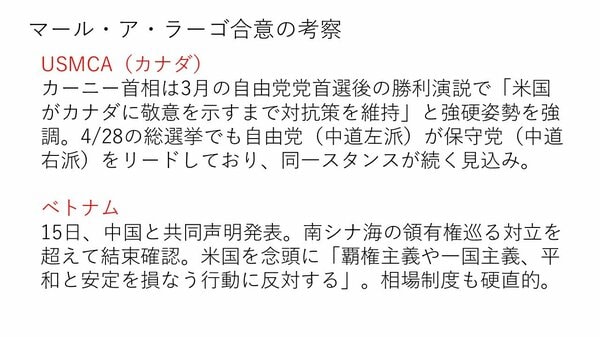
カナダでは3月14日に経済学者でもあったマーク・カーニー氏が党首選で勝利し、新首相に就任しました。カーニー氏は党首選後の勝利演説で米国に対する強硬姿勢を取ると、かなり強調しました。その点、4月28日に控えた総選挙ではカーニー氏率いる自由党が保守党をリードしている状況ですから、選挙後も対米強硬姿勢が続くでしょう。カナダも米国からの要求に対して是々非々の姿勢で臨んでいくと思われます。
ベトナムは4月15日に米国を念頭に覇権主義や一国主義といった平和と安定を損なう行動に反対するという趣旨の中国との共同声明を発表しました。そもそも中国とベトナムは南シナ海をめぐる領有権争いを繰り広げていますが、それを棚上げしてまで共闘路線を歩むスタンスを示しました。加えて、ベトナム・ドンは、変動相場制ではなく、為替が大きく動かないような中央銀行が深く管理している相場制度を採用しています。つまり、米国の要求をなかなか受け入れにくい状況と言え、ベトナムも米国にとっては手強い交渉相手になるでしょう。
―――――――――――――――――――――――――
後編:【マールアラーゴ合意が話題も、政治的な取り決めによる円高が定着するとは言い難い理由】では、依然続く円安傾向が変わりにくい要因を深掘りするとともに4月21日週の注目ポイントをお届けする。
「内田稔教授のマーケットトーク」はYouTubeからもご覧いただけます。