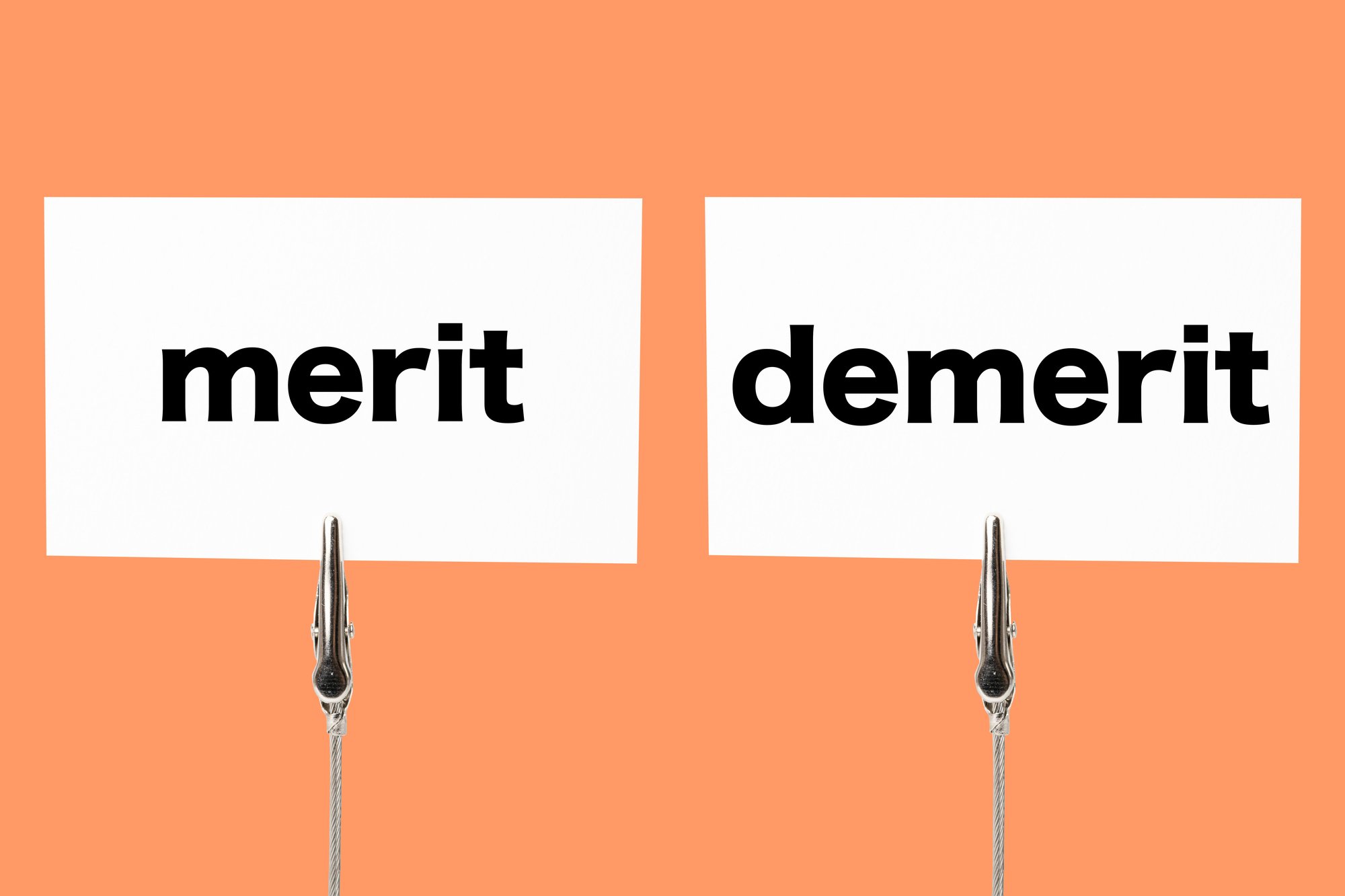iDeCoの若年層はパッシブ型比率が高い
アクティブ・パッシブ比率をみると、国内株式型についてはアクティブ比率が企業型DC、iDeCoともに4割程度と高い傾向があります。それ以外のカテゴリーではアクティブ比率は2割程度(iDeCoのバランス型のみアクティブ型が32.7%)で、とくにiDeCoの20代~40代では10%にも満たない状況となっています。
おそらく、各種SNS等で外国株式型パッシブへの言及が多いことなどが影響していると思われます。以前は、わからないから「なんとなく定期預金」だったのが、最近では「なんとなく外国株式型」になっているといえます。
外国株式型パッシブファンドの特徴
「S&P500を利用したいです」「外国株式型パッシブはないんですか」といった声を聞く機会が増えました。ある運用会社のS&P500指数に連動をめざす投資信託の残高は6兆円を超え、同じく全世界株価指数に連動をめざす投資信託の残高も5兆円を超えています。双方とも2018年の設定ですが、新NISAで大きく残高が増えました。
S&P500は米国の代表的な株価指数の1つで、米国株式市場全体の約8割の時価総額比率を占めています。NISAやiDeCoで「S&P500」という場合、指数に連動する投資成果をめざすパッシブファンドを指しています。全世界株価指数は「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」で、投資対象国は新興国24カ国を含む47カ国、投資銘柄数は2,687です(2024年10月)。
外国株式型パッシブという同じカテゴリーであっても、S&P500が米国の503銘柄に限定されるのに対し、全世界株価指数連動はより広く分散投資ができるものといえるでしょう(ただし、組み入れ比率でみた場合の上位5位は双方同様です)。
(逆説的ですが)定期預金の活用も必要
DC制度で「なんとなく外国株式型」から脱するためには、定期預金を上手に活用する必要があります。
DCは原則60歳までは引き出せない資産となるため、運用成果が出たから引き出して使う、ということができません。それもあって、いったん運用商品を選択すると、変更しないまま放置する人が多いのが現状です。
DCで積立投資を実践して、資産残高が増えたら、増えた部分はスイッチングして元本確保型に移す、という方法を実践しましょう。
最近の顕著な例では、昨年8月2日から5日にかけて大きく株式市場が調整した際、7月中にスイッチングしておけばよかった、と思った人もいるかと思います。この時の下落はすぐに持ち直しましたが、景気は循環します。ずっと上がり続けることも、下がり続けることもない、という前提からすると、増えた分を利益確定することも考慮しましょう。
利益確定の見極めには、ご自身のリスク許容度が重要となる点を再認識しましょう。リスク許容度には年齢や保有資産額等も影響するため、個々に異なります。ただ、どんなリスク許容度の方にもいえることは、「増えれば増えるほどいい」というスタンスではなく、いつか株式市場が低迷した時に、困らないのかどうか、ということです。
資産残高が増えている時にこそ、そうした視点を持つことも必要といえるでしょう。
※特にことわりのないデータについては運営管理機関連絡協議会の「確定拠出年金統計資料(2024年3月末)」の数値を使用