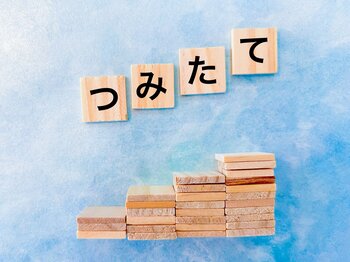確定拠出年金(DC)制度の「無関心層」は一定程度存在すると考えられます。ただ無関心層とひとくちにいっても、加入した時期や年齢等で課題は異なります。今回は、無関心層のなかでも50代に焦点を当てて考えてみます。
現役時代の事業主掛金額が同じでも、結果に大きな差
50代の無関心層の問題点は、気づいたときには時間が巻き戻せず、「知らなかった!」と思わざるを得ない状況に追い込まれることにあります。特にDC加入時、運用商品選択に向き合わず、よくわからないまま放置した人は要注意です。
一足先に60代に突入した世代をみると、現役時代の事業主掛金額が同じであっても、給付時にはDC資産残高が大きく異なるということが発生しています。運用商品の選択の違いやマッチング拠出の有無などで、金額的に2倍、3倍の差が開いていることもあるのです。
つい先日も、ある企業の担当者が体験談を話してくれました。年に2回発行される「お取引状況のお知らせ」(DC残高通知)を手にした50代の数人が会話をしていて、Aさんに対して「なんでそんなに増えているんだ?」という流れになったというのです。BさんとCさんは、その場で運用の基本的な考え方のレクチャーを受け、商品変更方法も確認したとのことです。
このようなケースで気づけたBさんやCさんはラッキーだったといえます。50代とはいえDC加入者期間が10年弱あり、運用の基本的な考え方を説明できる人が輪の中にいたのですから。
多くの50代無関心層は、こうした機会に巡り合わないままに老後を迎えることになるかもしれません。
時代背景や環境の影響も
年代を50代に区切った理由には、残りのDC加入者期間が短いことのほかにも時代背景の影響などもあります。
【時代背景】
DC制度がスタートした2002年以降しばらくの間はデフレ経済下にあったため、元本確保型(預貯金や保険商品)への資産配分であっても実質的な資産価値が下がることはありませんでした。さらに2008年のリーマンショック後には、投資信託保有者のほとんどが元本割れとなり、2012年ごろまでは元本確保型のほうが結果的によかったという考え方もありました。
【制度的要因①】
以前は、企業型DC加入者が運用商品を選択しない場合、「元本確保型」になる設定の規約がほとんどでした。それが「指定運用方法」が設定可能になった2018年5月以降は、投資信託を「指定運用方法」に選定する規約が増えています。
なお、「指定運用方法」は労使合意により設定するもので、運用商品を選択していない加入者について、一定期間経過後に指定運用方法での運用を指図したとみなされるものとなっています。
【制度的要因②】
DC制度スタート時には、企業型DC規約で「リスクリターンの異なる3本以上の運用商品」とともに「1本以上の元本確保型商品の提示」が法定されていました。その結果、2018年くらいまでに施行された規約では、複数の元本確保型がラインアップされています。