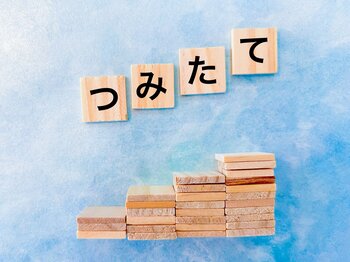元本確保型から資産を移動させることは難しい
筆者は継続教育を事業主に提案し、研修の場に臨む立場から強く感じることがあります。
いったん元本確保型に資産が入ると、そこから資産を移動させることはとても難しいということです。
元本確保型のみで運用していると、元本割れすることがないかわりに大きく増えることもありません。そのためDC制度や資産運用への関心が持ちづらく、継続教育自体に出席する人が少ないのです。
プログレスレポートでは継続教育について次のような取り組みが紹介されています。
「元本確保型商品の選択率が高い企業や想定利回りに達していない加入者が多い企業の従業員を対象にセミナーを開催。企業と協力し、原則全員出席とした上で、各加入者の資産残高と運用利回りを個別に資料配布し、その場で加入者が自身の運用状況を把握できるようにした。併せて、運用方法の変更に必要な個人の加入者専用サイトへのログインパスワード等も個別に配布し、その場で運用方法の変更を行うための手続きを解説した」
この例でポイントになるのは「強制力」です。「原則全員出席」であり「その場で運用方法の変更を行う」ことまで行って初めて、無関心層の行動変容に結びつきました。こうした設定ができる企業は限られています。そこで「強制力」に着目すると、次のような方法も考えられます。
・退職金制度を見直す
・運用商品の除外を行う
・運営管理機関を変更する
いずれも加入者個人で実施できるものではありませんが、退職金制度を見直すことでライフプランの気づきにもつながり、運用見直しに結びつくことも多いようです。
運用商品の除外は、否応なく運用商品の見直しにつながります。ただ、この場合も「指定運用方法」が定期預金に設定されていると、加入者は「何もしなければ定期預金になるから(考えなくてもいいや)」という発想になりがちです。そのため、指定運用方法の設定を投資信託にすることから始めた方が実効性を伴うといえるでしょう。
運営管理機関の変更は、いったん旧プランの資格を喪失して、新プランで新規加入者資格を取得するケースが多いようです。結果として、新たにDC制度を考えるきっかけになるようです。
さらに、年金制度改正法の成立も強制力を持たせた継続教育のきっかけになるかもしれません。
従来、加入者掛金(マッチング)拠出は、事業主掛金以下と定められていましたが、この規制が外れます。また企業型DCのマッチング拠出と個人型DC(iDeCo)本人掛金は同額まで拠出できるようになります。さらに拠出限度額も6万2000円まで増えることも決まっています。
上の施策の施行時期は公布の日から3年以内となっています。
企業型DCの事業主は、年金制度改正法案の活用のために今から企業型DCの制度設計や継続教育を長期で展開していくことをイメージすることが大切です。より魅力のある制度にしていくことが無関心層を減らしていくことにつながるといえます。