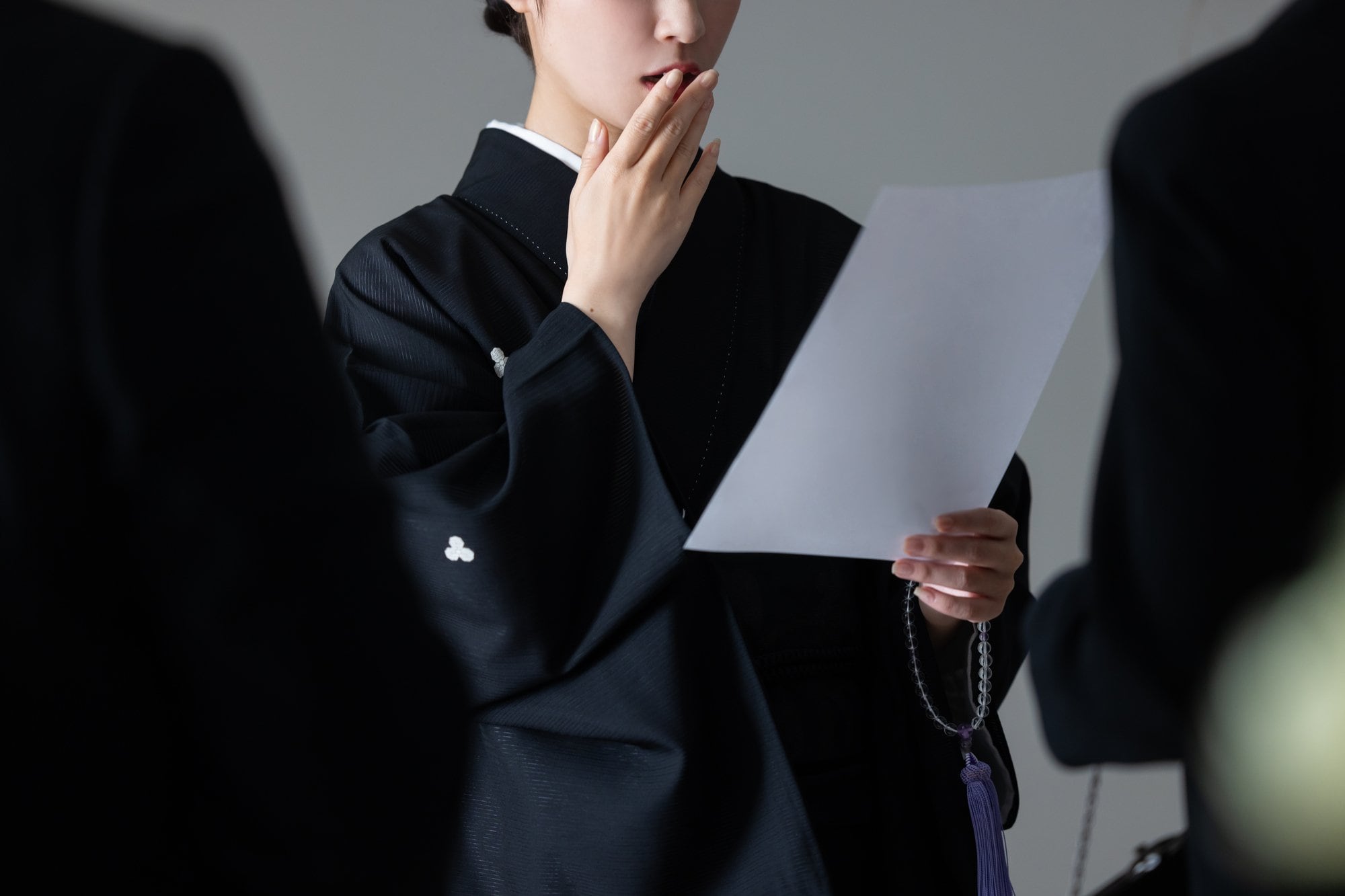気ままな生活が始まった
春めく柔らかな風に乗って、扉のベルの音が軽やかに鳴る。
「お母さん、遅いよ!」
駅前のカフェに着くと、美菜が手を振って佳菜子を出迎えた。まだ卒業してから1か月程度しか経っていないのに、社会人になった娘はどこか大人びた気がする。
「ごめんごめん。バスが遅れてね」
佳菜子が席に着くと、テーブルにはすでに水が2つ並んでいた。
「はい、注文どうぞ。お腹空いてるでしょ?」
「仕事はどう? 少しは慣れた?」
佳菜子は渡されたメニューを眺めながら尋ねた。
「うーん……どうなんだろう。先輩も同期もいい人たちばっかだけど、上司がいちいち細かくてちょっと苦手なんだよね。てかお母さんこそどうなの? 独り暮らしは」
「まあぼちぼち。でも気楽でいいもんよ。家事も1人分で済むしね」
佳菜子はあっけらかんと言って、少し大げさに肩をすくめる。
美菜が卒業し、独り暮らしを始めるタイミングで佳菜子は勇司に離婚届を突きつけた。佳菜子の見立てでは勇司が駄々をこねるだろうと思っていたが、貯金の使い込みから数か月のあいだの冷え切った視線が余程こたえたのか、勇司はすんなりとハンコを押した。佳菜子は今、1人用のマンションを借りて、気ままな生活を始めている。
とはいえ、これまでそれなりに賑やかな家で過ごしていたから、急に1人になったことは寂しくもある。ふと、美菜や勇司に話しかけてしまい、誰もいない部屋を振り返っては自嘲的に笑うのだ。
「あ、そうだ。お母さんに聞きたいことあったの。この前、同期が家に遊びにきたとき、ジュースこぼされちゃってさ。カーテンってどうやって洗うの? てか洗えるの?」
「なに、そんなこと? 洗濯表示見たらいいじゃない」
「見てもよく分かんないだってば」
大人びて見えたと言っても、こうして話していればいつまでも子どもなんだと改めて思う。もう少し、あるいはずっと自分は母親で、美菜は娘なのだろう。それはきっとこの先何があっても、どこにいても、変わることはない。
ふと視線を投げた窓の外で、雀が1羽、青い空に飛んでいく。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。