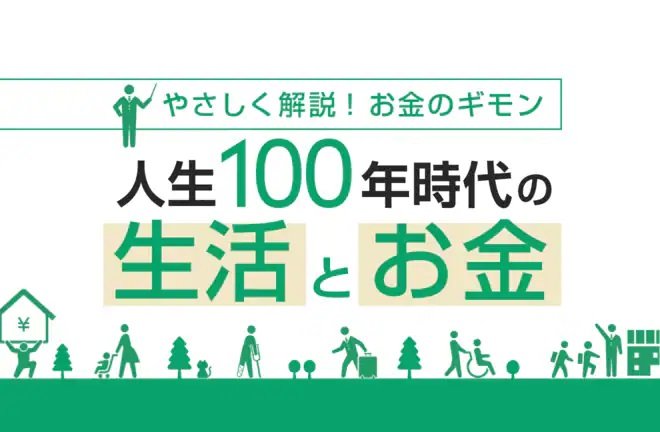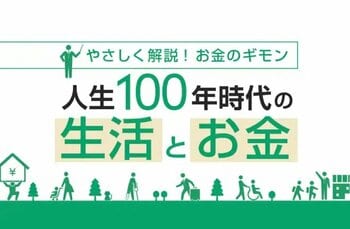物価上昇が止まりません。4月以降では、加工食品やサービスの値上げが目立つようです。値上げが当たり前になりすぎて、企業の事前アナウンスが報道されないこともあるようです。では、物価上昇は消費者にとってどのような影響があるのか、考えてみましょう。
企業経営にとって、値上げは創意工夫が活かせるチャンス 消費者満足度向上に期待
4月に入って値上げが顕著です。3月までは生鮮食料品が中心でした。4月以降は加工食品やサービス価格の上昇が目立ちます。原因は人件費、エネルギー代、原材料など多くのコストが上がったことです。もう毎年のように上がるため、企業が値上げを発表しても、必ずしもメディアで報道されないケースも増えています。
一方、春闘の結果を踏まえ、4月以降はやや大きな賃上げが期待できそうです。賃金で大事なのは実質賃金です。これは、賃金の伸び率から物価の伸び率を差し引いて計算します。昨年は、賃上げ率は高かったものの物価はそれ以上に上がったため、実質賃金はマイナスでした。多くの人があまり賃上げの実感がなかったのは、統計的にも正しかったのです。しかし、2025年度以降は実質賃金がプラス転換すると期待されています。言い換えると、やっと賃上げが実感できるようになりそうなのです。
近年、賃金と物価が上がり始めたことから、日銀は企業にアンケート調査を実施しました。企業サイドは、賃金と物価がともに上がる状態について、約7割もが好ましいと答えています。それは企業経営としては、値上げは創意工夫が活かせるチャンスでもあると答えていることを意味します。
この傾向は特にサービス業や飲食業で顕著です。値上げしても逆に顧客の満足度は高まる場合があるのです。こうなると、賃上げも可能になるので従業員満足度も上がり、利益も出やすくなるため株主や取引先など周辺の企業でも満足度も上がります。これがいわゆる生産性の向上です。さらに、そういう生産性の高い企業が創意工夫をしないために経営が苦しくなる企業を買収して、好循環が広がる例も増えています。言い方を変えると、10年ほど前から言われてきた賃金と物価の好循環がやっと実現しつつあるのです。
値上がりはしたけれども消費者として満足度が上がる、こういう消費行動をするのが得策な時代なのかもしれません。日本のサービス業や飲食業がインバウンドの外国人に大人気な秘密もここにあると思います。
■関連リンク:
https://www.resona-am.co.jp/labo/amdays/20250414.html