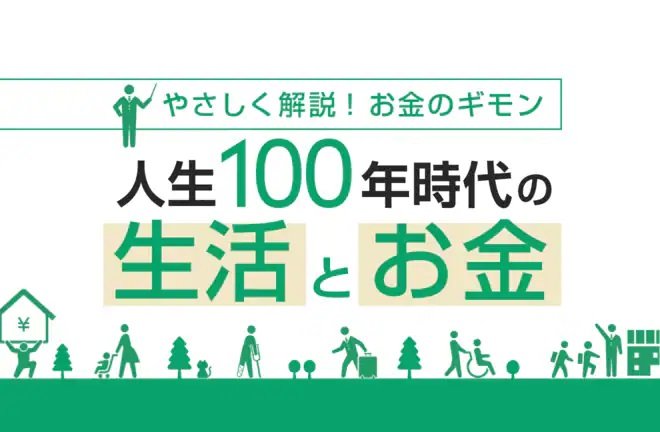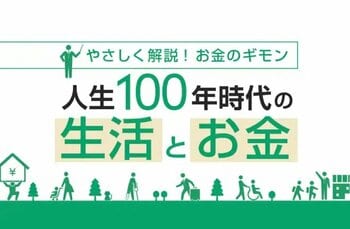昨今、世界中で金融市場が不安定化しています。かつては株価も金利も総じてどこの国も同じ方向性でしたが、国や地域でバラバラなのが新しい時代の特徴と言えるでしょう。例を挙げると、日本は「円高、金利高、株安」ですが、「通貨安、金利安、株高」と真逆の状況の国もあります。今回は、その原因について説明します。
金融市場が同方向だったグローバル化の終焉、各国がバラバラに動く今後は、世界への投資に細心の注意を
最近は金融市場が不安定化しています。ことの発端は米国トランプ政権の政策です。関税を上げる、上げないで二転三転しています。ウクライナ支援では人道支援よりビジネス上の利益の観点で進めようとしました。これが原因で二人の国家元首が公の場で口論しました。そして、実際に支援を一旦は一方的に停止しました。もはや米国を経済と安全保障の最重要パートナーとして信頼できないという空気感が世界を覆っています。
これに対応して欧州は独自の核を含む防衛戦略の方針を打ち出しました。その結果、ウクライナの復興需要に加え、防衛関連で武器弾薬だけでなくシェルター建設やインフラ強靭(きょうじん)化など幅広く恩恵が及びそうなことから、株式相場が盛り上がりました。財源として財政政策を引き締めから緩和へと転換することから金利は大幅に上昇しました。
米国では関税により経営の不透明感と景気の停滞感が強まっています。これが原因で株価も金利も大幅に低下しました。日本は、日銀が利上げを継続する意向を示しており、長期金利は上昇基調が続いています。これにより米国との金利差が縮小して150円前後の円高になっています。株価は米国と同様に下落しています。新興国では、中国や香港は景気回復と政策期待から株価が上昇、インドは景気悪化の懸念から株価は下落傾向です。
グローバル化の時代には、米国が先頭を走り、ほかの国が追随する形で、株価も金利もほぼ同じ方向に動きました。最近の国地域でバラバラな動きは、グローバル化が終わったことを象徴すると言えます。根本的な原因は、米国による国際ルールを軽視して関税など個別の交渉を進める姿勢にあります。例えばインドです。米国からの関税引き下げ要求で景気悪化の懸念が高まっています。関税の引き下げで海外から輸入品が流入すれば、国内産業が打撃を受ける可能性が高いからです。
反グローバル化の時代には世界情勢を見極めるのが難しくなります。世界に投資するにはアンテナをより高く張る必要があります。
■関連リンク:
https://www.resona-am.co.jp/labo/amdays/20250331.html