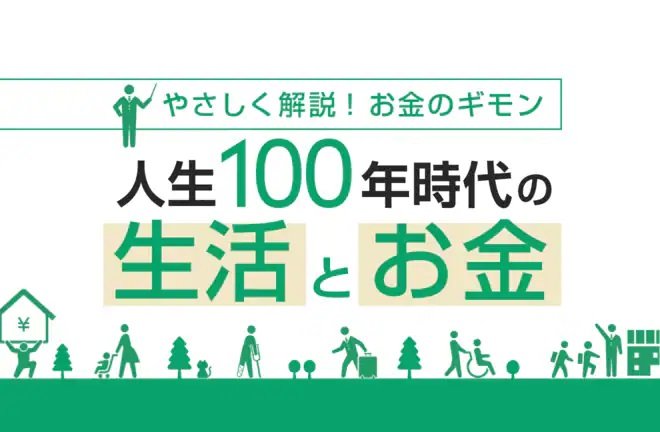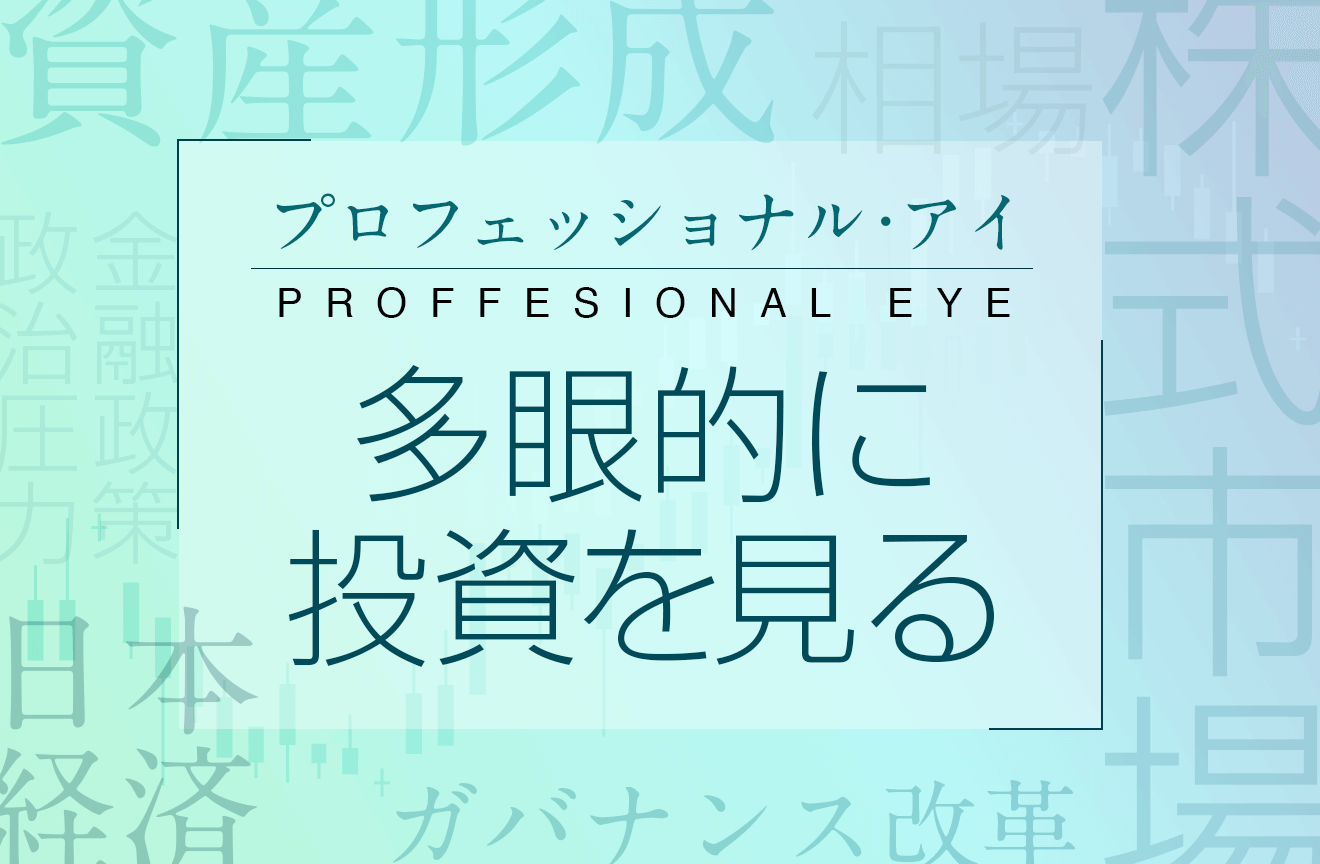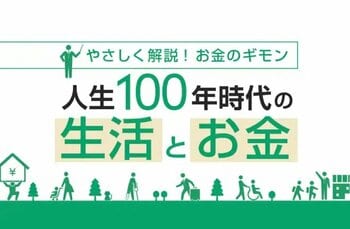毎年のように取り沙汰される「〇〇年問題」。2024年は、運送業や建設業で残業時間に上限が導入され、現場の混乱で配送や工期の遅れなどの問題が発生しました。2025年に問題と言われているのが、団塊世代が75歳以上になることです。長生きは喜ばしいことですが、半面、介護の人手不足や財政の予算制約などの問題が指摘されています。今回は、「2025年問題」の具体的な問題点と対応策について解説していきます。
2025年問題で深刻化する認知症患者の増加、「全世代型社会保障」の実現が日本の重要課題
団塊の世代は終戦後の1947年~49年の間に生まれた世代です。戦後のベビーブームで生まれた世代であり、非常に人口が多いのが特徴です。この世代が2025年には全員75歳以上になります。そして日本の総人口の約5分の1が75歳以上となります。統計的に75歳以上の約3分の1は介護が必要になります。認知症も増加する見込みです。厚生労働省の試算では、30年の認知症患者の数は22年より80万人増えて523万人になる見込みです。こうなると、介護や認知症の親のために仕事を続けられなくなる人、さらには学業を続けられなくなる学生が出る可能性があります。
しかし、暗い話ばかりではありません。認知症患者の推計は14年の推計と比較すると約3割も減少しました。予防や健康寿命への意識が高まったことの成果が出たのです。具体的には、高血圧や高コレステロールなど生活習慣病の改善です。そのためには栄養管理などの食事制限や早めのウォーキングなどの運動が良いとされています。さらに、感情や意欲や創造性などの面で脳の前頭葉を刺激することも効果的とされています。
25年はこれまで以上に対応策を強化する必要があると見られています。政府や財界は既にその方向性を示しています。内閣府は昨年7月に「経済財政運営と改革の基本方針2024」で人口減少や高齢化で起こる社会課題の解決を経済成長率の向上に結びつける方向性を示しました。最も重要なのは人工知能(AI)やロボットなど革新技術の社会実装です。経団連は昨年12月に「FUTURE DESIGN 2040」を公表しました。少子高齢化と人口減少が進む今の状況を克服すべき課題と捉え、現役世代の社会保険料の負担を抑制し、公正・公平で持続可能な「全世代型社会保障」の実現が必要だと提言しました。
2025年問題は将来的な日本社会の持続可能性を方向付ける重要な克服すべき課題なのです。
■関連リンク:
https://www.resona-am.co.jp/labo/amdays/20250113.html