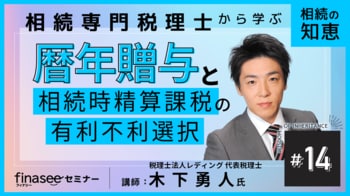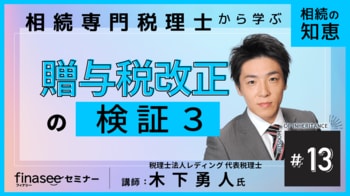最も責め立てたい相手は学校ではない
学校には謝罪させ、今後は今回のようなことが起きないよう、学校側も最大限の注意を払うと言ってくれた。だが、麻央の気持ちは釈然としない。
学校側の対応に不満があるわけではなかった。起きてしまったことはどうにもならないし、誠意が感じられる謝罪でもあった。それなのに、胸のおくにはずっともやがかかっているような気分だった。
夜勤を終えた麻央は寝ている悠里を起こしてしまわないよう、アパートの古い玄関扉のカギを慎重に開けた。
リビングの机に荷物を下ろし、半開きのふすまから和室をのぞき込む。悠里はブランケットをかけたまま幸せそうに眠っている。麻央はあくびを1つかみ殺し、悠里の隣りに横になる。この笑顔こそ、何としても守り抜くと決めたものだ。
「お母さん……?」
「あら、起こしちゃった。ごめん」
「……おはよう、おかえり」
「ただいま」
いつもは寝ざめが悪く、朝ごはんを食べていてもぼーっとしている悠里だが、すっと布団から起き上がり、勉強机にしている小さなちゃぶ台の横にあるランドセルの元へと向かった。麻央はびっくりしながら娘の様子を見ていたが、悠里はすぐに布団のところへ戻ってくる。
「ママ、ハッピーハロウィーン」
差し出された小さな手には、個包装のクッキーが1枚、握られていた。
「どうしたの?」
「ハロウィーンパーティーで、みんなと交換したの。ママもクッキー好きだから」
麻央は思わず涙を流しそうになってしまい、反射的に悠里を抱きしめていた。悠里は驚いたようでそのまましばらく固まっていたが、やがて麻央の背中に小さな手を添えた。
責めるべきは配慮の足りていなかった担任でも、学校でもなかった。娘に優しくも悲しい気づかいをさせてしまった自分自身こそ、麻央が最も責め立てたい相手だった。
「ごめんね。悠里につらい思いさせて、ごめんね」
麻央は1枚のクッキーを半分に折って、悠里と一緒に食べた。まだ涙が乾ききる前に食べたクッキーは甘くて、少ししょっぱかった。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。