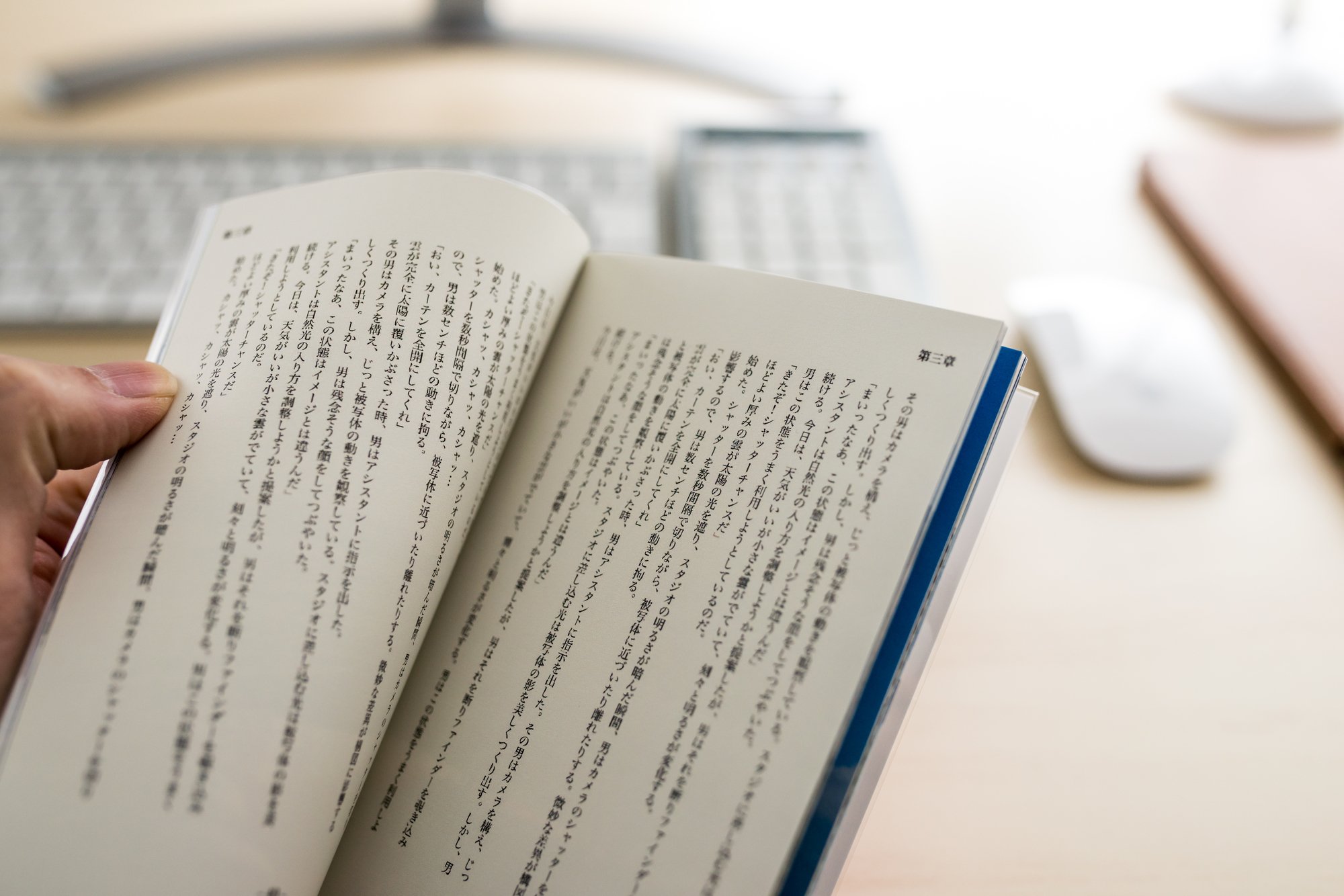小説家としての生き方
「へえ、そんな体験をされたんですね」
想伝出版の小さな会議室で執筆中の3作目について編集者の峰と打ち合わせをしている時、話の流れで先日の話をすることになった。恥ずかしさもあったが、誰かに聞いてほしい気持ちが勝った。
「はい。なんというか、人間の持つ多面性というか、そんなものを垣間見てしまったような気がしてゾッとしましたよ。でも、考え方を変えれば面白い体験ができたと思います。腹は立ちましたけど、いつか小説のネタにしてやりますよ」
間宮がそう言うと、峰はちょっと驚いたような顔をした。そして、じっと間宮の顔を見つめた。もしかして、なにか変なことを言ってしまったか?
「峰さん、どうしました?」
峰は間宮の質問には答えず、じっと顔を見つめ続けている。そして、テーブルの上に置いてあるコップの水をぐいっと飲み干すと、間宮にこう言った。
「間宮さん、考え方が小説家らしくなってきましたね!」
峰によると、嫌な思いをしても「これはネタになる」と考えるタイプの人が小説家には多いらしい。間宮はこれまでそんなことを考えたことがなかった。創作の邪魔にならないように、嫌なことはすぐに忘れようとしてきた。
「間宮さんが仕事を辞めたと聞いたときは『やっちゃったな』と頭を抱えましたけど、もしかしたら良かったのかも知れませんね」
峰は楽しそうに笑っている。間宮もつられて笑ってしまった。そうだ、自分はもう小説家なのだ。どんな思いをしても、それを小説の肥やしにしてしまおう。そうすれば、嫌な記憶も貴重な財産になる。これからも嫌なことはあるだろうが、全て小説に放り込んでしまえばいいんだ。執筆を進めている3作目に「小説が売れなくてバイトをする中年男」でも登場させようかな。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。