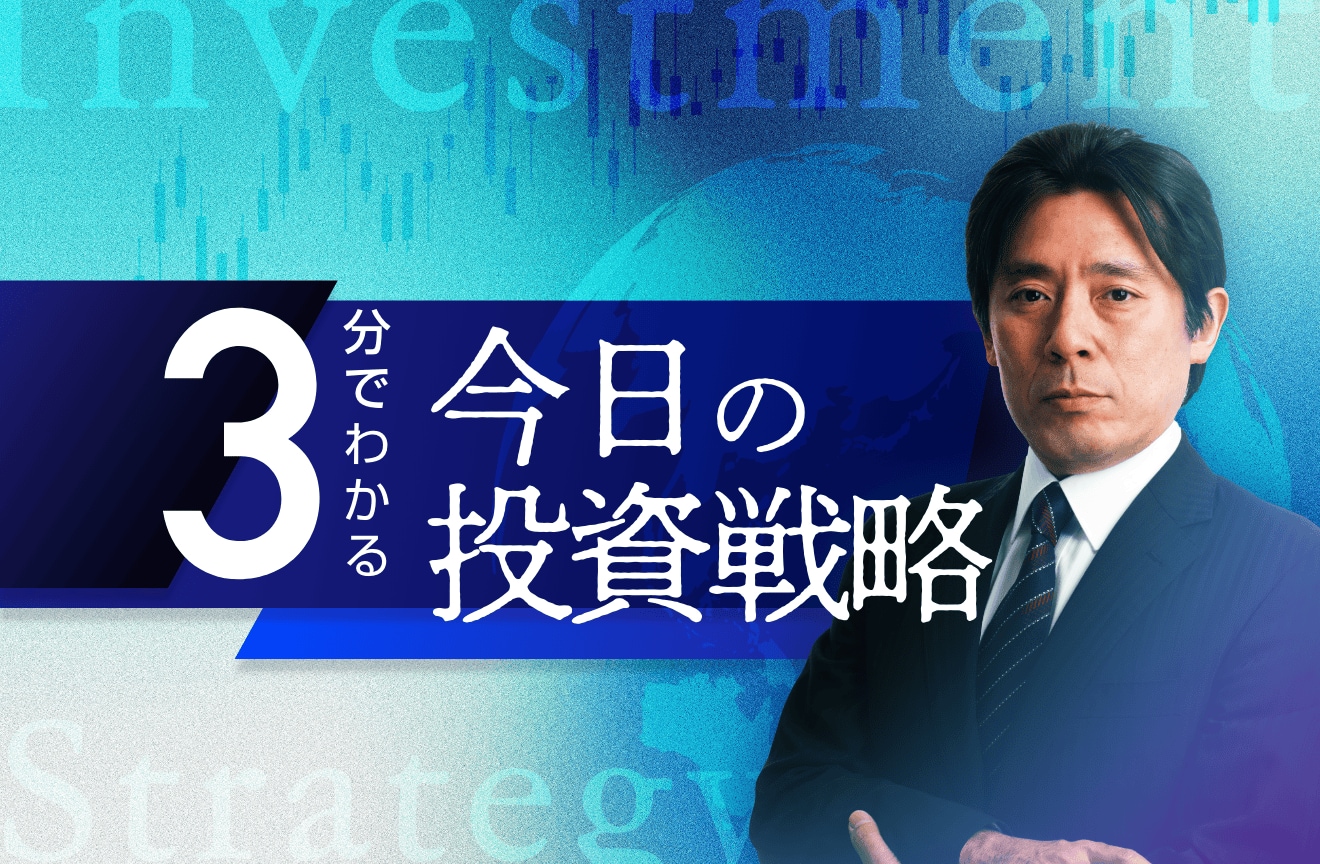政府・日銀はMMT(現代貨幣理論)を実践している?~その理論と問題点~
いずれにせよ、20日以降に召集される臨時国会で首相指名選挙が実施され、新しい首相が決まります。市場では、どちらかというと結局は自民党の高市総裁が指名されるとの見方が多いようですが、そうなったとしても、あるいは野党の統一候補が指名されたとしても、財政拡張路線が強まることは避けられない情勢です。
少し話は飛躍しますが、日本銀行が実質金利の大幅マイナスという緩和的な環境を維持する下で、巨額の政府債務を抱えながらさらに財政を吹かすというわが国の姿は、以前よく耳にした現代貨幣理論(MMT)を実践しているかのように筆者の目には映ります。
現在の長期金利の上昇とインフレの上振れリスクの高まりをMMTの結果と捉えるなら、それを推し進めればますます長期金利は上昇し、インフレは高まることになります。
MMTの論者からは、「自国通貨を発行する国では、どんなに財政赤字が膨らんでも破綻しない」、「財政支出はインフレが起きない限り問題ない」「インフレが起きれば増税すれば良い」といった主張が聞かれます。
著名なMMTの主唱者である米ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授に至っては、日銀がイールドカーブ・コントロール(YCC)を行っていたころの日本を、MMTの成功事例だと主張していました。
MMTは貨幣理論であると言われるとおり、貨幣から出発する理論です。具体的には、物々交換から派生して「交換」「価値尺度」「価値の保存」という機能を持つ貨幣が生まれたと考える「商品貨幣論」ではなく、負債が生じることによって貨幣が生まれると考える「信用貨幣論」の立場をとります。
分かりやすく言えば、銀行が貸出を実行するという行為は、借り手の口座に貸出額を記入することであり、そこに貨幣が生まれるという考え方です。
実は、この点に関していえば、筆者にとって全く違和感がありません。つまり、借り手がいなければ信用創造はできないわけで、もっと言うと、中央銀行がマネタリーベースを増やしたところで、資金需要がなければ貸出は増えず、従ってマネーストックも増えないということを意味します。
実際、2000年代前半の量的緩和も、2013年4月からの異次元緩和も、それによってマネーストックが大きく増えることはありませんでした。
では、MMTのどこに問題があるのでしょうか。端的に言えば、価格(金利)の形成理論がないことです。確かに、MMT論者が主張するとおり、政府が国債を発行すると、銀行がそれを購入するわけですが、政府は国債発行で得た資金を預金に付け替えることになるため、銀行システム内で資金がぐるぐる回るだけで、国債発行に制約はないということになります。
実際、日本はそうなっているように見えますから、ケルトン教授が成功事例と見るのも無理はありません。
しかし、資金が付け替わるだけだからといって長期金利が上昇しないかというと、そうではありません。
MMTの生みの親の一人として知られるウォーレン・モズラー氏は、「どの年限の国債にも限られた数の買い手しかいない」「誰かがそれを買いたいと思う水準まで金利は上昇する」と、金利が上昇することを認めています。投資家はもうかるかどうかやリスクなどを勘案して購入を決めるのであり、そこには価格(金利)決定メカニズムが存在します。
自国通貨建てで国債を発行する国では、自国通貨をいくらでも発行できるため、債務不履行(デフォルト)は起きません。これも理屈としては当然です。
ただし、価格決定メカニズムがない以上、「長期金利が上昇してクラウディング・アウトが発生」「長期金利の高騰や株価暴落が起きて金融危機に発展」「インフレが高騰し庶民の生活が脅かされる」といった可能性をMMTは否定することができません。ちなみに、現代では、金融危機やハイパーインフレはデフォルトと同一視されるのが普通です。
さらに、MMTは、通貨がなぜ通貨たり得ているかに関して、政府や中央銀行への信用ではなく、法定通貨として納税手段に使用できること、つまり国家権力が貨幣の価値を保証すると捉えています。
しかし、通貨が通貨たり得る最大の要因は、政府や中央銀行への信用ではないでしょうか。MMT論者が言うように、「インフレが起きれば増税すれば良い」と安易に考えるような政府であってほしくないですし、インフレが起きたからといって簡単に増税できるものでもありません。
このように、MMTは財政拡張に伴う長期金利の上昇やインフレの上振れを否定することができず、また、有効な処方箋を提供できるわけでもありません。長期金利の上昇やインフレの上振れが顕在化する前に、財政拡張ペースを抑制することが必要だという至極当然の結論から我々は逃れることはできないということを、改めて確認しておきたいと思います。