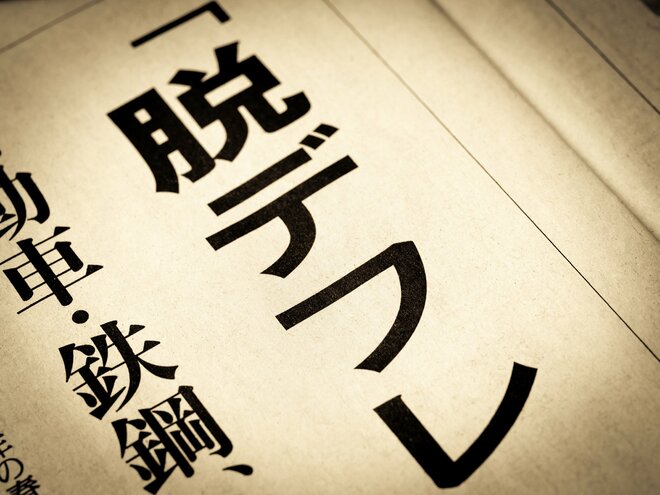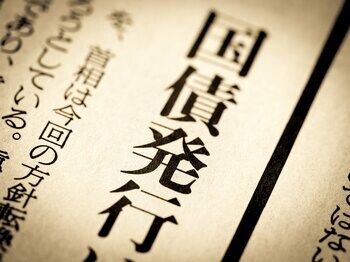ようやく始まった金利上昇の波。
長年、日本を悩ませてきた低成長・低賃金といった経済の“悪循環”を断ち切るチャンスかもしれません。金利が上昇する今こそ、日本経済が本来の強さを取り戻すヒントが見えてきます。
BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長の中空麻奈氏が、日本経済の現在地と成長の道筋を読み解きます。(全4回の2回目)
●第1回:いよいよ始まった日本の利上げ…植田日銀の“次の一手”は?
※本稿は、中空麻奈著『金利上昇は日本のチャンス』(ビジネス社)の一部を抜粋・再編集したものです。
インフレ・物価高への対応
政府・日本銀行は脱デフレを至上命題として、これまでさまざまな財政政策、金融政策を行ってきた。そして脱デフレを実現するためには、個人の消費意欲の回復こそが重要と考えられてきた。
しかし、日本の個人消費の弱さがコロナ禍でより露呈した格好だ。
コロナ禍の間、世界各国政府は、それぞれの国民を対象にして給付金等を配った。その結果、どの国でも国民の貯蓄が大きく増えたが、他の国に比べて真っ先に貯蓄を減らしたのが米国だった。ところが日本はどうかというと、消費性向や消費支出は徐々に改善へと向かっているものの、個人消費はコロナ前の水準の強さになっていない。
日本の個人消費を他国と比べて問題のない水準まで戻す状況を作り出す必要がある。個人消費を確実なものとし、デフレから脱却できるところまで回復させるためには、可処分所得を増やす必要がある。そのために用意されたのが2024年に実施された所得税・個人住民税の定額減税だった。たとえ企業の賃上げが続いたとしてもインフレ率が賃金の上昇率を上回る状況が続けば、いつまで経っても個人消費は回復しない。そこで出てきたのがインフレ対策、つまり物価を抑制する対策だ。
政策面の矛盾はここにある。
デフレ脱却を至上命題としながらインフレ対策を行った。これではアクセルとブレーキを両方同時に踏んでいるようなものだ。