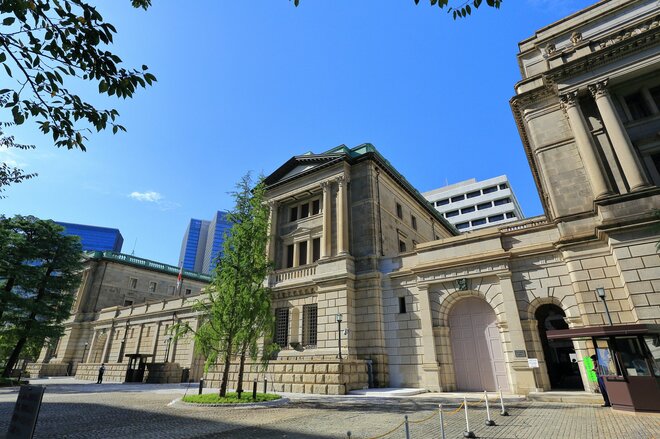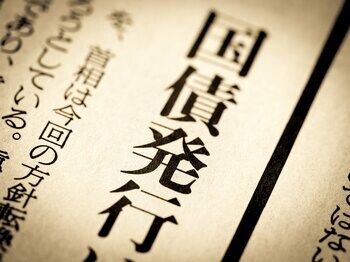ようやく始まった金利上昇の波。
長年、日本を悩ませてきた低成長・低賃金といった経済の“悪循環”を断ち切るチャンスかもしれません。金利が上昇する今こそ、日本経済が本来の強さを取り戻すヒントが見えてきます。
BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長の中空麻奈氏が、日本経済の現在地と成長の道筋を読み解きます。(全4回の1回目)
※本稿は、中空麻奈著『金利上昇は日本のチャンス』(ビジネス社)の一部を抜粋・再編集したものです。
ゼロ金利解除のソフトランディング
日本の政策金利は、2024年7月に0.25%、2025年1月に0.50%へと引き上げられてきた。2024年12月19日に行われた金融政策決定会合では、「もう1ノッチ(1段階)欲しいところ」と言って利上げに踏み切らなかったが、2025年1月23、24日に行われた同会合において政策金利は17年ぶりの水準とされる0.50%となった。
問題はここから先だ。
すでに金利は正常化に向けてのプロセスを踏んでいる段階にあった。さらに金利が上昇するために必要なのは、2%という物価目標の達成がこれから先も続くことに対する確信と、そのために必要不可欠な賃金の上昇が続くことである。これは黒田前日銀総裁の時代から、幾度となく繰り返し言われていることだ。
そして今。2%という物価目標と恒常的な賃金上昇が確からしさを強めている。
まだコストプッシュ型の物価上昇という状況を拭い去ることはできないが、生鮮食品およびエネルギーを除く消費者物価指数(コアコア)の前年同月比は、直近で言うと2023年5〜8月にかけての4.3%をピークに徐々に低下してはいるものの、2024年3月以降は2%超を維持して2025年1月時点で2.5%となっている。
賃上げの動きも続いている。2023年の春闘からベースアップも含めた定期昇給の要望に対して、企業は労働者側の要求に応えてきた。2025年の春闘においては第一回回答集計時点で平均賃上げ率は5.46%と前年を上回る。
これだけ材料が揃っているにもかかわらず、植田日銀総裁がこれ以上の金利上昇をしないとなれば、為替水準なのか政治状況なのか、どちらかが金利を上げられない理由になっているということだ。金利が上がらないほうがむしろマーケットは売られてもおかしくない。
日本国債が売られれば、市場で形成される長期金利は上昇する。また円が売られれば、海外からの輸入物価がさらに上昇してしまう。もちろん株価も急落する。国内景気にとって良いことは一つもなく、景気悪化と物価上昇によるスタグフレーションが深刻化するリスクも考えられる。
したがって日本銀行としては、物価と賃金の好循環が確たるものになるならば、定期的に金利は上げていくというメッセージを出し続けることが肝要となる。