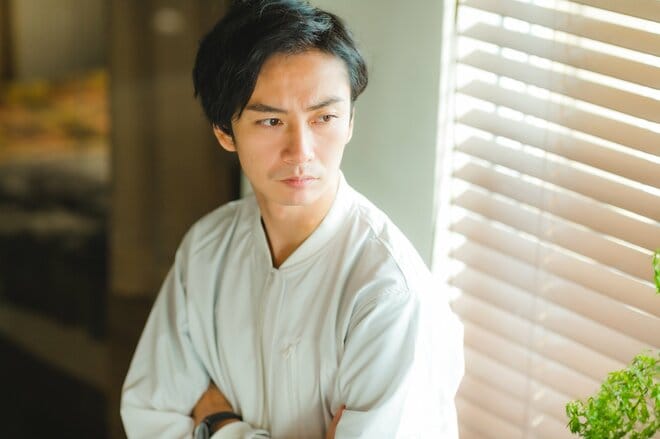遺言書に込めた“想い”が家族の絆を守る
「やっぱり……どこか不安だったんでしょうね。私は遺言書で、長女には不動産全部(全体の資産の7割)、次女には残りを現金で渡すようにしていたんです。現在の2人の経済格差を踏まえての内容だったのですが……いま思えばあの子たち、昔から“平等”に敏感でね」
高橋さんはそうため息混じりに語る。先日の記事を読んでから実に4日後のことのようで、彼の温度感の高さがひしひしと伝わってきた。
早速、彼の書いた遺言書を読んでみる。確かに法的な効力は一応満たしてはいる。だが問題点はいくつも浮き上がる。例えば、次女に渡す予定の現金は、相続発生時には目減りしている可能性がある。また長女に渡す不動産の方も名義変更や現金化に手間と費用がかかるという問題があり、彼の思い通りの結果とならない可能性が高い。
話を詳しく聞いてみると「大卒の次女に比べて、私に気を使って早くに働き始めた長女の方が経済的には少し苦労していてね」と高橋さんが相続分を決めた理由を語り始める。
そこで、私は、遺言書に“想い”を添えることを勧めた。財産の分け方だけでなく、なぜそのように分けたのかの背景や気持ちを丁寧に言葉にした、いわゆる付言事項を加えることを提案した。加えて、相続分も法定相続分(法律で定められた取り分で本来姉妹は同じ相続分となる)を意識して、不動産をすべて売却したうえで長女55%、次女45%という相続割合とすることも提案。
高橋さんは提案を受け入れてくれたものの、最初は遺言書の内容を変えていくことについて煮え切らない表情だった。
だが、遺言書を書いているうちに気持ちが変わっていったようで「こうして書いてみると、意外と気持ちが整理されるもんですね。あの子たち、これなら分かってくれると思いますよ」と、晴れやかな表情で語った。彼にとってこの時間はまさに第二の人生の集大成とも言える時間だったのだろう。
高橋さんは帰り際、私にお礼を述べる。
「確かに自分一人でも遺言書は作れました。ですが、それが自分にとってはもちろん、娘たちにとって本当にいいものではなかった。専門家である柘植さんに相談して本当に良かったです」
●数年後、高橋さんが亡くなり遺言書が発見されますが、想定通りの相続とはいきません。姉妹の間で起こってしまった“想定外の波乱”の詳細は、後編【「娘たちは争わずに済む」70代実業家が残した新旧2通の遺言書…姉妹の絆を救った父親の「最期のメッセージ」】でお届けします。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。