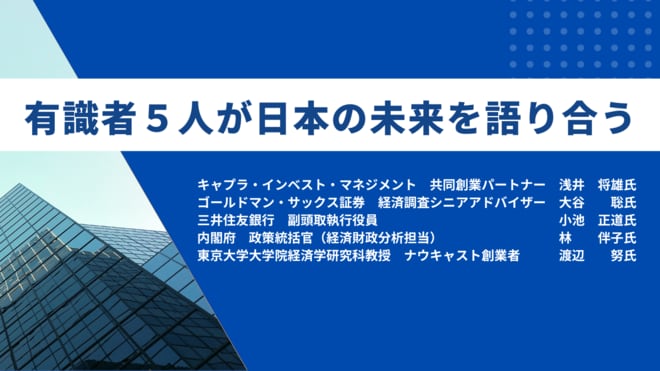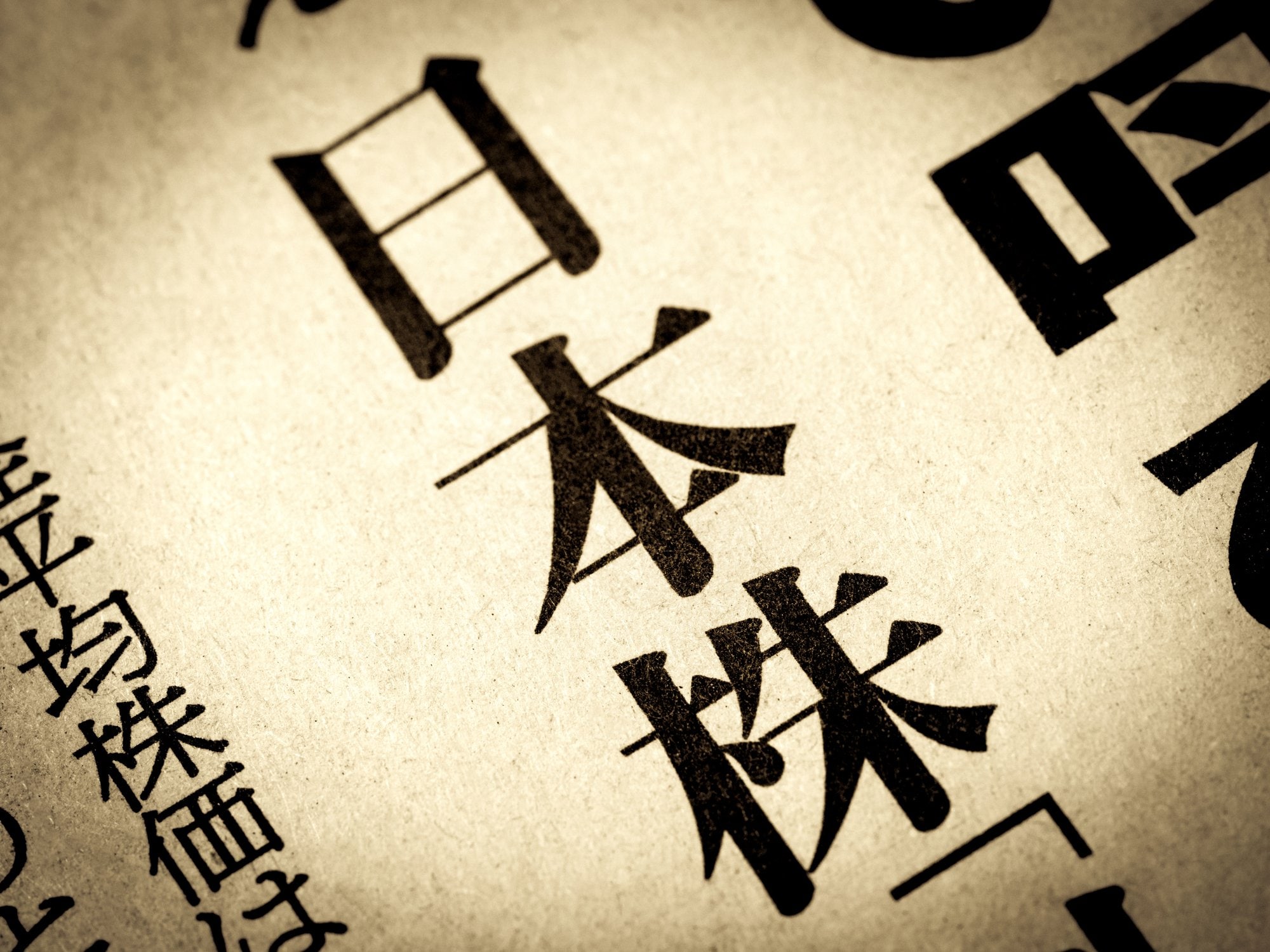パネリスト
キャプラ・インベスト・マネジメント 共同創業パートナー 浅井 将雄氏
ゴールドマン・サックス証券 経済調査シニアアドバイザー 大谷 聡氏
三井住友銀行 副頭取執行役員 小池 正道氏
内閣府 政策統括官(経済財政分析担当) 林 伴子氏
東京大学大学院経済学研究科教授 ナウキャスト創業者 渡辺 努氏
日本のインフレの起点となったのは「コロナ禍とプーチン大統領」
――長きにわたり停滞していた物価が動き始めたのはなぜでしょうか。
渡辺 よく海外の物価上昇が国内に波及したと説明されますが、私は根本的に違うと考えています。確かに輸入物価は上昇しているものの、国内物価はそれ以上に高騰しているからです。この国内要因を説明しなければ、物価上昇の説明にはなりません。
国内物価を単独で動かした要因は、「インフレ予想」です。私たちは毎年春先に各国の消費者に対してインフレ予想調査を実施していますが、これまで日本の消費者は物価据え置きを予想する人が多く、海外とは全く異なる傾向でした。しかし、2022年春の調査で変化が見られました。日本の消費者も物価上昇を予想する人が増え、欧米並みの傾向になったのです。これは大きな変化でした。このインフレ予想の上昇をきっかけに、企業も価格転嫁に踏み切ったというのが私の理解です。
ではなぜインフレ予想が上昇したのかが最も重要なポイントですが、正直なところよくわかりません。しかしさまざまな状況証拠から考えると、2022年にウクライナ戦争が始まったことが一つのきっかけではないかと考えられます。遠い国のできごとではありますが、戦争という大事件、そして小麦やエネルギーの供給不安といった情報が伝わり、また当時すでに8~9%のインフレに見舞われていたアメリカやヨーロッパの社会不安も聞かれるようになりました。こうした中で「日本にも同じようなインフレが起きるのではないか」という連想が人々の間に広がったのではないでしょうか。これが私の解釈です。
インフレ予想が上昇した理由を改めて整理すると、「偶然」と「欧米のインフレ」です。欧米のインフレはパンデミックに端を発していると考えています。つまり、ウイルスとプーチン大統領が日本のインフレ予想を変えたと言えるでしょう。アベノミクスを打ち出していた安倍元首相でもウイルスに打ち勝つことはできなかったでしょうし、プーチン大統領に直接的な制裁を加えることは難しかった。いずれにせよ、こうした強力な外的要因が日本の消費者のインフレ予想を変えたというのが私の認識です。そしてこれが、日本の物価を動かす要因になったと言えるでしょう。
――足元の物価上昇をどのように評価していますか。また、2024年における物価上昇をけん引した品目や要因、特に注目していたポイントについてもお聞かせください。
浅井 弊社キャプラ・インベストメント・マネジメントは典型的なレバレッジヘッジファンドです。私たちが着目するのは市場に存在するごく僅かな価格の歪みであり、相対的に価格差のあるものを収斂させることに主眼を置いています。特に日本市場のポートフォリオにおいては、日本国債に大きくレバレッジをかけ、ロングとショートを同時に行っています。
こうした運用において、顧客に安定したリターンを提供するための基盤となるのが、金融政策の正確な予測です。金融政策の予測には物価の正確な予測が不可欠であると考えており、渡辺氏をアドバイザーに迎えて物価予測に取り組んでいます。
渡辺氏と進めている物価予測プロジェクトでは、日本銀行が可視化しているデータと可視化していないデータの両方に注目しています。日本銀行が可視化しているデータについては渡辺氏の戦略によってほぼ正確に予測できるようになりましたが、もう一方の日本銀行が可視化していないデータをどのように探し出し、それが物価にどう影響するかを分析することが現在の大きな課題となっています。2024年のテーマは米価でした。
私はイギリス在住で米を食べていますが、欧州産のブランド米は2017~2018年時点で日本米の25%~30%ほどの価格で取引されていました。しかし昨年、円安・ポンド高が進んだことで日本米が割安になり、ロンドンをはじめヨーロッパ中の日本食レストランが一斉に日本米の買い付けを始めました。
欧州企業は、12月に新米が出ると1年分の米を予約購入するため、通常より10%ほど高い価格で購入します。加えて円安の影響で、実質的には前年比約40%高い価格で大量の日本米が買い付けられました。これが2024年半ばに顕著になり、2025年も米価上昇が続くと予想されます。これは、全農が提示する米価、ひいては卸売業者が提示する米価に影響を与える可能性があります。ヨーロッパ向けの輸出が増加し、国内流通米よりも高値で取引されるため、この傾向が続けば各種データに大きな変化が現れてくるでしょう。
2024年に続き、2025年も米価上昇が続くと予想しています。外食価格の上昇といったCPIへの影響分析も、われわれのポートフォリオを構築する上で欠かせません。
林 2023年1月に日本のCPIは4.3%に達しました。その後は政策効果もあり同年11月から2024年秋まで2%台で推移しましたが、同年秋以降は食料品価格を中心に上昇が加速し、同年12月の全国平均は3.6%となっています。
食料品価格の上昇要因としては3点考えられます。一つ目は、浅井氏のお話にもあった米価の上昇です。二つ目は、2024年夏の猛暑による生育不良を背景とする生鮮野菜の価格上昇です。三つ目は、為替の変動や物流費の上昇による食料品価格全般への影響です。
これらの結果、2025年1月下旬時点の食料品価格の前年比上昇率は4.7%に達しています。この食料品価格の上昇は、消費マインドへの影響が懸念されます。
2024年の可処分所得は、賃上げと政策効果により上昇率は高まりましたが、消費の伸びは所得の伸びに届きませんでした。これは、所得の増加分が全額消費されず、貯蓄に回っているためです。マクロの貯蓄率は近年4%前後で推移しており、コロナ前の1%と比較すると大幅に上昇しています。
この貯蓄率上昇の背景には、3つの要因が考えられます。一つ目は、食料品を中心とした物価上昇率が4%を超えていることです。二つ目は、恒常所得仮説に基づくと、現在の賃金上昇は一時的なものと捉えられ、消費に回らず貯蓄に回っている可能性があることです。賃金上昇が持続するという認識を人々に持ってもらうことが重要であり、2025年の春闘は重要な意味を持ちます。三つ目は、長生きリスクです。一部の家計では、物価、特に食料品価格の上昇を背景に、将来の生活設計を見直す動きが出ている可能性があります。
こうした状況を踏まえると、CPI上昇率2%を掲げる日本銀行の「物価安定の目標」は非常に重要と考えます。
BtoC取引における価格転嫁の進捗に注目
――1月公表の「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)によれば、日銀は物価上昇が続くとみているようですが、物価の先行きについてはどのようにお考えでしょうか。また、物価の先行きを考える上で特に重要な品目や上振れ下振れ要因となりうるものもあわせて教えてください。
大谷 インフレ率は下げ止まりから反転上昇に向かっており、私も今後の物価上昇は継続すると見込んでいます。現在の物価上昇の最大の要因は、皆様からもご指摘があったように、米国のインフレとその波及効果です。しかし、大局的に見ると、それは一時的な要因であり、今後の物価上昇の基本的なメカニズムは「賃金上昇とサービス価格への転嫁の進展」だと考えています。加えて、円安による輸入物価の上昇も物価上昇に繋がると見ています。
したがって今後の物価動向を考える上で最も重要な点は、賃金上昇に加えて、いわゆる川下のBtoC取引における価格転嫁がどの程度進むかです。賃金は構造的な労働市場の変化を背景に、高めの伸びを続ける可能性が高いと考えています。現在は川上にあたるBtoB取引では賃金を含む価格転嫁がかなり進んでおり、川下のBtoC取引においても緩やかに、しかし着実に価格転嫁が進展していくと予想しています。
物価の上振れ・下振れ要因についても見てみましょう。まず下振れリスクとしては、賃金が上昇していることから可能性は低いと考えていますが、物価上昇によって個人消費が減退し、消費関連財・サービスの価格転嫁が停滞する可能性が挙げられます。
一方、物価の上振れリスクとしては円安が考えられます。市場では、今後の利上げペースと深く関連している円安の物価への影響に加え、価格転嫁の進展、すなわち日本銀行が注目している「2次的物価上昇」のテンポと先行きに対する日銀の見方が注目されていると思われます。
小池 インフレの起点についてですが、先ほど渡辺氏からもご指摘があったように、2013年のアベノミクス開始時は賃金上昇を起点とした好循環を目指しましたが、10年間にわたって実現しませんでした。しかし、2019年の米中関係悪化を契機に世界の分断が始まり、グローバリゼーションの時代は終わりを告げ、デグローバリゼーション時代へと移行しました。これが欧米でインフレを引き起こし、ついに日本にもその波が押し寄せました。
企業はコスト増に対応するために値上げに踏み切りましたが、予想外に売上が落ち込むことはありませんでした。むしろ、値上げが成功したことで、追随する企業が増え、賃上げの原資も生まれるという好循環がようやく回り始めている状況です。つまり、今回のインフレは世界的な分断、すなわち新冷戦によって引き起こされたものであり、この状況が変わらない限りインフレは収まらないでしょう。日本においてもインフレは継続すると考えます。
インフレには様々な上昇・下降要因がありますが、林氏からもご指摘があったように、人間の行動パターンは急速に変化することがあります。例えば日本人の行動パターンとして、横並び主義、つまり他人の行動に追随する傾向があります。
バブル期を経験された方もいらっしゃると思いますが、当時、人々は安いものより高いものを好んで購入する傾向がありました。見栄を張る文化と言えるかもしれません。このような状況になると、期待インフレ率が急上昇する可能性があり、日本でも同様のことが起こる可能性は否定できません。
インフレの様々な上昇・下降要因を考慮しつつも、重要なのは、私たちは既に2%以上のインフレが継続する世界に生きているということです。この認識を共有し、今後の行動指針としていただければ幸いです。