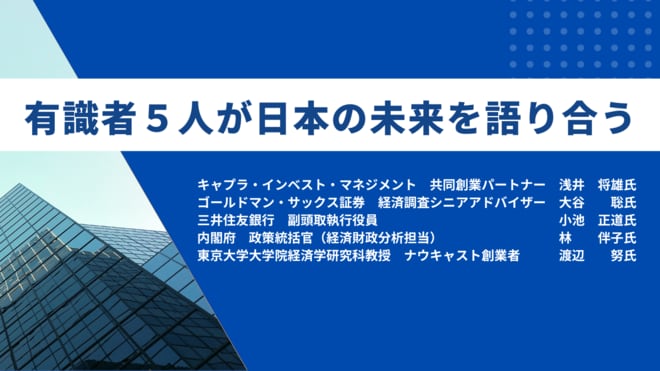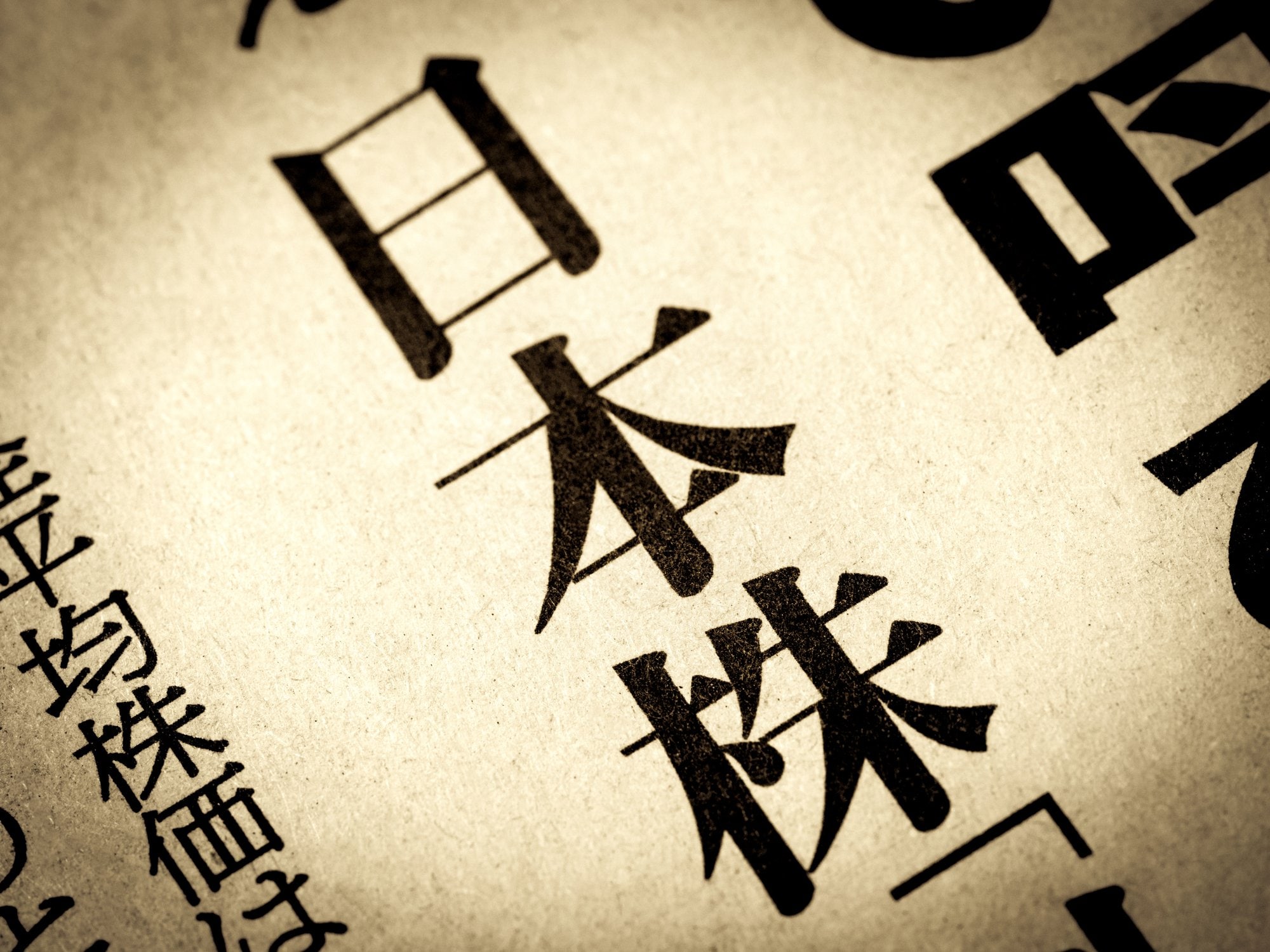パネリスト
キャプラ・インベスト・マネジメント 共同創業パートナー 浅井 将雄氏
ゴールドマン・サックス証券 経済調査シニアアドバイザー 大谷 聡氏
三井住友銀行 副頭取執行役員 小池 正道氏
内閣府 政策統括官(経済財政分析担当) 林 伴子氏
東京大学大学院経済学研究科教授 ナウキャスト創業者 渡辺 努氏
――日本経済の現状をどのように分析・評価していますか。
大谷 人口減少などの人口動態の変化と、転職市場の拡大といった労働市場の構造的な変化により、地域における賃金は上昇しています。これに伴い個人消費も、力強い伸びとはいえないものの堅調に推移しています。かつては物価上昇が個人消費の大きな減少に直結していましたが、2024年は個人消費が落ち込まなかった点が特筆すべき変化と言えるでしょう。
個人消費の底堅さが企業の収益を押し上げ、歴史的な高水準を記録しています。この好調な業績を背景に、企業は積極的な投資スタンスを維持しており、設備投資は脱炭素やDX、省力化投資といった中長期的な視点に基づく戦略的投資がけん引しています。人手不足や工場の供給制約、都市再開発プロジェクトの長期化といった課題は存在するものの、旺盛な設備投資需要のもとでの供給制約は、設備投資が緩やかに増加していることを示唆していると捉えています。
このように2024年は、賃金上昇と高水準の企業収益を起点として、所得から支出への好循環が強まりました。日本経済は人口減少の影響を受けGDP成長率は高水準とは言えず、力強い経済成長とまでは言い切れませんが、それでも経済の頑健性は高まっていると評価できます。また物価上昇の影響を直接的に受ける低所得世帯の消費動向には注意が必要ですが、マクロ経済の視点から見ると、日本の実体経済、特に国内民間需要については大きな懸念材料は見当たらない1年だったと言えるでしょう。
課題となる実質賃金 春闘で「6%」を目指すべき
渡辺 消費は腰折れしていないという点については大谷氏と同感です。しかし、2024年の経済指標や企業業績を見る限り、景況感は必ずしも強くないこともまた事実です。この点について考察したいと思います。
消費が伸び悩んでいる理由の1つとして、実質賃金の問題が挙げられます。消費の抑制は、実質賃金の上昇が限定的であることに起因しており、実質賃金が上がらない原因を分析することが重要です。
実質賃金に応じて労働供給と需要が決まるという経済学的モデルにおいて、現在の人手不足は労働需要の超過を示唆しており、実質賃金の上昇が不可欠です。名目賃金ではなく実質賃金の上昇こそが重要なのです。人手不足が実際に発生している現状を踏まえると、実質賃金は上昇するはずでしたが、現実はそうなっていません。
この理由の1つとして、過去の事例や他国の状況を参考にすると、パンデミック直後のアメリカのように労働供給が制約された時期には、一時的に賃金上昇の期待が高まりました。しかし、実際には物価上昇に追いつかず、実質賃金は下落しました。アメリカでも比較的最近になって実質賃金が上昇し始めたことから、労働需給と実質賃金の間にはタイムラグが存在し、実質賃金は時間をかけて反応する可能性が示唆されます。この点を踏まえると、今年あるいは来年にかけて人手不足とそれに伴う実質賃金の上昇が本格化する可能性も考えられます。
2024年以降の実質賃金の低迷の理由を別の視点からも見てみましょう。例えば名目賃金と物価に分けて考えると、物価上昇のペースに名目賃金の上昇、特に春闘での賃上げが追いついていないことが原因と考えられます。2022年の夏ごろから連合と物価上昇の見通しや賃上げ要求水準について議論を重ねてきましたが、当時はまさに「手探り」状態であり、適切な賃上げ要求水準を判断することは困難でした。結果的に、2022年末に設定された5%という賃上げ要求水準が、その後の春闘における基準となりました。
この5%という水準は低かったのではないかと決定にかかわった1人として反省しています。当時の見通しよりも実際の物価上昇率が大きくなったため、結果的に賃上げ水準が控えめになってしまいました。5%が基準として残ってしまったことが、現在の実質賃金の低迷につながっている可能性があります。
仮に6%の賃上げが実現していれば、現在の実質賃金は上昇していたと考えられます。今年度の春闘はすでに「5%以上」を目標にスタートしており、今から変更することは難しいですが、来年以降については、6%程度を新たな基準として検討する必要があるでしょう。
――2025年以降の日本経済の展望や直面するであろう課題、経済の上振れ・下振れ要因として注視している点についてお聞かせください。
浅井 2025年は、日本銀行が金融政策の正常化を確実に進める1年になると考えています。もちろん、下振れ要因として7月の参議院選挙による政治の不安定化、そして財政・為替の変動リスクなどが挙げられます。財政問題は日本経済にとって大きな課題ですが、2008年と比較して日本の金融機関のバランスシートは健全であり、海外勢からの「攻撃」を受ける可能性は低いと見ています。
政治の混乱に伴う資産価格や為替の変動は下振れ要因となる可能性がありますが、むしろ上振れ要因の方がより強いと考えています。日銀総裁が指摘する海外の不確実性についても、上振れリスクの方が大きい可能性があります。地政学リスクの大幅な減少やエネルギー価格の小幅な下落といったポジティブな要素、そして賃上げによる経済の過熱感など、ポジティブサプライズが発生する可能性も想定されます。
数値的には、実質GDP成長率1%、CPI2%という日銀の目標値を上回る可能性が高く、特に年後半には経済の過熱感が顕著になるかもしれません。名目GDP成長率についても、一時的に大きく変動する局面が現れる可能性があると予想しています。
小池 今年の日本経済については非常に楽観的に見ています。周知の通り、デフレは終焉し、インフレ時代へと突入しました。この状態は今後10年程度続くと考えています。実際、家計や企業の行動様式はすでに変化しています。
家計においては貯蓄から投資へのシフトが進んでおり、企業においても内部留保を重視する経営姿勢から設備投資など積極的な投資へと転換しています。近年、日本企業の経営者の間では「価格転嫁」「賃上げ」「ROE向上」がキーワードとなっており、これらの議論が活発に行われています。
こうした変化の中で、今後、健全な競争が日本経済に生まれると予想しています。具体的には、すでに一部で始まっている業界再編や企業の淘汰が進むと考えています。一見すると厳しい状況のようにも見えますが、これは経済活性化に向けたよい兆候と捉えるべきです。
日本企業や日本人は決して脆弱ではなく、政府による適切なセーフティーネットの整備を前提とすれば、賃金水準の高い企業への人材流動化が促進され、生産性向上につながると見込んでいます。このように、日本経済の将来は明るいと言えるでしょう。
一方で、消費の伸び悩みを懸念する声もありますが、3年目となる今年の春闘における賃上げは、消費を喚起する上で重要な転換点になると考えています。以上のことから、今年は日本経済にとって良い年になると期待しています。
労働マッチングのDXで雇用・所得環境のさらなる改善に期待
林 浅井氏、小池氏による力強いお話、大変心強く感じます。
日本経済の先行きについては、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復が続くと考えています。ただし、海外経済に関しては、米国の政策動向や中国の不動産価格下落による内需停滞など、注意すべき点も存在します。国内経済については、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復が続くと予想しており、特に消費、物価、賃金、労働市場の動向に注目しています。
日本の賃金動向を見ると、名目賃金は2022年5月以降、8カ月連続で2%以上の上昇を記録しており、これは1992年以来33年ぶりのことです。また、企業の人手不足感も強まっており、非製造業ではバブル期並みの水準となっています。ただし、労働需給のミスマッチも存在し、これが供給制約の一因となっている可能性があります。
日本は人口減少という課題を抱えていますが、労働参加率の上昇により就業者数は6800万人まで増加しています。労働参加率の上昇の背景にはさまざまな要因がありますが、労働市場のDXによるマッチング効率化もその一つです。従来、仕事探しはハローワークが主流でしたが、現在ハローワークで仕事を見つける人は全体の15%に過ぎません。
民間職業紹介やスポットワークアプリの普及が急速に進んでおり、主要5社の登録者数は2800万人に達しています。パート・アルバイトはもちろんのこと、正社員の副業にもこれらのアプリが活用されており、1日だけのスポットワークから長期雇用へと移行するケースも2割程度あると聞いています。このように、労働市場のマッチング効率化は大きな変化であり、賃金上昇と労働市場における資源配分の変化、そしてDXによるさらなる変化の加速に期待しています。