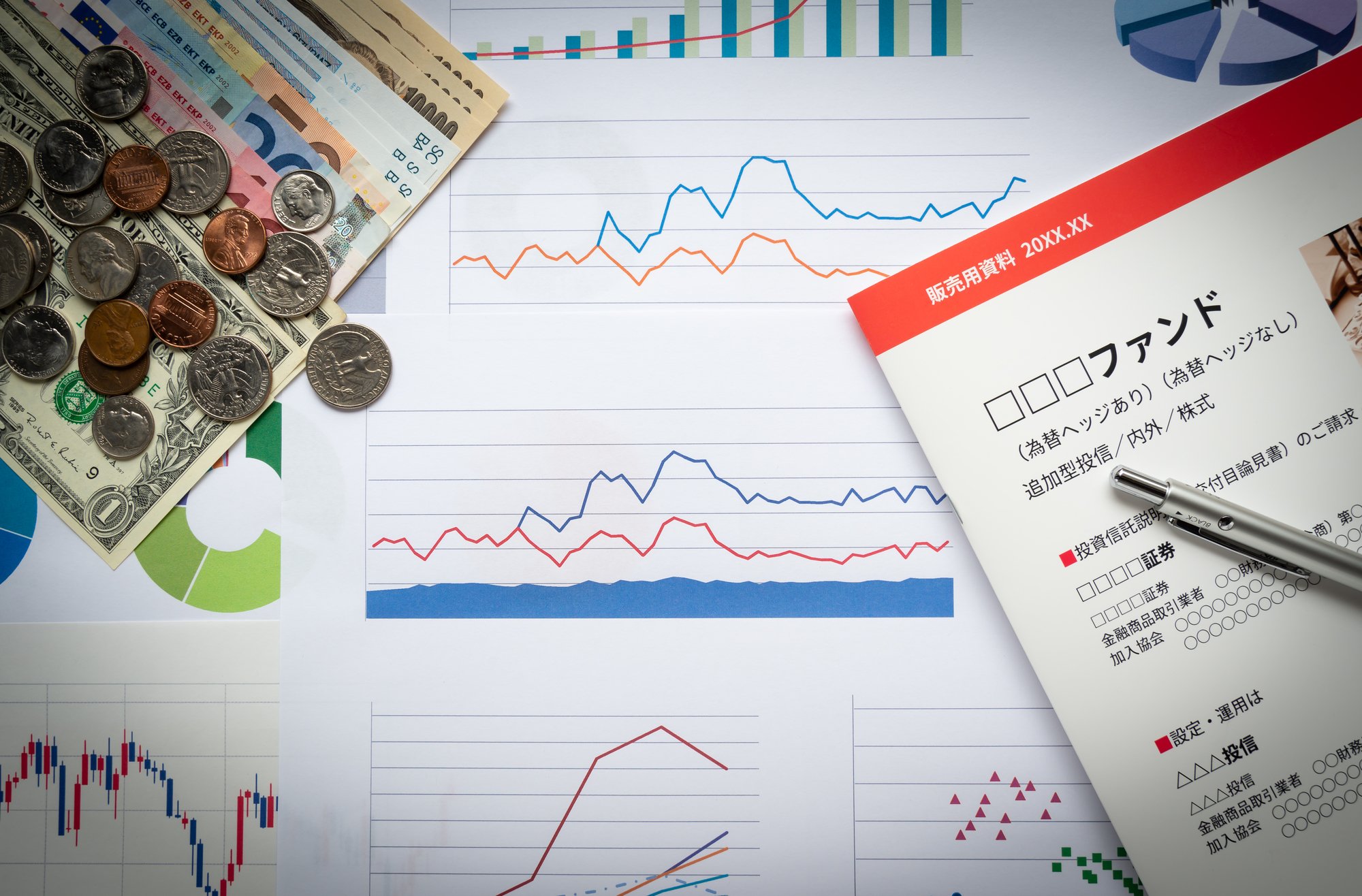なぜ口座数の伸びは鈍化しているのか?
このように買付額は大きく伸びましたが、NISAが全国民的な制度になっているかどうかを判断するには、やはり口座数の伸びが重要になってきます。
口座数の増加が伸び悩んでいるのは前述したとおりです。では、どうして伸び悩んでいるのでしょうか。
第一の理由は、あくまでも仮定に基づく話ですが、やはり「日本人は投資が嫌い」ということ。本当にそうなのかどうかは定かでありませんが、これだけ大きな非課税メリットが打ち出されているのに、新NISAのスタートからわずか9カ月間で、新規の口座開設が伸び悩んでいるのは、日本人の多くが根本的に投資を嫌っているのか、それともどこかに使い勝手の悪さがあるからです。
新NISAの生涯非課税枠や毎年の非課税投資額上限が煩わしいのかも知れませんが、成長投資枠だけでも1年で240万円の非課税投資額が設けられています。これを全額満たせるような人は、そんなにいないでしょう。また1800万円の生涯非課税枠も、個人が保有している金融資産の中央値を見れば十分とも言えます。
となると、NISAの口座数が伸び悩んでいるのは、使い勝手に問題があるとも考えられます。たとえば、課税口座との損益通算ができないことや、1人1口座の問題に関しては、まだ解決できる余地がありそうです。
特に後者については、直販のみで販社を使わない投資信託会社から、かなりの口座ならびに資金流出を招いているという事実があります。
せっかく1800万円もの生涯非課税枠があるのだから、その良しあしは別にして、利用者側からすれば、もっと他の商品にも資金を分散させたいというニーズはあるでしょう。
最近は金融機関の口座を開設する際に必ずマイナンバーの提示を求められます。これを使って名寄せができれば、「1人複数口座」も可能ではないかとも思うのですが、何しろ税の問題が絡んでくるだけに、実現にはまだ時間がかかりそうです。
ところで、これは余談ですが、旧NISAがスタートする直前、某運用会社のお誘いで、NISAの原型となるイギリスのISAを視察する機会がありました。空港からロンドン市内までタクシーで移動する際、運転手に「ISAを知っているか」と聞いたところ「もちろん。自分も利用している」との答え。ISAがイギリス国民に幅広く浸透していることを、改めて認識しました。願わくば、日本のNISAも、このくらい普及してもらいたいところです。