2025年の米国、日本それぞれの景気は…
――ご著書では、「金融政策サイクル(長短金利差)」、「信用サイクル」といった“周期”があること、そして日本の場合は、米国の影響を大きく受ける点をご解説され、これらで過去を検証し、中長期的な展望も綴られている点が印象的でした。こうした視点で見て、2025年の今、米国、日本はどのような状況にあると見ていますか。
米国経済は、約5年周期の金融政策サイクルでは、利上げ効果で景気は減速していますが、約10年周期の信用サイクル(米銀の融資姿勢と企業の借入需要の関係)は良好なので、信用サイクルが景気の下支えとなり、今の景気減速は限定的なものにとどまる見込みです。米国株式市場の調整があっても、大幅なものではないと考えます。
日本経済は、長く続いたデフレ状態からも脱却する局面にあり、長期金利の上昇はそのサインと思われます。同時に、米国の金融政策、日本のQT(資金吸収)やマネタリーベースの動向など、利上げの継続にはいくつもの関門が待ち受けており、日銀の手腕が試される時代に入ったとも言えそうです。
今後を知りたいなら、今までの道のりを理解することが、一番の近道です。日本は否応なしに米国の影響を受けていますので、ぜひ本著を読んで、米国経済と併せて日本を考えるようにしてみてください。
――そのような環境下で、NISA等を活用しながら、積立投資をする意義はどのようなところにあるでしょうか。また昨今よく目にするのが、「資産形成は全世界株式(もしくはS&P500)インデックスファンド1本さえ持っておけばOK」という情報です。こうした情報に対して、FMとしての意見や個人の運用へのアドバイスをお願いします。
インフレ局面では、現金の実質価値が目減りするため、資産運用が必要と考えます。そして、資産運用の極意は、と聞かれれば、「長期運用」の一言に尽きます。
しかし、金融市場に価格の上下はつきものだと分かっていても、一喜一憂し、特に下落局面では不安になり、売ってしまいたくなるのが投資の“あるある”で、長期運用とは言うほど簡単ではありません。
そこで、「長期運用」を実現するためにおすすめするのが、「積立投資」です。例えば、毎月末に1万円ずつ購入するなど、投資タイミングを分散する手法です。異なる商品をいくつか購入すれば、投資先の分散にもなり、運用資産の変動を抑えるのにも有効なので、精神的にも金銭的にも長続きしやすいはずです。実際、世界最大の機関投資家でもあるGPIF※も、内外の株式・債券に分散投資することで、運用収益を積み上げています。
たしかに、「全世界株式(もしくはS&P500)インデックスファンド」は、さまざまな国や企業(もしくは米国)の株式に分散投資する分かりやすい商品の1つで、これ一択で十分という考え方もあるでしょう。
ただ、自分のお金なのですから、本著をお読みいただき、株式だけでなく、債券・金・為替(ファンド含む)など市場の分散を図ったり、景気動向に応じて多少メリハリを利かせた商品選択をしたりと、ご自分の判断で、ご自分に合った長期運用を実現していただけると著者冥利に尽きます。
※ 年金積立金管理運用独立行政法人
――『金利を見れば投資はうまくいく 日本編』を手に取りながら、投資やマーケットについての知識をアップさせたい投資家は日ごろどのような情報を注意して見ていけばよいでしょうか。
ぜひやってみていただきたいことが1つあります。
それは、金利の上下を考える際、「短期金利」と「長期金利」を区別するクセをつけること。特に、政策金利の変更など重要なイベントがあった時に、経済の先行きを判断するのに有効です。
例えば、昨年7月の日銀による利上げで、短期金利は上昇、長期金利は低下しました。この「長期金利の低下」は、「早すぎる利上げが、景気や株価にマイナスだ」というサインを送っていたのです。
本著の主題となりますが、長短金利のどちらがどう動くかで、サインの意味が異なるので、長短金利の動きが区別できれば、きっと正しい景気判断・投資判断につながると思います。
――ありがとうございました。
マネックス・アセットマネジメント
債券運用部長
堀井正孝氏

国内有数である先進国債券ファンド「グローバル・ソブリン・オープン(通称グロソブ)」の元運用責任者。第一生命保険および系列運用会社、国際投信投資顧問(現三菱 UFJアセットマネジメント)、SBI系列運用会社での債券運用歴 30年超。著作に『改訂版 金利を見れば投資はうまくいく』など。
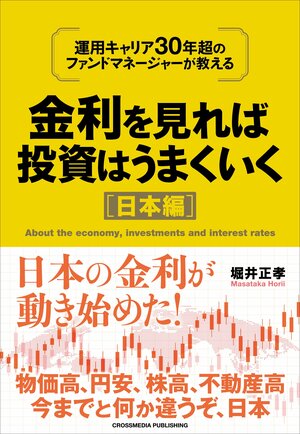
米国中心に金利と経済を詳しく解説したベストセラー『改訂版 金利を見れば投資はうまくいく』の日本版。景気を春夏秋冬の“周期”でとらえることを軸に、過去の金融政策を振り返り、金利のある世界に戻りつつある日本の景気を把握し、この先どのようなシナリオが想定されるか解説。(クロスメディア・パブリッシング/1848円〈税込み〉)






























