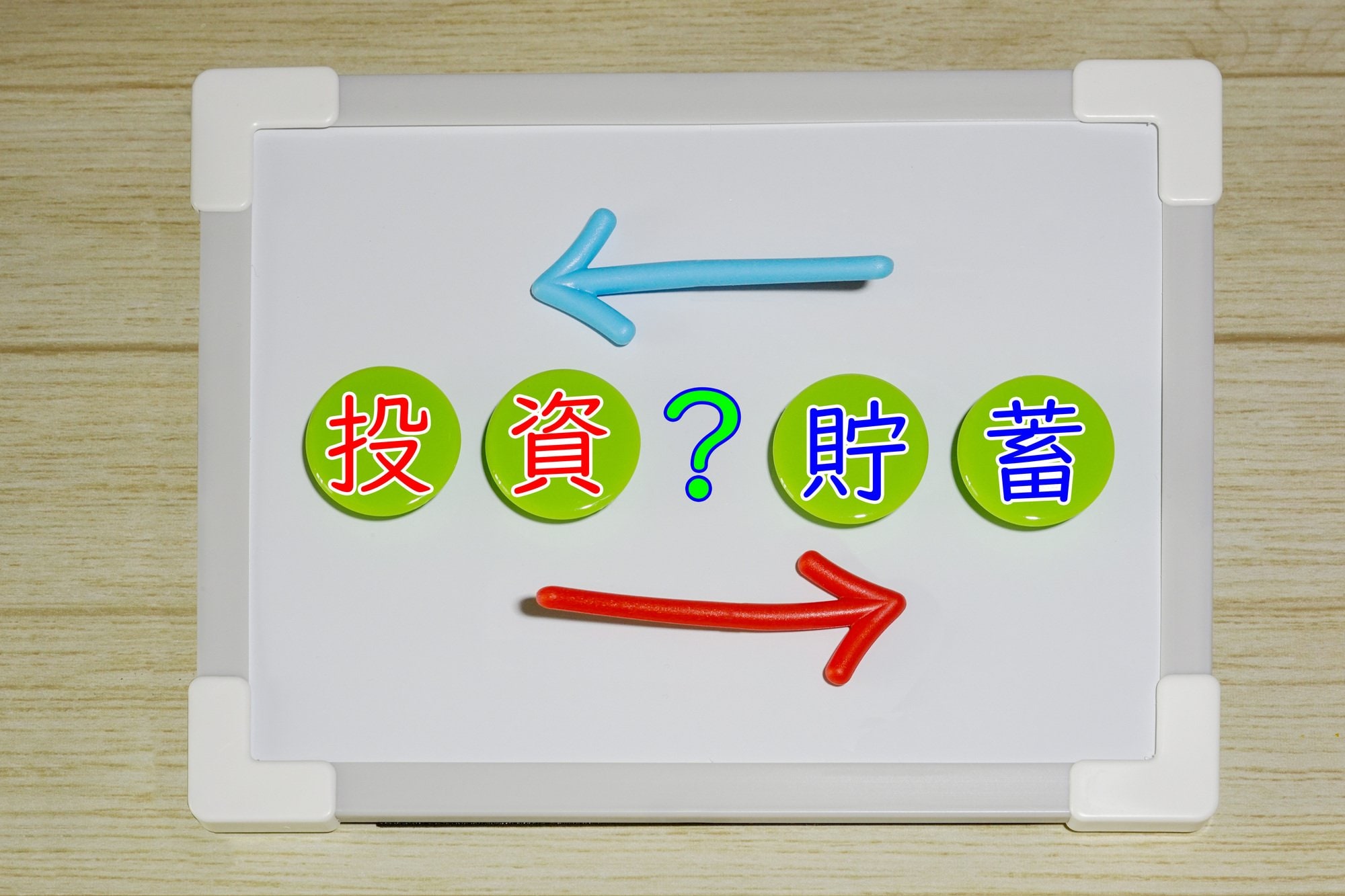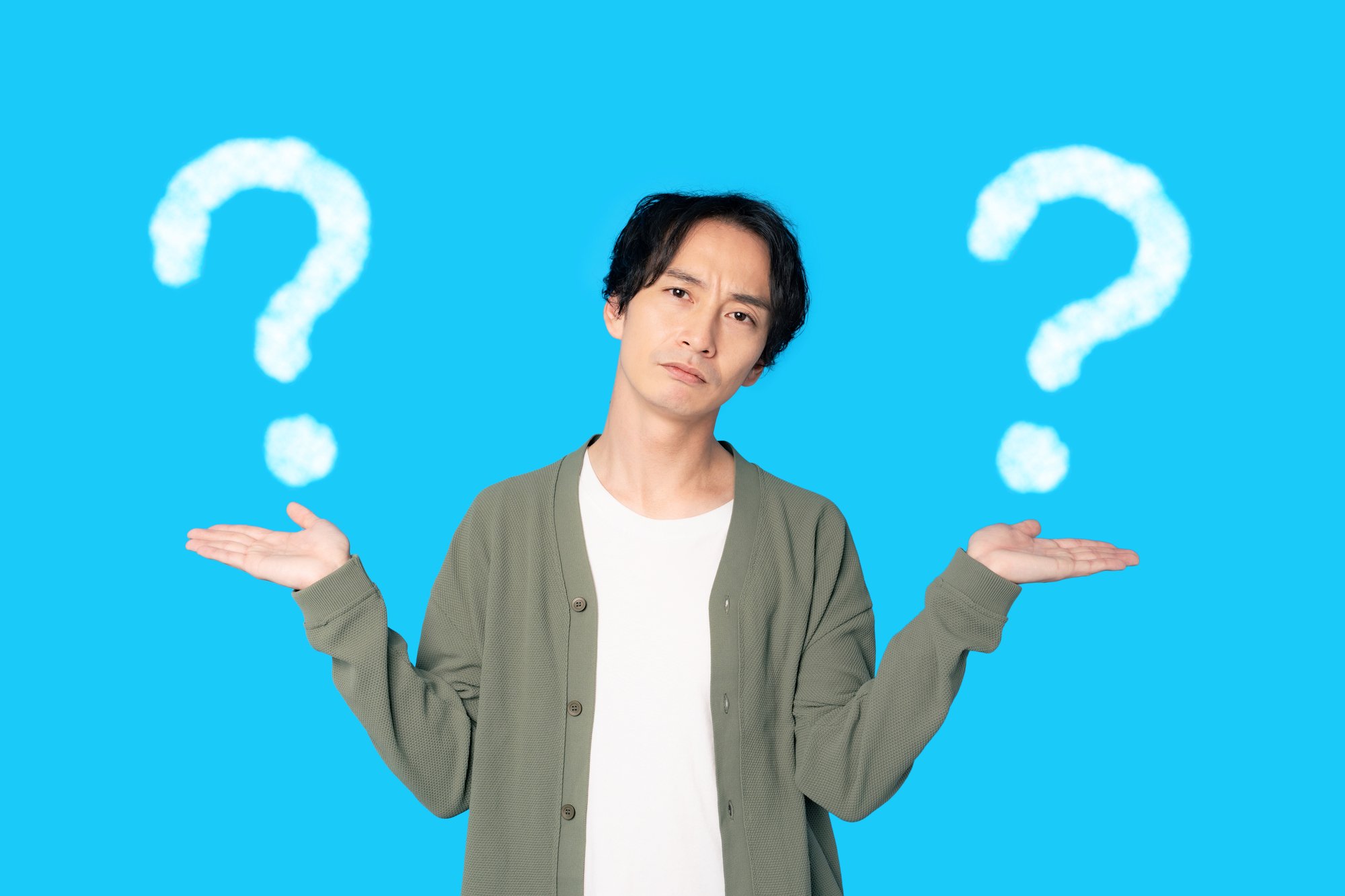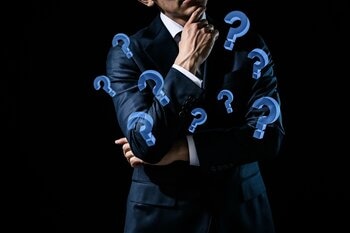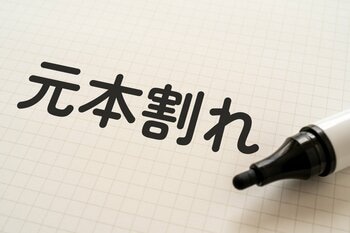20代&30代:リスクを取る余裕がある年代
結果からは20代と30代の積極的な投資姿勢が明らかだ。特に20代二人以上世帯では積極派が全年代・世帯で最も多い。SNSなどの普及の影響もあり、若いうちから資産形成の重要性が認識されつつある上に、時間を味方につけた長期投資が可能な年代であることが一因だろう。資産を安全に保つための行動にも積極的で、特に情報収集にも熱心な傾向がある。老後まで十分な時間があることを強みに、NISAやiDeCoなど税制優遇制度についても情報を集め、活用することも一案だ。
40代&50代:バランスを模索しつつ老後準備
40代、50代になるとリスク性商品への積極姿勢はやや弱まるものの、依然として一定数の積極派が存在する。まだ十分リスクを取って資産を増やしたいという意向は物価上昇が続く現在を見据えての判断だろう。老後に向けた資産形成を継続しつつも、リタイアまでの時間を鑑みてリスクとリターンのバランスを考えた運用を継続したい年代だ。
60代&70代:安全性重視で判断
60代、70代になるとリスクを取った投資には消極的な姿勢が強まる。多くがすでに退職を迎え、年金生活に入っていることから資産を減らしたくない意識が強いはずだ。中でも70代単身世帯は消極派が66.1%と、全年代・世帯で最も高い。一方で二人以上世帯は消極派がやや減少する。老後資金を守りたい一方で、インフレリスクへの対応や余裕資金の運用など、守りながら増やしたいと状況に応じて判断している世帯もあることがうかがえる。毎月の資金計画と照らし合わせ、無理のない運用が望まれる。
預貯金にもリスクはある
全年代を通して見ると、若い世代ほどリスクを取った運用姿勢が強く、年代が上がるにつれ消極的になる傾向が明確だ。時間の余裕やライフステージの違いを反映した結果といえる。また、二人以上世帯の方が単身世帯よりもリスクに前向きな傾向があるようだ。
元本割れ対策は、若い世代ほど積極的に行っており、特に情報収集や預け先の分散など基本的な対策を取っている。しかしどの年代でも「何もしていない」世帯が最も多く、元本割れ対策の重要性が十分に認識されていない可能性もある。
元本確保型の預貯金であってもリスクがないわけではない。金融機関の破綻時には1金融機関あたり1000万円とその利息までしか原則保護されない。ほかにも最近の物価上昇による資産価値の目減りなど多様な側面にリスクは潜んでいる。自身の状況を鑑み、年齢や生活に応じた適切な資産管理を継続していくことが必要だ。
<調査概要> 調査名/「家計の金融行動に関する世論調査2024年」(金融経済教育推進機構) 調査時期/令和6年6月21日~7月3日 調査対象/単身世帯:全国2,500世帯(20歳以上80歳未満で単身で世帯を構成する者)、二人以上世帯:全国5,000世帯(世帯主が20歳以上80歳未満で、かつ世帯員が2名以上)、総世帯:令和3年調査より二人以上世帯、単身世帯の調査方法が同一となったことから、両調査の計数を合算する形で作成を開始した参考計表 調査方式/インターネットモニター調査