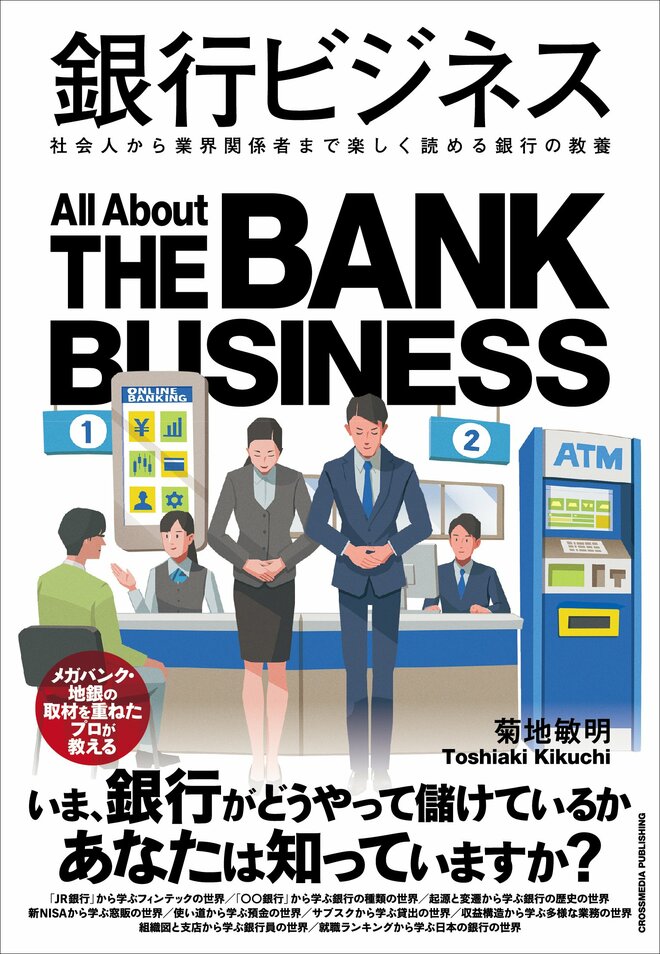個人投資家が増えれば日本の成長につながる
もっとも、いくら資産運用を始めても、結果として資産が増えなければ意味がないのも確かでしょう。ただし、それはマーケット次第のところもありますし、投資である以上は必ず儲かるなどと言い切ることはできません。それでも、金融庁が公表している資料によると、米国の家計金融資産は2022年末の時点で1京4517兆円、一方の日本は2023年9月末時点で2121兆円。注目したいのが増加率で、米国は2002年からの20年強で3.3倍になっているのに対し、日本はわずか1.5倍にとどまっています。しかも、米国ではそのうち運用によるリターンで2.4倍になっているのに対し、日本はわずか1.2倍。この数字をみても、運用の有効性と「貯蓄から投資へ」の必要性がわかるのではないでしょうか。
また、米国では多くの個人投資家の資金が、株式市場を下支えしている面もあります。日本でも同様に個人投資家が増え、それが日本の株式市場の後押しになれば、企業の成長にもつながるはずです。企業が成長すれば賃金も上昇し、消費が拡大することで企業の売り上げも増加します。企業の成長によってさらに株価が上昇すれば、投資家はそのリターンを得られます。つまり、投資家、企業、従業員がそれぞれ恩恵を受けられるという「好循環」が生まれるのです。それが「貯蓄から投資へ」の意味であり、その担い手となる銀行の役割もこれからますます重要になるのでしょう。
そうした中、前回触れた手数料に関しても、新たな取り組みが始まろうとしています。単なる販売からコンサルティング営業へと舵を切る中、販売手数料や信託報酬の位置づけも変わりつつありますが、そもそも商品に紐づけること自体に少し無理があるのは否めません。そのため、顧客の投資資産額に対して、例えば1%といったように一定の料率で手数料を取るといった仕組みが模索されているのです。
そうすると、顧客の資産が増えれば銀行の収益も上がることになり、いわゆるWin-Winの関係になれるわけですね。さらに、商品とは関係なく、ファイナンシャルプランニングなどのコンサルティング自体に手数料を取るといった取り組みも一部の銀行では始まっていますから、今後も窓販のあり方はさらに変化していくことになるのでしょう。銀行にとって窓販は「第4の業務」の中心であるのにとどまらず、「貯蓄から投資へ」の担い手としての社会的な使命でもある。そういっても過言ではないのかもしれません。
銀行ビジネス
著者名 菊地敏明
発行元 クロスメディア・パブリッシング
価格 1848円(税込)