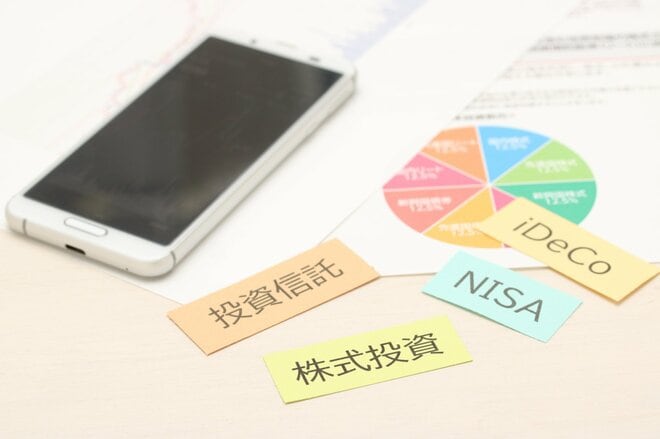2001年に政府が打ち出した「貯蓄から投資へ」。この流れは、新NISA制度などの手助けもあり、ますます加速しています。
個人による投資が拡大する中、人々のお金を預かる銀行でも大きな変化が起こりました。
2000年前後に始まり銀行の新たな業務として拡大・定着した投資信託や保険の窓口販売、通称「窓販」の世界から、その変化について論じます。(全3回の3回)
※本稿は、菊地敏明著『銀行ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を抜粋・再編集したものです。
なぜ「貯蓄から投資へ」が必要なのか
「顧客本位の業務運営」の浸透もあって大きく変化した銀行は、「貯蓄から投資へ」を推進 する日本において、ますます重要な役割を担うことになるのでしょう。けれども、そもそも本当に「貯蓄から投資へ」が必要なのか、懐疑的な人も少なくないはずです。ネットやSNSの書き込みの中にも、「政府は国民の預金を奪おうとしている!」といった陰謀論を唱えるものがあったりします。
ここで改めて、「貯蓄から投資へ」がなぜ必要なのか、その意義を考えてみましょう。まずは、日本の少子高齢化の現状を国立社会保障・人口問題研究所が2023年に公表した「日本の将来推計人口(令和5年推計)」でみてみると、2020年には現役世代(15~64歳)2.1人で高齢者(65歳以上)1人を支えている状況が、2038年には1.7人で1人を、2070年には1.3人で1人を支える状況になると推計されています。
2024年7月には、5年に1度行われる公的年金の「財政検証」の結果が公表されました。それによると、現役世代の男性の平均手取り収入に対する年金額の割合を示す所得代替率の見通しは、さまざまな前提によっても異なるものの、もし経済の状況が過去30年と同程度であれば、2024年度の61.2%が、2060年度には50.4%になると予想されています。つまり、現役世代の平均収入の半分程度しか年金では賄えないわけです。2019年の前回の財政検証よりも改善した部分もありますので、「年金崩壊」などと過度に悲観的になる必要はないにしても、依然として楽観できない状況ではあるでしょう。
だからこそ、自助努力で公的年金を補わなければならず、その手段の1つが資産運用なわけですから、「貯蓄から投資へ」が必要になるのです。そのため、政府も単に呼びかけるだけではなく、その推進役となる銀行などの金融機関に「顧客本位の業務運営」を徹底させ、さらにNISAのような税制優遇制度を作ったり、iDeCoのような私的年金制度を拡充させたりと、さまざまな後押しをしてきました。