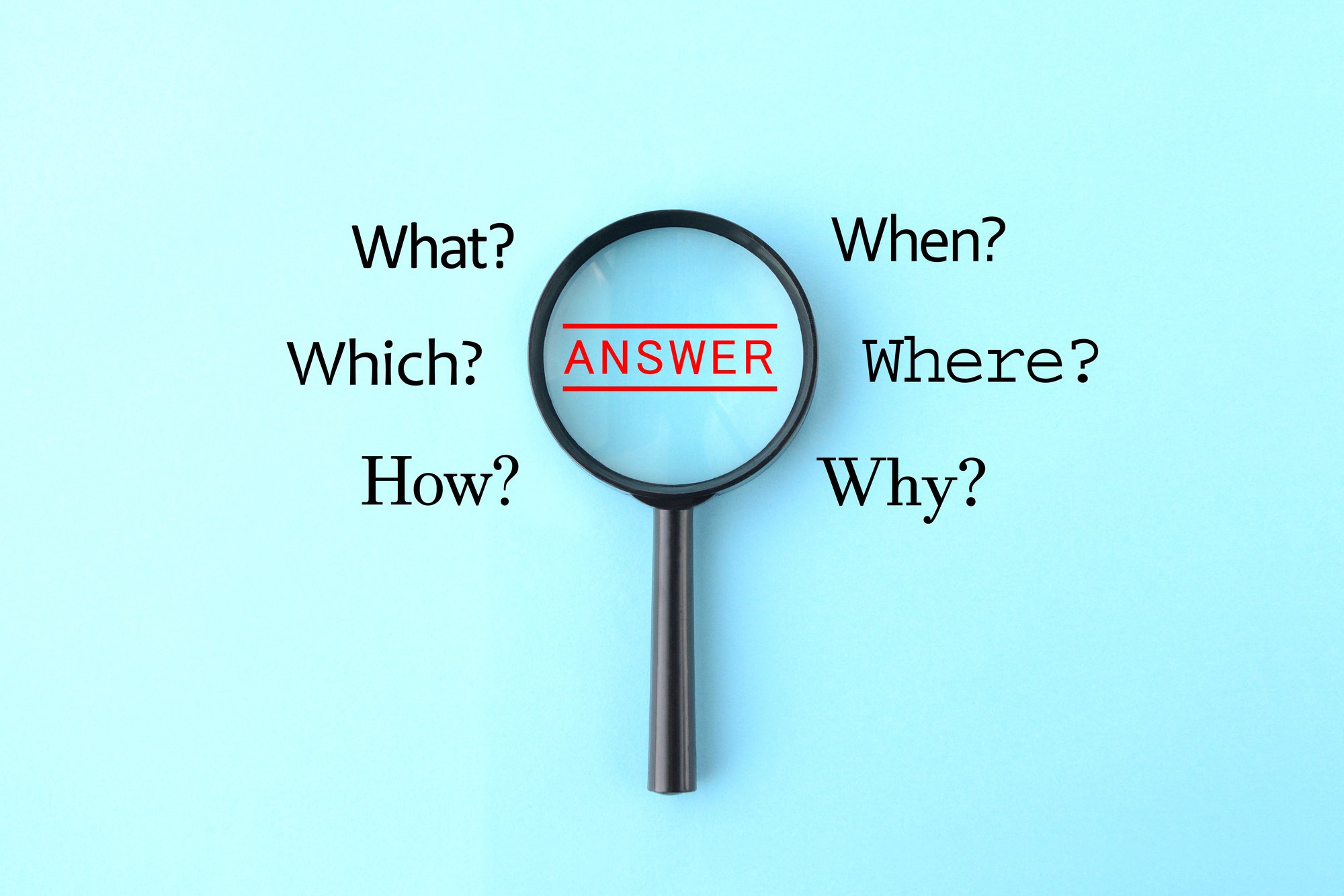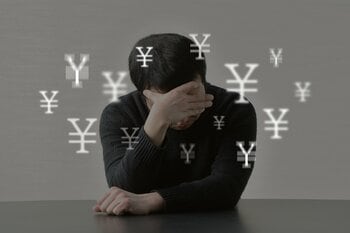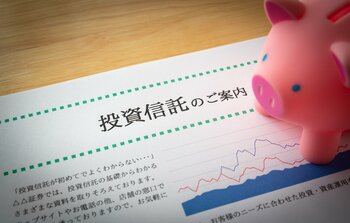投資家保護の仕組みにも目を向けたい
もう一つ重要なのが、KYC(本人確認)や適合性確認(Suitability)など、投資家保護の観点です。
金融商品を販売する際には、「誰が買うのか」「その人のリスク許容度や投資経験はどの程度か」などを踏まえ、本当にその金融商品が適しているかどうかを販売側が事前にチェックすることが不可欠です。こうした仕組みがあることで、投資家が自分に見合わないリスクを負うことを未然に防ぐことができます。
また、KYCには投資家の属性を確認するだけでなく、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正取引を防ぐ役割もあります。
アメリカのデジタル証券では、ウォレット開設時に厳格な本人確認が行われ、対象投資家を適格投資家に限定する仕組みも整えられているようです。
一方、日本では現在は証券会社などを通じてKYCは行われていますが、今後デジタル証券が発展するにつれ、取扱い主体や販売チャネルごとのルール整備、投資家保護の一層の強化が求められていくでしょう。
投資の本質は「形式」ではなく「中身」
「デジタル証券」という言葉には、あたかも先進的かつ魅力的な資産であるかのような響きがあります。しかし、投資形態が変わっても、投資対象の持つ本質的な価値が変わるわけではありません。
トークン化が価値を生むためには、常に売買のニーズがあり、価格が安定し、投資家保護の仕組みが整っている資産から始めるのが良いかもしれません。アメリカでMMFや米国債からスタートしているのは、投資資産の本質的な性質と、投資家保護の仕組みから考えたときに、無理のない実効性を重視しているからです。
日本でも今後、デジタル証券が本格的に普及していくためには、表面的な技術やイメージの新しさにとらわれず、資産の性質や投資の本質に根ざした取り組みが求められていくでしょう。