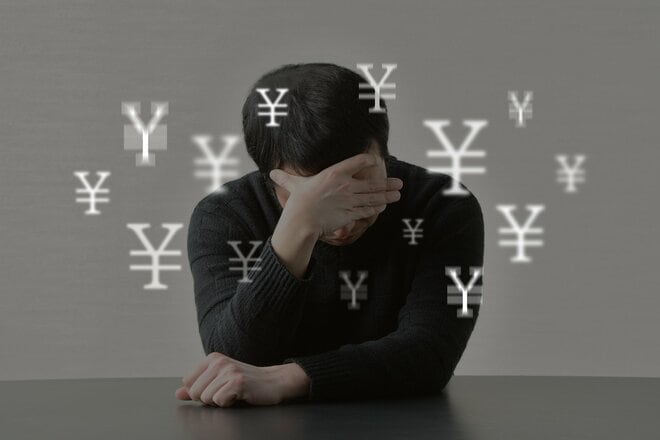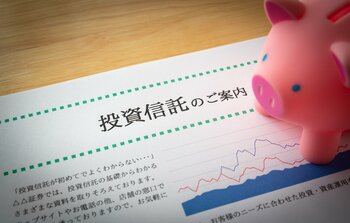2025年7月、不動産クラウドファンディング業界に衝撃が走りました。「ダイムラーファンド」などのブランド名で展開してきた「ダイムラー・コーポレーション」(本社/神奈川県横浜市)が破産し、投資家から集められた資金の多くが返還されない見通しだと報じられています。他のクラウドファンディングに投資している方も、不安を感じているのではないでしょうか。
「倒産隔離」のないクラウドファンディングが多い現実
今回の破産は決して例外的なケースとは言い切れないのではないでしょうか。というのも、実は日本の不動産クラウドファンディングの多くが、今回のダイムラー社と同じような構造的リスクを内包しているためです。その本質は、「運営会社(営業者)と投資家資金の間に法的な壁(倒産隔離)がない」という点にあります。
多くの不動産クラウドファンディングでは、運営会社本体が営業者となり、投資家はその会社と直接、匿名組合契約などを結ぶ仕組みです。この場合、運営会社が倒産すると、投資家の資金やファンド資産も他の債権者と同じように破産手続きに取り込まれ、資金が守られないのです。
なぜ倒産隔離できないのか? 法制度の限界
なぜこうしたリスクが構造的に存在するのでしょうか。
その理由は、不動産特定共同事業法(不特法)の規制体系にあります。現行の多くのクラウドファンディングが運営するライセンスの枠組みでは、運営会社本体が営業者となる仕組みが前提です。
2013年に同法が改正されたことによって合同会社等をSPC(特別目的会社)として利用する「倒産隔離スキーム」も制度上は認められるようになりましたが、現実には一般投資家向けクラウドファンディングではあまり普及していません。依然として「営業者=運営会社本体」の方式が主流で、倒産隔離が実現している案件は少ないようです。