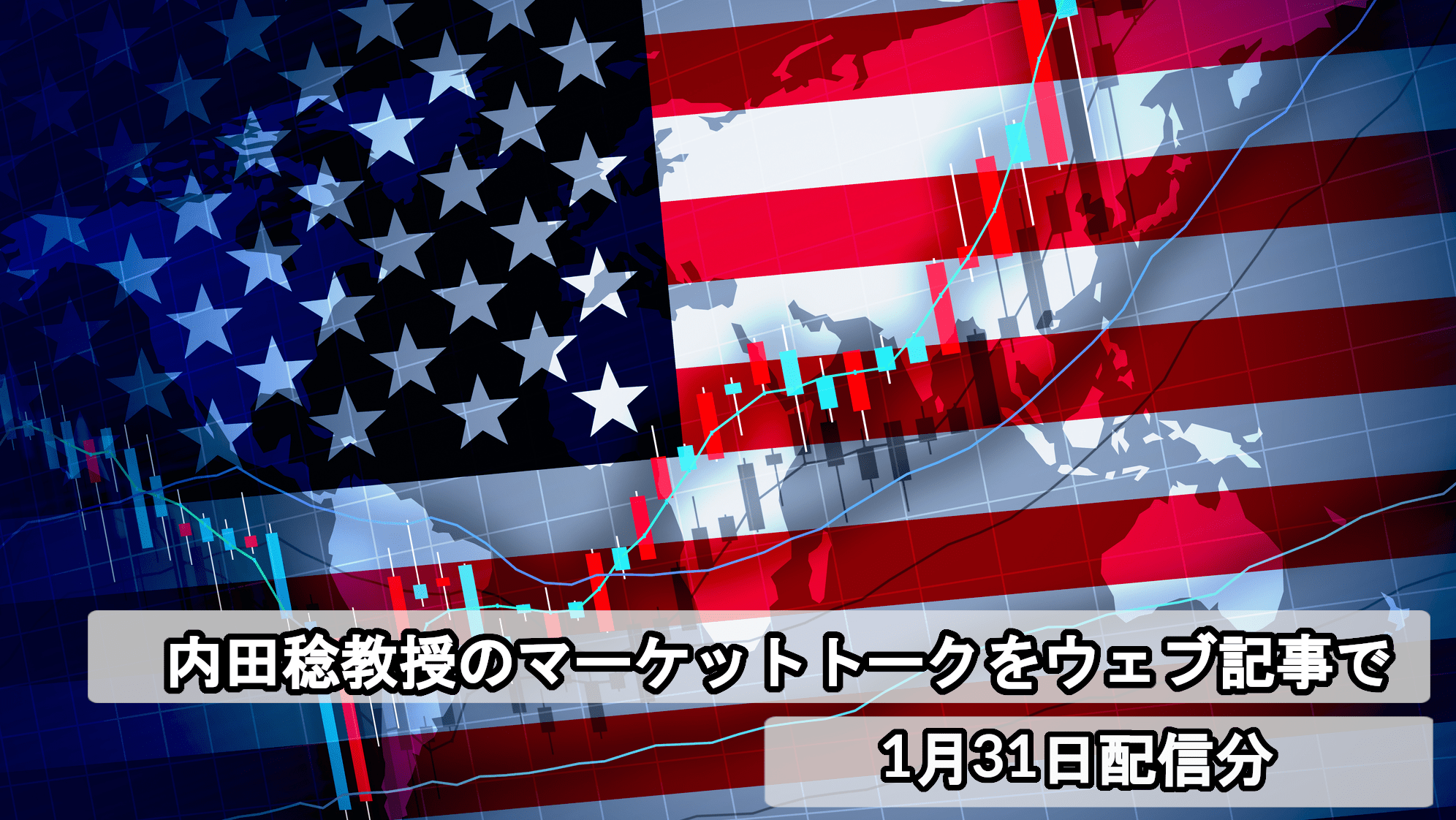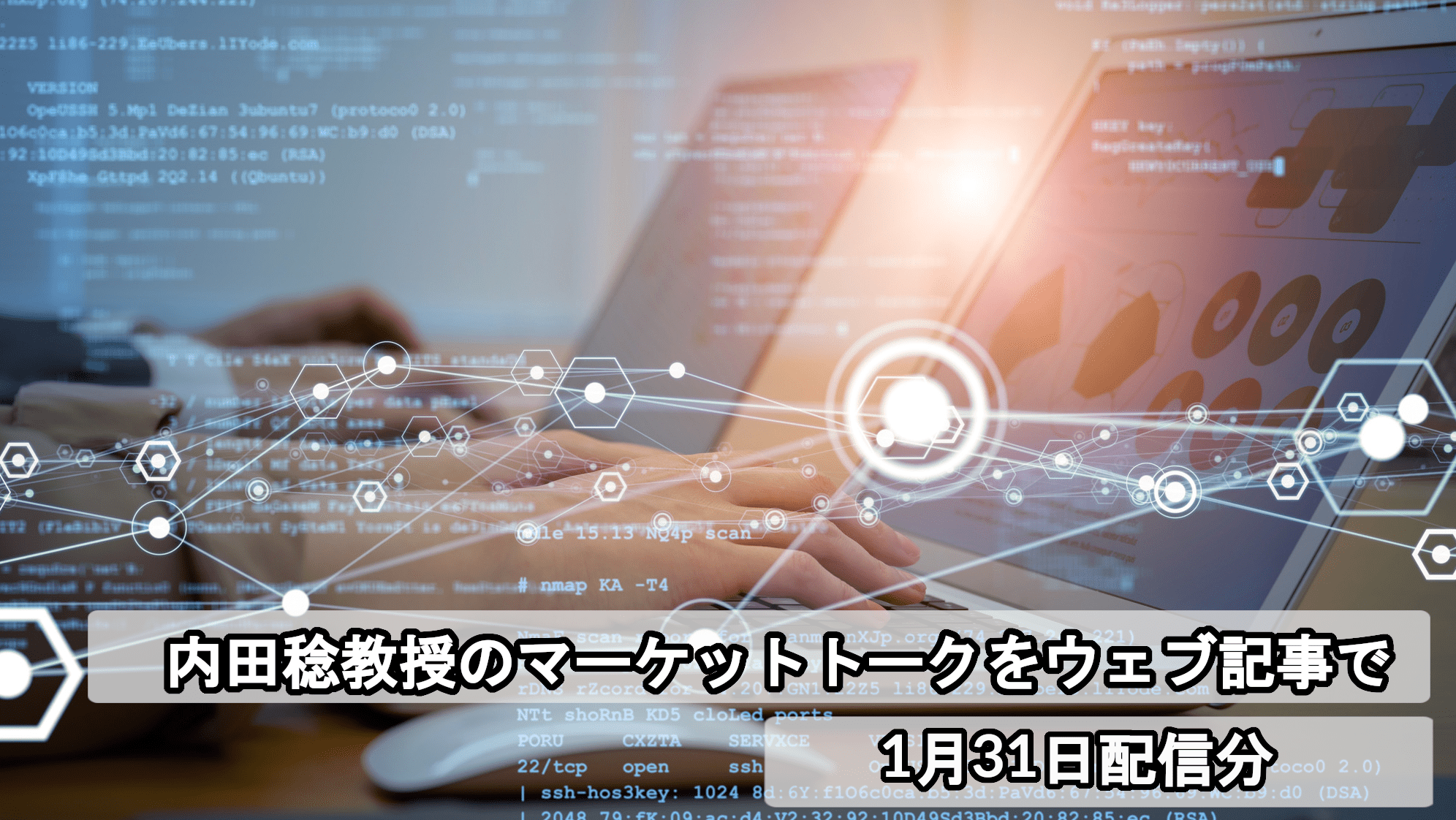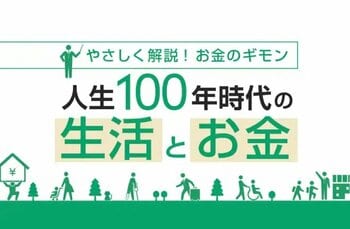金融政策の正常化について
最近の日本銀行の金融正常化について申し上げると、日本銀行は2023年3月にマイナス金利政策およびイールドカーブコントロールを修正し、金融政策の正常化を開始しました。7月には政策金利を0.5%に引き上げ、2024年1月にはこれをさらに引き上げています。
このような動きに対して、急速な引き締めを行うことで、ようやく実現してきた賃金・物価の上昇が危うくなるのではないかという懸念を表明する声があります。しかし、私はそのような懸念は当たらないと考えています。
現在、日本の消費者物価指数は2%を超える水準で推移していますが、1998年から2012年までのデフレ期では物価は下がるか横ばいが続きました。経済成長率も0.5%という極めて低い水準となり、失業率も4%台で推移し、日本の完全雇用水準である3%程度からは遠い状況が続きました。
特に深刻だったのは、この15年間で毎年平均0.9%ずつ賃金が下落したことです。現役の労働者の実質賃金は年平均0.7%程度の目減りとなり、大きな影響を受けました。日本は米国のようなレイオフではなく、雇用維持を優先したため、企業は過剰雇用を抱えながら賃金を引き下げるという対応を取りました。
アベノミクスによる経済政策の転換
このような状況を脱却し、安定成長を回復することを目指して、2013年からいわゆるアベノミクスが開始されました。その3本の矢は、大胆な金融緩和、機動的な財政運営、そして成長戦略としての構造改革でした。
アベノミクスの結果として2014年以降、消費者物価上昇率や経済成長率、失業率は2016年と2021年を除けば、継続的にプラスを維持しています。ただし、2%の物価安定目標に近づいたのは、2022年のウクライナ侵攻による原油価格高騰と円安の影響によるところが大きかったといえるでしょう。2014年からのアベノミクスの政策効果だけでは、いわゆる社会心理的な要因、長年のデフレで定着したマインドセットを変えることができず、長期のインフレ期待は0%台にとどまっていました。
経済成長率については、2020年に-4.0%を記録した以外は概してプラスを維持しており、従来0.8%から1%程度とされていた潜在成長率も、現在では1%台を維持できるとされています。つまり、「失われた30年」という状況は既に脱却していると言えます。
最近の円安と貿易収支
2022年以降、3%台の物価上昇が続いていますが、その初期段階では6%台まで上昇しました。これはウクライナ侵攻による原油価格の高騰が主因です。この影響で日本の貿易収支は大幅な赤字となりましたが、経常収支は第一次所得収支(対外投資収益)の黒字により、依然として黒字を維持しています。
ただし、この第一次所得収支の黒字の約半分は海外での再投資に向けられており、日本に還流していません。そのため、為替市場の需給面では、その貢献は限定的です。このような状況下で貿易収支の大幅な赤字が続いていることが、円安の一因となっています。
ウクライナ侵攻開始時点で1ドル115円程度だった為替レートは、日本銀行の金融緩和期間(2013年から2022年まで)の平均的な水準である110円前後(プラスマイナス10円程度)から大きく乖離することとなりました。
金融政策正常化の意義
現在の日本銀行による金融政策の正常化は、極めて適切な判断であると考えられます。賃金上昇については、2023年は春闘での賃上げが実現し、2024年も5%台の賃上げが予想されています。ただし、この賃上げの恩恵は主に大企業に限られており、労働者の7割を占める中小企業では、まだ十分な賃上げが実現していない点に注意が必要です。
金融政策の正常化は、単なる引き締めではなく、正常な中立的金融政策に向けた移行過程として理解すべきです。中立金利とは、金融の引き締めでも緩和でもない、経済に対して中立的な金利水準を指します。様々な試算がありますが、1%程度とする見方が多く、いずれにしても現在からそれほど離れていない水準です。
日本経済は、デフレマインドを脱却し、設備投資の増加と潜在成長率の上昇という好循環に入っています。現在、G7の中で経済が好調なのは、米国と日本のみです。日本はアベノミクスの効果もあって、着実な成長を遂げていますし、財政状況も消費税増税等の効果により改善傾向にあります。日本経済は、もはや異次元の金融緩和やデフレ的な金融緩和を必要とする状況を脱し、新たな成長段階に入ったと評価できます。