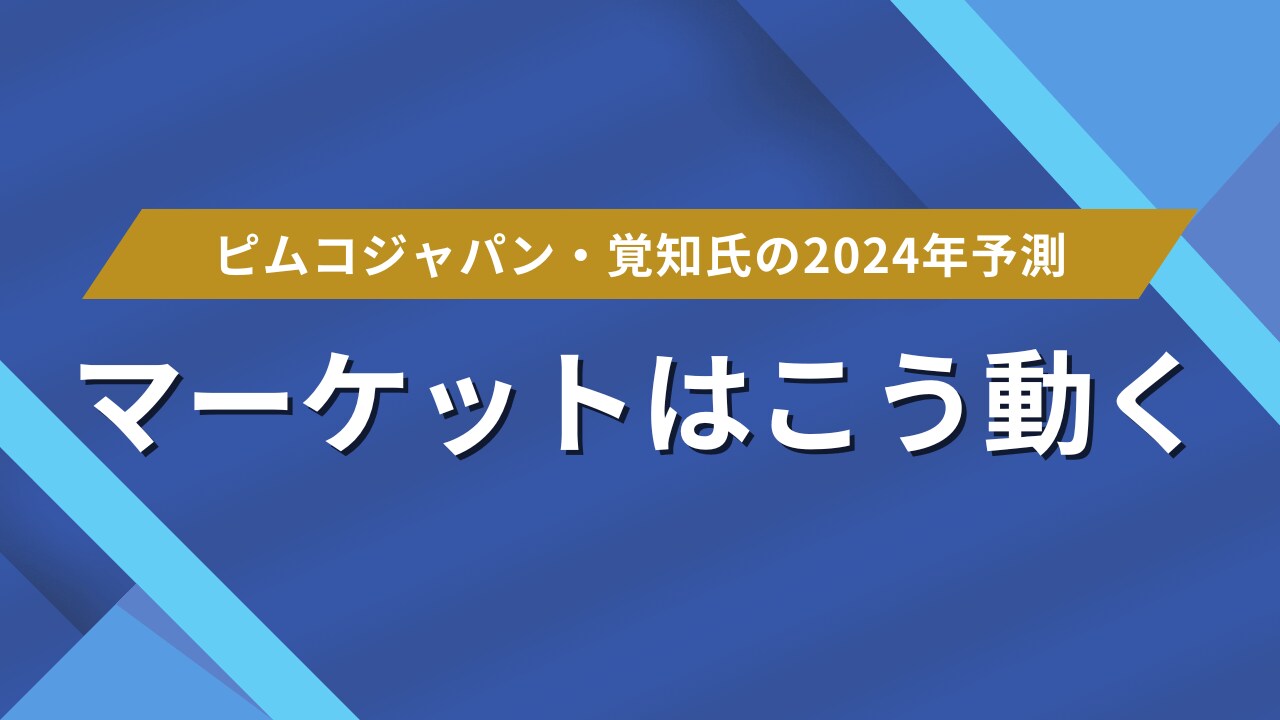中立金利の上昇は資産運用にどんな影響を与え得るか
――FRBが長期的に適切な政策金利の水準を2.6%に引き上げたことは、中立金利の上昇を示唆するのでしょうか。また、AI革命による生産性向上が中立金利上昇の背景にあるのではないかという見解についても、ご意見を伺えればと思います。
池田 中立金利がどの程度なのかという議論は、資産運用を考える上でも重要なポイントです。仮に中立金利が上昇しているのであれば、安全資産の利回りが上昇することになります。従来は低成長の下で目標と実現可能なリターンにギャップがあり、それを埋めるための追加のリスクテイクが必要でしたが、そうした環境が変化しつつある可能性があるわけです。
今回の局面は40年ぶりの高インフレという状況下にありますが、それ以前は中央銀行が大規模な量的緩和(QE)を通じて長期金利の上昇を抑制してきました。しかし、インフレ高進を受けてその政策が転換点を迎えつつあります。いわば「大政奉還」とも言うべき変化が起きており、QEからQT(量的引き締め)への移行に伴って、市場の実勢に基づく金利(=中立金利)を探る段階に来ていると考えられます。
この中立金利を考える上で、まず重要なのが潜在成長率です。人口減少や高齢化は潜在成長率の低下要因ですが、AI革命のような生産性の向上は押し上げ要因になります。一方、自国産業の保護を目的とした生産・事業拠点の国内回帰の動きは投資を増加させ、金利上昇圧力をもたらすでしょう。近年の脱炭素を目指すグリーン投資も同様の効果を持ちます。他方、高齢化の進展や所得格差の拡大は貯蓄率を高め、金利の下押し要因になります。
これまでは、中央銀行によるQEが貯蓄・投資バランスに大きな影響を与えてきたため、潜在成長率と実質金利の間に大幅な乖離が生じていました。しかし、米国はQEからQTに舵を切っており、実質金利は潜在成長率に見合う水準まで急速に上昇してきています。
私の試算に依ると、コロナ禍以降の米国の潜在成長率の推計は現在1.9%程度であり、そこに2%のインフレ目標が達成された場合の名目潜在成長率は3.9%になります。現状の米10年国債利回りはこの水準に近く、均衡点に達しつつあるのかもしれません。まさに「大政奉還」が進行中だと言えるでしょう。
一方、日本については、潜在成長率が0.3%、目標インフレ率の2%が達成されると名目潜在成長率は2.3%になりますが、現状はそこから大きく乖離しています。もっとも、日銀の対GDP比で見た総資産は欧米中央銀行と比べても大きく拡大しており、植田総裁もこの「遺産」は当分の間残ることを指摘しています。加えて、日本で賃金・物価の好循環が本当に定着するかどうかも不透明です。こうした観点から、日本の長期金利については、現状程度の水準が当面続く可能性が高いと見ています。
また、生産性上昇に関するAI革命のインパクトについては、90年代後半のIT革命ブームの際と共通点が見られ、どちらも規模の経済や先行者利得が強調されています。それが投資ブームを引き起こし、生産性上昇率を押し上げることで楽観論に真実味が帯びるわけです。
しかし、技術の急速な普及は同時に陳腐化を招き、差別化要因が失われることで収益率が低下し、いずれブームは減退する。こうした一連のサイクルは、90年代後半のIT革命の際と同様の経路を辿る可能性があります。もっとも、それが1〜2年の短期間で終わるものではない点に留意は必要です。
資産運用における「もしトラ」リスクを再点検する
――11月の大統領選挙でトランプ氏が再選された場合、市場にはどんな影響が及ぶでしょうか。
池田 現時点では、トランプ氏再選はまだ想定の域を出ないものの、仮に実現した場合でも、議会の構成次第では政策運営に制約が生じる可能性があります。ただ、トランプ氏の掲げる政策を見ると、減税延長、関税引き上げ、エネルギー開発促進、移民規制強化など、総じてインフレ圧力を高める方向に作用すると考えられます。
主な政策を個別に見ていくと、関税引き上げは輸入品の価格を押し上げると同時に国内の購買力を損なうため、スタグフレーション的でもあります。また環境・グリーン政策についても、トランプ氏は懐疑的なスタンスを取っており、この分野での投資には逆風が吹く恐れがあります。また、ウクライナ情勢についても同氏の動向には不確実性があります。
さらにFRBの金融政策運営について、トランプ氏がパウエル議長の交代を画策する可能性はありますが、議長人事だけで利上げを止められるとは考えにくいでしょう。ただ、財政赤字の拡大を伴う減税延長によって、市場が財政リスクプレミアムを要求し、長期金利の上昇を促すかもしれません。
――まとめに代えて、金利や為替を含む今後の市場動向について、お考えをお聞かせください。
池田 先述の通り、米国経済が「浅い谷」を辿るのであれば、FRBの利下げ幅は市場予想ほど大きくならず、利下げも予防的なものにとどまるでしょう。すなわち、短期金利の低下余地は限定的だと考えられます。
典型的な景気後退局面では、長期金利の低下とともに大幅利下げによって短期金利が急低下し、イールドカーブが大幅にスティープ化する傾向がありました。しかし、「浅い谷」のケースでは、90年代後半の事例のように、長短金利は小幅な低下にとどまりやすいと考えられます。
一方、日本では賃金・物価の好循環に対する自信が持てない中、追加利上げはまだ見通せない状況です。とすれば、日米金利差は縮小方向にあるものの、市場の想定ほどは縮まらない可能性が高く、円高が進みにくい。そのため、ドル円のヘッジコストもそこまでの低下は見込めないと考えられます。
――本日はどうもありがとうございました。