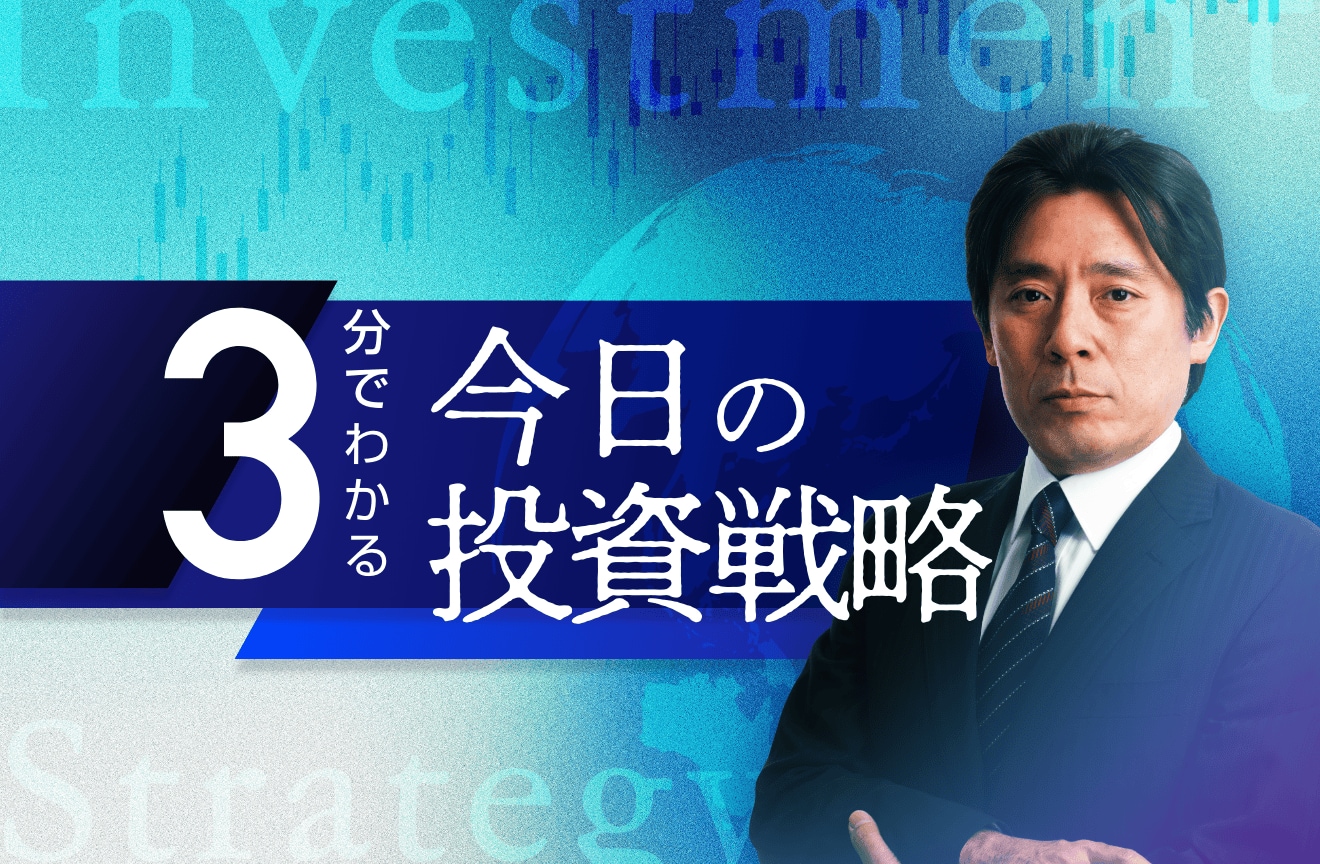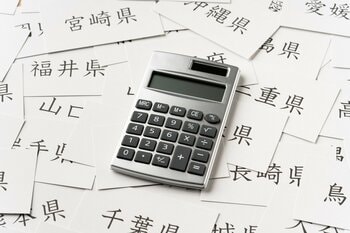――日本の投資家にとって、今後魅力的な投資機会はどこにありそうでしょうか。
着目すべきなのは実質金利です。その理由は、インフレが今後上昇していくと考えているからです。トランプ氏による関税政策や人口動態による賃金上昇、環境意識の高まり、各国の軍事費増など、インフレを押し上げる構造的な要因が複数ありますが、市場はまだ完全には織り込んでいません。市場が予想する将来のインフレ率(ブレークイーブン・インフレ率)は2.5%程度ですが、われわれは3~4%になる可能性があると考えています。
こうした市場の「ミスプライシング」を利用することで、各種債券などを通じた実質金利への投資は利益を生むでしょう。また、現在はデュレーション(金利変動に対する債券価格の感応度)を取ることがリターンにつながる局面でもあります。インフレとデュレーションの両面から魅力的な投資機会となり得ます。
――投資を考える上で、注意しておくべきリスクは何でしょうか。
マクロ経済の分析に基づいた運用を行うわれわれは、成長、インフレ、金融政策、財政政策の4つを見ていますが、現在最も神経質になっているのは、多くの国で見られる政治的リスクと財政の悪化です。
多くの国の政治家は、有権者を喜ばせるために支出の削減に及び腰になっています。その一方で、金利上昇による利払い費の増加や、高齢化に伴う医療・年金コストの増大など、支出圧力は高まる一方です。この非常に複雑な状況は、中長期的には多くの国で国債の格下げにつながる可能性があります。
こうした状況を考えると、先ほど実質金利が生み出す投資機会を捉えられる物価連動国債が魅力的だと説明しましたが、かつて「安全資産」と考えられてきた国債は、もはや「安全資産」とは言えないかもしれません。実際に投資するにあたっては、資産配分のアクティブなマネジメントが必要不可欠です。
このようなアクティブなマネジメントを取り入れた投資手法の一例としては、特定のベンチマークにとらわれずにグローバルな債券ユニバースから投資機会を見つけ出す、いわゆる絶対収益を狙う債券アンコンストレインド運用が有力な選択肢となるでしょう。われわれの提供する戦略では相応のパフォーマンスが出ていることもあり、年金基金や金融機関などの機関投資家や個人投資家向けラップ口座などを通じ、幅広く関心が集まるようになっています。
――今後の運用を考える上で、投資家が注目しておくべき指標はありますか。
米国のインフレ率です。現在、市場が最も気にしているのは米国の経済成長の行方ですが、それはインフレのレベルに大きく左右されます。先ほど申し上げた4~5%という水準を超えるようなことがあれば、経済は困難に直面するでしょう。逆に、その水準を下回っていれば大きな問題は起こりにくいと考えられます。米国のインフレ率は、金融政策をはじめあらゆる要素に影響を与える、最も重要なポイントです。