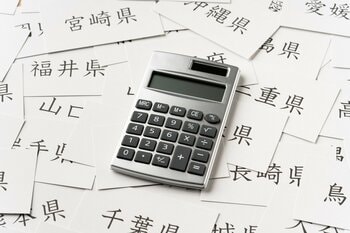――米国、欧州、日本の金融政策について、これまでの評価と今後の見通しをお聞かせください。
まず米国ですが、2023年までのFRB(連邦準備制度理事会)は引き締め局面にありましたが、昨年からの利下げ傾向は継続すると考えています。米国の中立金利(景気を刺激も抑制もしない金利水準)は3%から3.25%程度ですが、現在の政策金利は4.25%であり、引き締め的です。市場はFRBの見通しと同様の年末までのあともう2回の利下げを織り込んでおり、私もこのシナリオは実現可能だと確信しています。先ほど申し上げた通り、インフレが急騰するとは考えていないため、利下げは可能です。
次に欧州ですが、ECB(欧州中央銀行)の政策金利2%は、欧州における中立金利の水準に沿っています。成長やインフレといったマクロ経済の見通しから、今後数カ月の間に金利が上下に動くことはないと考えています。
最後に日本です。日銀は今後の会合で利上げをしていくと思います。現在の政策金利は0.5%ですが、今後半年から1年の間に1~1.25%程度になる可能性があります。長年のデフレや低インフレからインフレの状況が改善し、経済成長も堅調であることが背景にあります。ゆっくりとしたペースにはなるでしょうが、利上げは可能だと考えています。
――米国の強さが際立っていますが、ドル資産への集中は今後も続くでしょうか。
大きくは変わらないでしょう。
株式市場において、米国は群を抜いて世界最大の市場です。AI革命の最前線にいる「マグニフィセント・セブン」のような巨大企業が投資家を引きつけており、米国の優位性はすぐには変わらないと思います。
債券市場についても同様です。米国債市場は世界で最も流動性が高く、規模も大きい。投資家はポートフォリオの分散のために欧州や日本へ資金を少し動かすかもしれませんが、米国を代替する投資先になるのは難しいでしょう。トランプ氏の政策で劇的に変わるようなことがあれば見解を見直すかもしれませんが、現状では大きな動きは想定していません。
――欧州に目を移すと、ドイツ経済の低迷が与える影響はどの程度でしょうか。
確かにドイツ経済は不振で、成長率はほぼ0%です。他の欧州諸国が1%強の成長を遂げているのとは対照的です。またインフラや軍事費への大規模な支出計画を承認しましたが、これらの計画が実行されるには時間がかかります。そのため、ドイツ経済を多少上向かせることはあっても、抜本的な改善には至らないでしょう。
しかし、ドイツ経済がユーロ圏全体に与える影響を過大評価すべきではありません。ドイツが欧州のGDPに占める割合は約25%です。仮にドイツが他の国より1%アンダーパフォームしたとしても、ユーロ圏全体のGDPへの影響は0.25%程度にとどまります。逆に、スペインのような南欧諸国は非常に好調です。
――各国の長期金利は今後どのように推移すると見ていますか。
まず米国ですが、FRBが利下げを行っても、長期金利は上昇すると見ています。10年物国債の金利は現在約4.1%ですが、年末から来年にかけて、インフレの若干の上昇やFRBの独立性に対する懸念から上がっていくでしょう。ターゲットとしては4.5%程度を想定しており、5%には届かないと思います。
欧州では、ドイツの10年物国債金利(現在約2.7%)は、今後3~6カ月はあまり動かないと見ています。経済が若干改善したとしても、インフラ投資などのための国債増発がすぐに具体化するわけではないからです。一方で、フランスの10年物国債金利(現在約3.5%)は上昇するでしょう。政治的な不安定さが続いており、格付け機関による格下げの可能性もあります。新政権が組まれても、左右両派のコンセンサスが必要な予算編成は難航が予想され、財政赤字削減の目標は以前より緩いものになる可能性があります。今後数カ月で3.8~4%程度になることも考えられます。
最後に日本ですが、日銀の利上げはすでに市場にある程度織り込まれています。10年物国債の金利は現在1.6%台程度ですが、1.75%くらいまで上昇する可能性はあります。しかし、米国やドイツの金利との相関を考えると、それ以上に大きく動くとは考えていません。