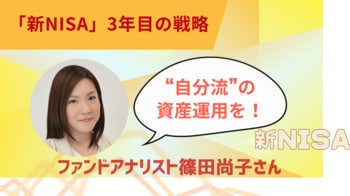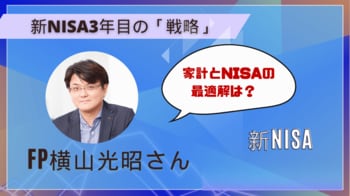2025年9月「1兆円ファンドが11本」の報道が
かつては純資産総額が1兆円を超えるファンドは滅多に現れなかったのですが、近年、それが増えているという記事が、9月25日の日本経済新聞に掲載されました。記事を一部引用すると、
「1兆円超ファンド11本の内訳はインデックス型が6本で、アクティブ型が5本。インデックス型のうち5本は新NISA(少額投資非課税制度)のつみたて投資枠と成長投資枠の両方で投資できる。残り1本は確定拠出年金(DC)専用の『野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)』で、今年7月に初めて1兆円台に乗せた」
「それ以前の1兆円超ファンドはすべてアクティブ型だったが、ここ数年はインデックス型ファンドの台頭が目立つ」
ということでした。
インデックス型ならば、原則として純資産総額が多ければ多いほど良いが…ファンドには適正規模がある
確かに、純資産総額が30億円前後しかないファンドに比べて、1兆円あるファンドの方が長期保有に適しています。なぜなら純資産総額が小さいファンドは、繰上償還条項に引っ掛かり、運用の継続性に疑義が生じてくるからです。
ただ、その一方で純資産総額が大きければ良いというものでもないのが難しいところです。昔、日本の中小型株を中心にポートフォリオを組むファンドの運用担当者5名に、「運用しやすい資産規模はどの程度か」と尋ねたところ、「200~300億円」という答えが返ってきました。それ以上に資金が集まってしまうと、自分の売り買いによって株価を動かしてしまい、それが見えないコストになってしまい、極めて運用しにくい状況に陥ってしまうのです。
過去においても、非常に優れたパフォーマンスを持っていたファンドだからという理由で、販売金融機関が積極的に営業した結果、キャパシティをオーバーしてしまい、運用成績が悪化したケースがあります。どのファンドも、投資先によって適正規模があるのです。
では、今をときめく11本の「1兆円ファンド」の適正規模はどうでしょうか。
現在の1兆円ファンドで何といっても目立つのは、三菱UFJアセットマネジメントが運用している「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」と「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」でしょう。前者の純資産総額は8兆8367億9600万円、後者は7兆8620億9200万円です(2025年10月7日時点)。
とはいえ、後者は世界中に分散投資するポートフォリオなので、その合計時価総額からすれば、運用に苦労することはなさそうです。
ちなみに全世界の株式市場の合計時価総額はMSCI-ACWIで72兆ドルを超えています。1ドル=150円で計算すると、日本円で1京円を超えています。また、MSCI-USAでも46兆ドルを超えていますから、6900兆円です。この数字を見れば、1兆円を超えるインデックスファンドの本数が相当程度まで増えたとしても、日本の投資信託の売り買いが、米国や世界の株式市場に影響を及ぼすことはなさそうです。
いささか懸念されるのは、インデックスファンドよりもアクティブファンドでしょう。前出の日本経済新聞でも、11本中5本がアクティブファンドと指摘しています。
とはいえ、世界時価総額ランキングトップ50に入っている米国企業は33社あり、その時価総額合計は2025年時点で28兆9134億ドルです。これを1ドル=150円で円換算すると4337兆100億円です。この規模感からすれば、米国の成長株を対象にしたファンドの純資産総額が3兆5000億円弱、テクノロジー関連企業に投資するファンドが1兆3705億円あったとしても、その売り買いが株価形成に及ぼす影響は、ほとんどないと考えても良さそうです。
もちろんマーケットインパクトは個別ファンドの純資産総額だけでなく、国内で設定・運用されている全ファンドの規模で考える必要があります。ちなみに公募投資信託の株式売買状況を、外国株式について見ると、2024年の年間で買付額が23兆1026億6600万円、売付額が14兆2352億6500万円ですから、世界時価総額ランキングトップ50に入っている米国企業33社の合計時価総額である4337兆100億円と比べても、マーケットインパクトは軽微であると考えられます。
本音を言えば、これだけの数がある1兆円ファンドの多くが日本株を対象にしたものであれば、日本の株価を底上げする原動力になったかもしれませんが、米国を中心とする外国株式市場を投資対象とするからこそ、1兆円を超える純資産総額を持つファンドが11本あっても、円滑に運用ができていると言えるかもしれません。