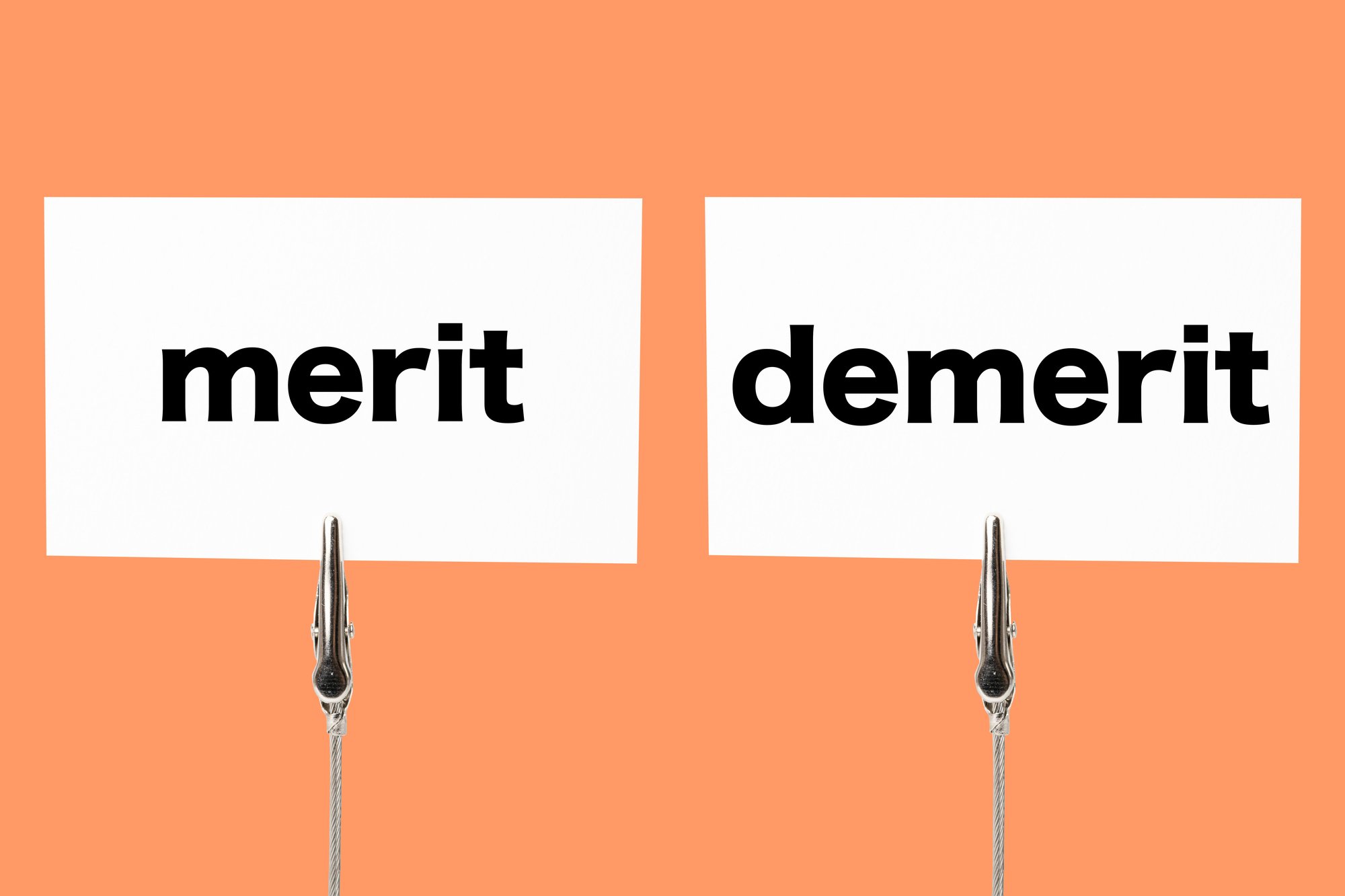選択制DCの制度運営リスク
選択制DCの掛金は、活用する社員にとってはDC掛金か給与等での受け取りかを選択しているので、「本人掛金」のイメージが持たれがちですが、法令上は「事業主掛金」です。
制度運営側である企業の担当者も、制度開始直後は事業主掛金と理解していても、時間が経ち担当者が交代するにつれ、理解があやふやになりがちです。
さらに、人材の流動化が進んでいることもあり、中途入社の社員が前職で利用していた企業型DCが自社の企業型DCと異なることも想定されます。人事担当者が「退職金DC」と「選択制DC」の違いを理解しておかないと、説明を受ける側の社員がわからないから使わない、等の活用チャンスを逃すことにもつながりかねません。企業型DCといっても、企業によって異なる設定がありうるという認識は必要です。
デメリットも伝える必要がある
DC制度がスタートして20年以上が経過するに従い、選択制DCが発展的に活用されるようになりました。すでに退職金制度がある企業で、選択制DC活用が進んでいます。その要因としては2点考えられます。
一つは、退職金制度の見直しをせずにDCを活用するイメージです。退職金制度の見直しにはかなりの時間と労力がかかり、追加費用が発生することもあります。また「退職金」ではリスクを取りたくないという労働者側の意向が働くこともあります。
その結果、退職金制度自体を変更せずに、選択制DCを導入するという企業が増えました。この方法は、社会保険料を折半負担する事業主にとっても、社会保険料の削減効果というメリットがありました。
もう一つは、法令に起因しています。マッチング拠出は事業主掛金以下という制約があることから、退職金DCの事業主掛金が少額の場合、マッチング拠出も少額しかできません。そのため、マッチングのかわりに選択制DCを退職金DCの上乗せとして活用するケースが出ています。
2022年10月の法改正(企業型DC加入者もマッチング拠出をしていなければ個人型DC:愛称iDeCoを活用できる)がこうした動向に影響を与えた側面があります。
たとえば退職金DCの事業主掛金が5000円の場合、マッチング拠出は事業主掛金以下という制限があるため、マッチング拠出による掛金も5000円までしか拠出できません。一方、iDeCoであれば掛金を2万円まで拠出でき、その分節税効果が高いといえます(※1)。
さらに、選択制DCは掛金が本人の給与収入ではなくなるため、税制優遇に加え、社会保険料の抑制効果もあります。
選択制DCを活用する企業が増えたこともあり、厚生労働省の審議会でも選択制DCがテーマに取り上げられました。その結果、「社会保険料の削減効果がある」というメリットの説明だけではなく、給付面でのデメリット(※2)もしっかりと説明することが法令解釈通知に盛り込まれました。
さらに、2024年末の税制改正大綱では、マッチング拠出が事業主掛金以下という制限を外すと記載され、改正法案が国会に提出されました(2025年5月時点)。
DC制度は20年あまりの間に多くの変化が起こりました。都度、知識をアップデートし、よりよく活用することが重要です。
※1 2022年10月当時は確定給付型の制度がある場合のiDeCoの拠出限度額は1.2万円。2024年12月の法律改正により、「5.5万円-他制度掛金相当額-企業型DCの事業主掛金」と「2万円」のどちらか小さいほうが上限金額に改正された。
※2 給付面のデメリットとして分かりやすいのは、将来の老齢厚生年金の減少。そのほか、社会保険料負担が減ると障害年金や遺族年金、傷病手当金、失業保険の給付にも影響することがある。