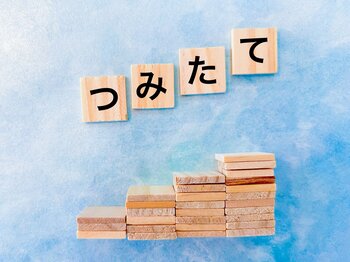「継続投資」がもっともパフォーマンスがよい結果に
運用商品変更について、具体的な数値で考えるとわかりやすいかもしれません。DCの黎明期に設定された投資信託を継続投資する試算(シミュレーション)を一例としてみましょう。
結論からいうと、過去20年超のデータに基づくと「運用商品を変更せずに継続」したほうがよいパフォーマンスになりました。
〈期間〉2002年7月~2025年3月
〈投資対象〉配分固定のバランス型投資信託(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)
〈投資金額〉毎月1万円ずつ(計273万円)
月末の基準価額で買い付け
〈時価評価額〉約541万円(2025年3月末)
継続投資の間には、リーマンショックやチャイナショック、コロナショックが発生しています。そのため、元本割れした期間も49回(月)ありました。特に2008年10月から2012年10月までの間には、前月末と比べて10%以上も基準価額が下落した月もありました。
そんな時、どのような対策法があるのでしょうか。以下3つのパターンでスイッチングや商品配分変更を行った例で詳しく見てみましょう。
〈パターン1 思い切ってスイッチング+積立投資は継続〉
元本割れが発生し、金額も大きくなったため、年末に運用商品変更を思い立ちました。
2008年12月に投資信託から定期預金へのスイッチングを実施。一方、掛金の運用商品変更は行わず、投資信託のままで毎月の積立投資を継続した場合、2025年3月末の残高は約412万円となりました。
〈パターン2 スイッチングと商品別配分変更を実施〉
パターン1と同じ時期に「リスク性商品はこりごり」と、すべてを定期預金に変えてしまった場合、マイナスが確定するため約263万円と元本割れの状態が定着します。
〈パターン3 スイッチングした後に再度投資を開始〉
パターン1と同様にスイッチングを行い、毎月の積立投資は継続。さらに、2008年12月に定期預金にした金額を2013年3月に再度スイッチングして同じ投資信託にした場合、2025年3月末で約495万円になりました。なお、2013年3月はパターン1で元本割れしていた資産がプラスに転じたタイミングです。
過去の数字は将来を保証するものではありませんが、長期継続投資を行える環境にある方は、継続したほうが良いのかもしれません。一方で、資産残高が気になってしかたがないという方は、心の平穏のためにスイッチングをすることも一つの考え方です。
いずれにしろ、元本割れが定着しないように、毎月の掛金での投資は継続したほうがよさそうです。
続いて、運用見直しについてのよくある質問を5つ取り上げます。詳しく見ていきましょう。