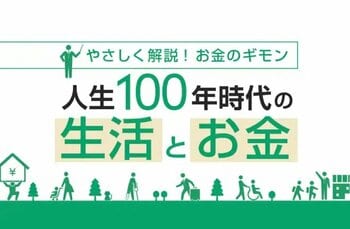経済の動向を分析し、未来を見通すエコノミスト。そのレポートなどは金融業界のみならず、個人投資家から注目されることもしばしば。
第一生命経済研究所 首席エコノミスト・熊野英生氏は、新著『エコノミストの経済・投資の先を読む技法』のなかで、ビジネスや投資に役立つ「先読み」の技法を解説しています。
不確実性が高まる時代、「未来のことは何もわからない」と悲観しがちですが、経験則にもとづき、粘り強く仮説を立てていけば、未来の大まかな方向性は見えてくるかもしれません。そこで今回は、景気と株価の関係について、熊野氏に読み解いてもらいます。(全3回の2回目)
●第1回:【エコノミストの先を読む技法】株価と景気サイクルの関係とは? 「トレンド」と「サイクル」の仕組みを解説
※本稿は、熊野英生著『エコノミストの経済・投資の先を読む技法』(明日香出版社)より、一部を抜粋・再編集したものです。
4つの経済サイクル
景気循環をより深く理解するために、代表的な4つの経済サイクルを解説します。
在庫循環(キチン・サイクル)
企業が保有する在庫の変動によって発生する短期的な景気循環です。在庫が積み上がれば生産を抑制し、不足すれば生産を拡大します。この在庫調整のプロセスが、景気の波を大きくします。
設備投資循環(ジュグラー・サイクル)
設備投資の行動によって発生する、中期的(約10年)な景気循環です。企業は将来の需要拡大を見込んで設備投資を行います。目先の需要は自己実現的に増えますが、しばらくして過剰な設備投資は供給過剰を招き、景気後退の要因となります。
建設投資循環(クズネッツ・サイクル)
住宅やビルの建設投資の変動によって発生する長期(約20年)の景気循環です。
技術革新の波(コンドラチェフ・サイクル、またはシュンペーターの波)
技術革新が経済全体に大きな影響を与え、超長期の景気循環を引き起こします。
これらの経済サイクルの説明は、教科書的なものです。しかし、私はそのまま鵜呑みにするのは実体とは少し食い違うと考えています。現代は「イノベーションの時代」であり、特にIT分野を中心とした技術革新が経済に大きな影響を与えているからです。
たとえば、従来は在庫循環が景気に大きく影響すると考えられていましたが、情報技術の発達により企業は需要予測をより細かく行い、在庫管理の効率も高まっています。在庫をほぼ持たない企業もあり、その結果、在庫循環が景気に与える影響は以前より小さくなっていると考えられます。