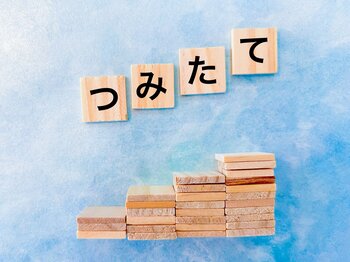企業型DC加入者がiDeCoを活用するデメリット
メリットがある反面、デメリットもあります。なかでも、企業型と個人型でDC口座が二つになるデメリットでは手数料と手間の二つを勘案する必要があります。
手数料(下記は野村のiDeCoの場合)
iDeCoの運営管理手数料は本人負担ですが、企業型DC加入者は事業主負担が一般的です。併用することで発生するiDeCoの手数料は下記のとおりです。
① iDeCo開始時 2,829円
② 加入者の手数料 105円(掛金拠出する月に発生)
③ 事務委託先の手数料 66円(毎月)
iDeCo掛金を拠出する月は171円(②+③)の手数料が発生します(※)。この金額を税制優遇で補うために必要な掛金額は、所得税率5%であれば月額1,140円となります。企業型DCのマッチング拠出と比較して、iDeCoのほうが月1,140円以上多く出せるのであれば、税優遇効果で手数料をカバーできます。
なお、①のiDeCo開始時2,829円の手数料は口座を開設するときに発生します。そのため、以前、iDeCoの口座を持っていたが企業型DCに移換してしまった、というケースでは、再度2,829円が発生します。
離転職が多い方は、企業型DCの設定次第で併用したほうがいいかどうかが変わるので、iDeCo口座を運用指図者として残しておいてもいいでしょう。その場合の手数料は、③の月66円となります。
管理の手間
二つのDC口座があることで、手間が増えます。たとえば運用状況の確認は、複数のWEBサイトや残高報告書で確認することになります。
これについては、企業型DCとiDeCoの残高を一つのWEBサイトで表示できる金融機関もあるので、企業型DCの運営管理機関のiDeCoを活用すると軽減することもできます。
※お勤め先にDB制度がある場合、iDeCoは毎月拠出のみ可能
老後資金としていくら必要か
DCは老後資金を準備するための制度です。とくに引退年齢が近づいてきている年代の方は、老後資金が十分かどうかも判断ポイントになります。若い年代では現実味のある数字にはならないので、ご自身の余裕資金からDC制度の活用を考えましょう。
老後資金を考えるうえでは、公的年金でいくら受け取れるのかが重要です。2022年4月からスタートした厚生労働省の公的年金シミュレーターは、「ねんきん定期便」に記載の二次元コードを読み取ることで、将来の年金受給見込額を確認できます。
現在の老後生活費は夫婦二人世帯の月平均が24万円程度です※。公的年金では賄いきれないと思う金額を計算しましょう。なお、公的年金シミュレーターは今後、iDeCoの試算機能を追加することも検討されています。
※出所:「高齢者の生活実態」(厚生労働省)
*拠出限度額にかかる部分はすべて月額