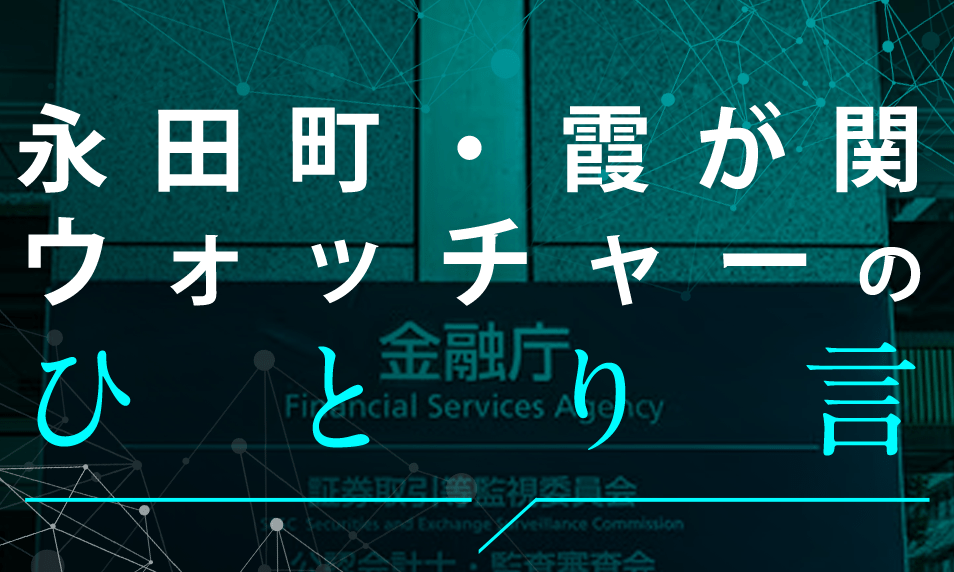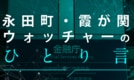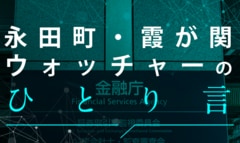政治の潮目はバラマキから「応能負担」へ?
開催中の国会審議では、少数与党がかなり苦戦している。野党の提案を多々受け入れざるを得ず、「年収103万円の壁」を見直し、所得税の課税最低限を160万円に引き上げるべく、税制関連法案を修正した。ほかにも「高校の授業料無償化」について、2025年4月から公立・私立を問わず一律に年間11万8800円の就学支援金の所得制限を撤廃するとともに、2026年4月から私立高校向けの就学支援金を45万7000円に引き上げることとした。夏の参院選を控え、どうしても「政策よりも政局」重視となるのだろう。先日、ある議員がセミナーで「今国会はまさに『パンとサーカス』の供与合戦状態。より中長期的な視点で国の将来を論じるべきではないか」と嘆いていたが、首肯するところだ。
こうした中、安定財源確保に向け、国会審議では与野党問わず頻繁に「応能負担」という言葉が発せられている。例えば、野党第1党である立憲民主党においても、金融所得課税に関し、富裕層優遇のいわゆる「1億円の壁」解消に向けて、当面は分離課税のまま累進税率を導入し、中長期的には総合課税化するほか、資産格差が拡大・固定化している現状に鑑み、税率構造や非課税措置の見直しなどにより、相続税・贈与税の累進性を高めることなどを提案している。
このほか、政府内では、近年、医療保険・介護保険における負担の在り方全般について、マイナンバーの活用により金融資産の保有状況も勘案して、負担能力を判定するための具体的な制度設計について検討すべきという声が高まっている。この背景には、日本の金融資産の6割超を60歳以上の世代が保有していることがある。主な収入が年金という高齢者は、年収(フロー)基準で捉えると負担は勤労世代より少なくなる一方、一般的に勤労世代より資産(ストック)を多く持っている。勤労世代の減少と高齢世代の増加が進む中、政府が年齢ではなく所得(フロー)に金融資産(ストック)を加えたベースで負担を求めることは無理もないように思う。
だが、応能負担が過度になると、高所得者や資産保有層の負担感が強くなり、納税意欲が低下する可能性がある。また、実務的にも、金融所得課税の累進税率適用や総合課税化が進むと、確定申告者の急増が予想されるところ、確定申告に不慣れな方々にとっては苦行にほかならず、政府・自治体側も、当面の間、徴収事務の負担増を覚悟する必要がある。加えて、金融資産の保有状況を踏まえた負担ということになると、預貯金口座のマイナンバーとの紐付けなどが必要となるが、国民の政治や政府に対する不信が高まっている現状において、この作業は容易ではないだろう。とはいえ、安定財源確保が論点となる中、消費税等の応益負担を増やすくらいなら、まずは応能負担を増やすべきとの意見は強まる可能性がある。
毎月分配型ファンドもNISAで解禁すべき
こうした状況では、ある程度の金融資産を保有する高齢者においては、資産の有効活用が重要性を増してくる。幸いなことに、永田町も霞が関もNISAについては制度維持の姿勢を崩していない。
現状、60歳代以上のNISA口座開設は1~2割程度に留まっており、3割に近い30歳代~50歳代よりも利用率が低い。よって、高齢者においてもこうした非課税投資枠を有効活用することを積極的に検討すべきだろう。
一方、多くの高齢者は金融資産を取り崩しながら生活しており、投資をするにしても、その取り崩しニーズとバランスさせることが求められる。こうした要望に対しては、ネット証券などが、投資信託を定期的に一定額、あるいは一定率を売却し資金を受け取れるサービスを無償で提供している。また、公的年金が支給されない奇数月に分配金を受け取れる隔月分配型投資信託がNISA対象銘柄にも複数並んでいる。斯様に非課税制度を利用しながら資産運用と資産取り崩しを両立させるサービスや投資商品があることを政府や業界団体はもっと積極的に報じても良いのではないか。
現在、毎月分配型投資信託はNISA対象外にもかかわらず、常に投資信託の買付ランキング上位に挙がっており、相応に顧客ニーズがあることが窺われる。よって、過度な分配金にならない仕組みとすることを条件として、毎月分配型投資信託のNISA対象化を検討しても良い時期に来ているように思う。
このほか、学校での金融教育が進められる中、高校生以下の若年層においてもNISA制度を使いながら投資経験を積むことができるようにすべきとの要望が以前より業界内から出ているところ、例えば、その資金面をサポートすべく、高齢者が一定額を上限として、孫や子のNISA投資資金を無税で提供できるようにするといったことも一案かと思う。
また、日本証券業協会も令和5年度の税制改正要望に掲げていたが、被相続人がNISAで保有していた上場株式等については相続税を非課税とすることで、高齢者のNISA活用を促すことも良いアイデアかと思う(この案については、上場株式の長期安定株主を増やすという副次的なメリットもある)。
私事で恐縮だが、数年前になるが、日本でもベストセラーとなったビル・パーキンス氏著の「Die with Zero」における「幸せになるためには惜しまずにお金を使え」という彼の提言に筆者は深く共感し、(平均的な)健康寿命に向かって、旅行や趣味に大いに資金を投じようと心に誓ったことがある。その後、孫が増えるにつれ、やはり、それなりに彼らに資産を残してあげたいという気持ちが強くなってきた。「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」という格言もその通りかと思うのだが、せめて釣り竿や餌を買う資金程度は残してあげたいと思っている。NISA制度がそうした願いをかなえるツールとなってくれれば大変ありがたい。