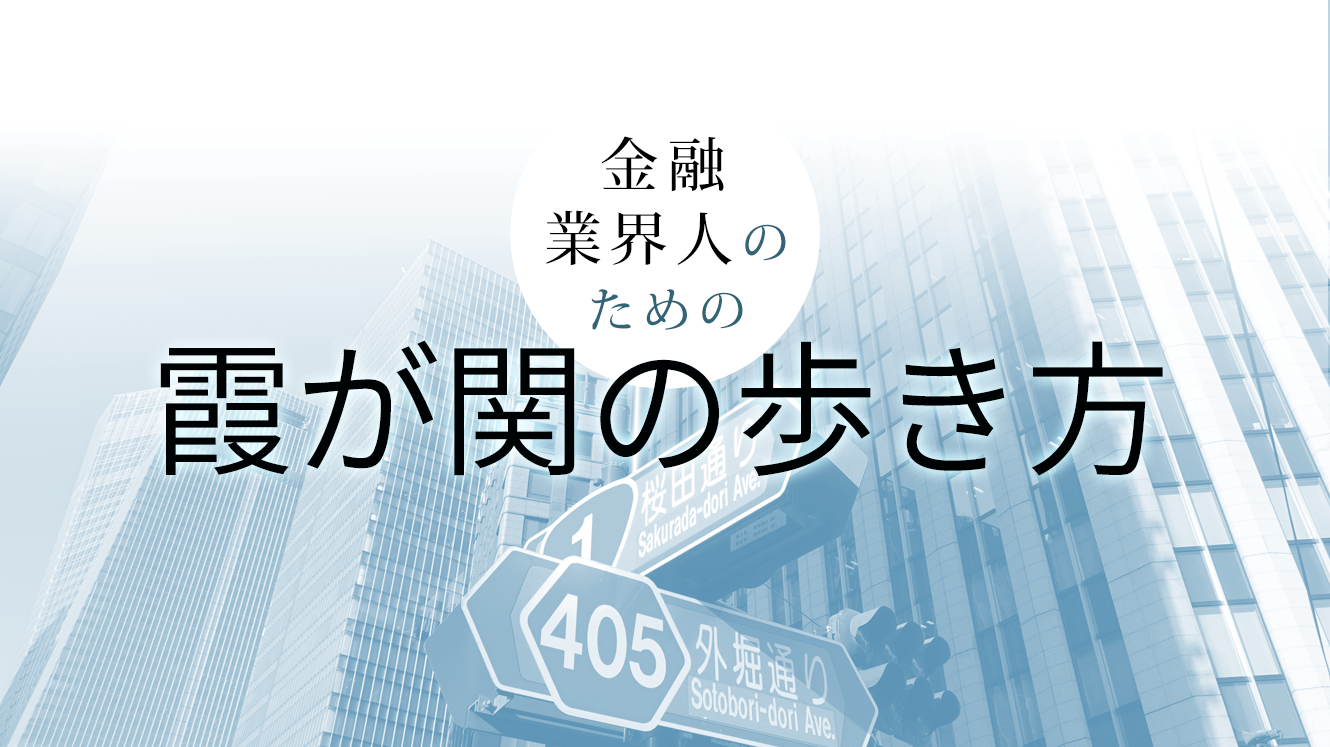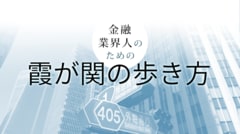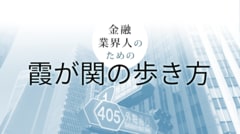2700万人が口座開設、政局流動化でさらに重み
高市早苗政権が発足したものの国内の政局は極めて流動化しており、公明党の連立離脱で同党が自民党と合意した政策の実施も不透明となっている。
ただ、金融庁が岸田政権時代から官邸と歩調を合わせて進めてきた運用立国路線は既に国の方針に組み込まれており、同庁では「いまさら撤廃や縮小などは考えられない」(同庁幹部)との見方が強い。
運用立国の柱である新NISAの実績を見ると、2025年6月末時点で口座数は2700万件に迫っている。この数字は同年7月に実施された参院選で自民党が比例区で獲得した1280万票の2倍以上の規模だ。
選挙と資産運用を混同するなといわれそうだが、福田康夫政権時代に証券税制などの取材で関連する議連の会長を務めていた山本有二衆院議員(当時)を訪ねたことがある。その席で何かの拍子で「グロソブ」の話しになり、「この投信のお客さんは何人くらいか」と尋ねられた。
当時のグロソブの残高は6兆円近かったので「顧客情報は分からないが、平均保有額が200万円なら300万人、300万円なら200万人といったところ」と答えると、「そんなにいるのか。我が党の党員よりはるかに多いな」と驚いていた。政治家はこうした見方をするのかと感心した覚えがある。
頭数を票に置き換える政治家の習性が同じだとすれば、2700万口座まで利用者が膨らんだ新NISAを改悪することは難しい。これだけ国民に浸透した制度を縮小したり、同制度を核とする運用立国路線を後退させたりすることは政治的なリスクが大きすぎる。さらに、政局の混乱でよくも悪くも政治が金融庁などの意思決定に介入する余裕を失うことで、霞が関のペースで議論が進む可能性がある。
同制度が今後も伸びていけば、投資環境の改善を促すコーポレートガバナンスの改革や資産運用業の高度化などへ続く運用立国の路線が覆ることはないだろう。
投資立国の台頭で相対的な存在感は低下も、
両路線の橋渡し役がアセットオーナー
ただし、運用立国が堅持されるとしても、相対的に存在感が低下する場面はあるかもしれない。今後は同路線よりも「投資立国」が脚光を浴びるとみられるからだ。
資産運用立国と投資立国は、関連しつつも別個の政策だ。政策的な意図があって使い分けられている。
「運用立国」は家計をマネーの出し手とし、国内外に有利な投資機会を求め、国民を豊かすることが目的だ。他方、「投資立国」は国内外の有力な投資家から資金を集め、国内の企業を投資先とし、国の生産性を高めることを狙う。
もちろん、運用立国による資金が投資立国に導かれて国内のスタートアップに向かうことはあるだろう。だが、少なくとも自民党の資産運用立国議連の中心メンバーでは2つの政策を明確に分けて議論している。同議連の事務局長代理を務める神田潤一衆院議員は「家計を豊かにする政策と企業を強くする政策は分けて考えている。企業を強くするためのものが投資立国だ」と説明している。
これまで投資立国が前面に出なかったのは、先行していた運用立国の充実を急いだことと、両者の取り違えによる混乱を避けたるためだろう。だが、運用立国が最終局面を迎えたことで投資立国に重心が移るのは想定通りだ。
では、運用立国の最終局面とは何か。それがアセットオーナーの機能強化だ。そして、アセットオーナーの改革が運用立国と投資立国の橋渡し役となる。
投資立国の柱はPE、加えてインフラFか
資金の出し手は年金基金に期待
投資立国が国内に資金を呼び込む政策として具体的な投資先はどこか。筆頭は新しい技術やアイデアの事業化を目指すスタートアップ企業だ。地方創生の流れに乗って社会基盤の整備を支援するインフラファンドも注目されそうだ。インフラの建設などは大企業に任せても「日常的なメンテナンスは地元企業の仕事になる」(地方銀行の役員)からだ。
では投資家は誰か。運用立国の効果で拡大した個人投資家も想定されるが、基準価額が1万円で購入したものを1万2000円で売却したり目先の分配金を求めたりする投資行動では心もとない。
海外の投資家の資金は潤沢だが、この国の未来を託すスタートアップ企業やインフラを海外の資金で賄うことを不安に感じる向きは少なくないだろう。
そこで国内の長期投資の担い手として期待されるのが年金基金などのアセットオーナーだ。だから、金融庁がアセットオーナーの機能強化を「インベストメントチェーンの残された最後のピース」と呼んでいるのである。