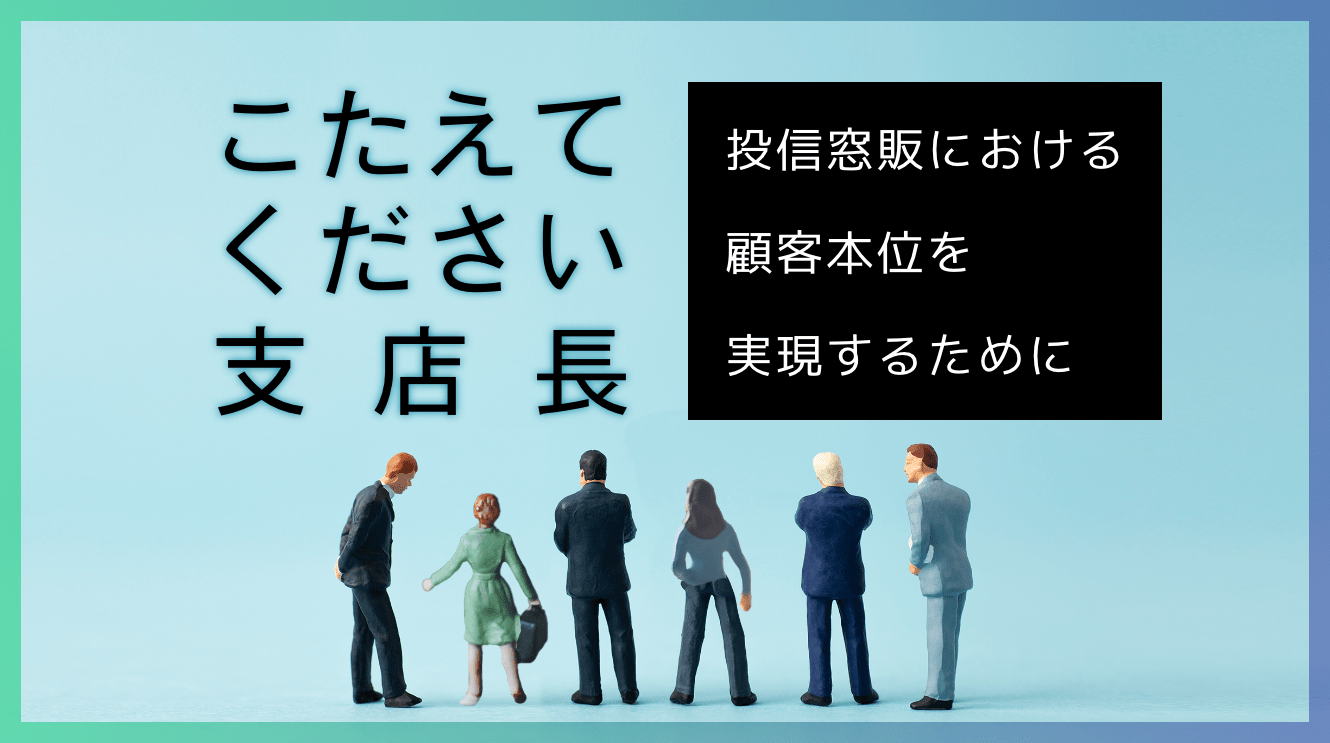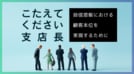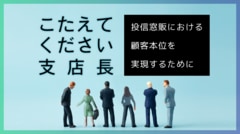Q:職員「高齢者にリスク性商品を販売することは顧客本位から外れませんか?」
A: 支店長「コンプライアンスルールから外れないように、お客さまのご意向をよく聞いて販売活動をしてください」
森脇's Answer:
これは当たり障りのない優等生的回答であり、それこそコンプライアンス担当者からみれば問題ない回答かもしれません。しかし、今後増えていく高齢者の投信保有という本質的課題とそれに対する現場の不安に何も答えていないばかりか、収益目標もコンプライアンス上の難点も現場に丸投げしている責任転嫁の回答です。
顧客起点で考える
高齢者のみならず、投資信託を含む金融商品はニーズがあるお客さまに販売するものです。従って、高齢者には投資信託を販売しないなどと一律に制限するべきものではありません。
例として、新たな資金を投資に振り向けたいとの申し出があった75歳男性について、以下のような二人のお客さまを想定して考えてみましょう。
Aさんは投資未経験。年金受給額は暮らしていける程度の金額だが余裕があるわけではない。預貯金保有額もさほど多くはない様子。
Bさんは投資経験あり、現在も投資継続中。年金受給額は十分で、貯蓄に回せるほど余裕がある。預貯金の保有額も十分である。預貯金を取り崩す必要性を感じていない。
上記のわずかな情報だけでも、それぞれに対して投資商品を販売すべきか否かは明白だと思います。Aさんには投資商品は案内すべきではありませんが、Bさんに販売するのは問題ない可能性が高いと考えられます。年齢で一律に販売を制限するなど、画一的なルールを適用してお客さまに対応するのは明らかに顧客本位でない活動なのです。
もう少し詳しく解説しましょう。NISAの制度が普及する以前、投資は資金に余裕がある人が余剰資金を運用する、すなわち資産活用が主流でした。一方、NISA普及後は資産形成としての長期・積立・分散投資が広く知られるようになり、投資の目的は資産活用と資産形成という二つに大別されるようになりました。Aさんは資金に余裕がなく、投資の目的は資産活用ではありません。では、人生100年時代を見据えてNISAを利用して長期積立分散にて長生きに備えたい、というのが投資を始めたい理由であったらどうでしょうか。それでも投資商品を案内するのは適切とは言えません。
男性の平均寿命は約81歳ですし、80代に入ると認知症発症の可能性が高まると言われています。高齢者は昔の話はよく覚えており、最近のことは忘れがちとよく言います。これまで投資経験がなく、75歳という高齢からの初挑戦である投資信託購入は「こんな商品契約した覚えがない」など、近い将来忘れてしまうリスクがあります。ましてAさんは資金に余裕がないのですから、投信を販売すべきではありません。もし販売できるパターンがあるとすれば、子どもと同居しておりAさん自身の資金は特に生活には使わない場合です。さらに将来は同居の子ども一人に全て相続させる予定で、しかもその子どもも投資に同意していることがより望ましいです。このような状況であれば、子ども同席のもと、投資商品の契約をご案内することは可能でしょう。このように、投資するのに十分合理的な理由と環境が整っていなければ、たとえお客さまが投資商品を購入したいとのご希望があっても全力でお断りすべきでしょう。
高齢者への販売活動の注意点
高齢者に投資商品を販売する上では、主に3つの点に注意していただきたいと思います。
まず1点目は、利益相反の適切な管理態勢です。高齢者への販売においては、お客さまご本人のリスク許容度を把握するのと同じか、もしくはそれ以上に、無理な販売が行われていないかをチェックし、それを防止する仕組みが必要です。ここで強調したいのは、検証するのはお客さまの認知能力よりも無理な販売が行われていないかの方であるということです。要するに、お客さまをチェックするより、自金融機関をチェックせよ、ということです。金融機関はお客さまを検査するルールは充実していますが、その方向を自分たちに向け、自金融機関が組織として適切に活動していることを示せるような仕組み作りが必要なのです。正しく顧客本位で活動していれば、リスク許容度や投資意向を確認する際にお客さまの認知能力はかなり高い確率で察知できるはずなのです。
どうすれば適切な販売活動を検証できるのか、具体的な方法についてここでは詳述しませんが、自金融機関の実態を踏まえながらぜひ考えてみてください。
2点目は、安易な考えで投資に臨もうとしている、エゴの強いお客さまをお断りすることです。投資をギャンブルと区別せずに考えている方はいまだ少なくありません。多くの人々が利益を得ているらしいとの情報を聞きつけて、単に儲け話に乗りたいとの動機でやってくる方には商品を案内しないことです。下落時には苦情になりやすく、これは高齢者のみならず若い方にもみられるので注意してください。
3点目は記録の残し方です。高齢者への販売に関する記録は、若い方以上に詳細な記録が必要です。近い未来に認知症の発症リスクがあるためです。
記録のポイントは、投資動機と投資金額に関する「個別具体的な理由」です。例えば、日経平均株価に連動する商品を500万円契約する際の記録が「最近日本株が注目されているよね。500万円は使う予定がないので投資します」というものでは情報が足りません。良い例としては「バブルの時に日本株に投資していたよ。銘柄は〇〇ね。当時500万円投資して倍になったところで解約したんですよ。ですから今回はその増えた分でもある500万円投資しますよ。」などと投資理由についてお客さま個人しか知りえない情報を書くことです。それが合理的な販売活動をしたことの証明になります。
ルールの見直し
支店長や管理者の皆さんに求められることは、実態に即したルール変更をすることです。
NISA以前の販売活動は、長きにわたる日本株の低迷も相まって、利益が出たらすぐに解約をする短期売買や回転売買が主流だったことは周知の通りです。そういった営みにおいては売買における顧客の都度の判断能力が重要であり、ある程度の年齢で手じまいするのが普通であるという風潮がありました。しかし、インフレの時代に突入し、日本株もバブル期の最高値を超えるという状況の変化のなか、NISAの制度拡大により投資は生涯するものだとの価値観もかなり浸透しつつあります。この数年で人々の意識は様変わりしています。ところが、金融機関の窓販業務におけるルールや仕組みは、相変わらず生涯投資など想定していないまま運用されているのが実状ではないでしょうか。金融機関の古いルールにお客さまを合わせることは金融機関本位でもあります。時代遅れになっている仕組みを更新していく必要があるのです。
今回のような質問が出るということは、その金融機関において社会情勢や市場環境に即したルール変更ができていないこと、あるいはそれが浸透していないことを示唆しています。さらに言えば、高齢者に対する無理な販売が行われている可能性をも見てとることができます。職員からのこういった疑問・質問を、お客さまからいただく苦情とともに、組織改善の鍵として役立てていただくことを期待します。