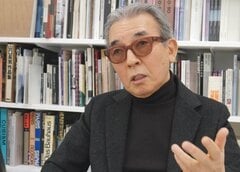かやば太郎氏 金融庁が来年度税制改正要望で、NISAでの毎月分配型投信の解禁案を見送る方向となりました。
本石次郎氏 今にして振り返ると、毎月分配型の解禁論は、政官の水面下の議論の中で半ば偶然的に生まれ、図らずも一気に注目を集めてしまったような経緯があります。しかし実際には、岸田文雄氏が率いる資産運用立国議員連盟を含め、政界側でそれほど強いモチベーションはなかったんです。
財研ナオコ氏 とはいえ業界内では、「毎月分配型の解禁は岸田氏周辺が言い出した」というイメージが強い。高市首相-片山さつき金融担当大臣の下で、金融界における岸田氏の影響力が低下していることを印象づける結果になってしまった。
かやば氏 金融庁は岸田政権が創設した旧「新しい資本主義実現会議」に幹部を送り、官邸と太いパイプを築いていました。高市政権が立ち上げた成長戦略会議内にも、資産運用立国の具体策を議論する分科会のようなものが設置されるとすれば、引き続き金融庁が取りまとめ役を担うのかもしれません。金融庁幹部は「やることは今までと何も変わらない」と強調しています。
財研氏 政府のプライオリティが大きく変化する中で、成長戦略会議全体のレベルで、金融庁がこれまで通りの存在感を維持できるとは思えないけどね。
かやば氏 金融庁の組織改編などは既定路線となっているし、資産運用立国の名の下で続けられてきた施策が全てストップしたわけではありません。資産運用立国というコンセプトが、生みの親である岸田氏や同氏率いる議連から距離を置き、親離れを始めたというところでしょうか。
本石氏 高市政権が石破政権から引き継いだ「地域金融力強化プラン」策定に向けた議論も、大詰めを迎えています。
かやば氏 本業の融資だけでなくエクイティを通じた支援、M&AやDX支援などを求める流れになってはいますが、一部の有識者委員からは、地銀にそんな余裕があるかとツッコミもあがっていました。
本石氏 目玉は、実質的な合併促進策である資金交付制度の延長・拡充です。会合では、資金交付制度を活用して長野銀行と経営統合を進めた八十二銀行の幹部が登壇し、店舗統合などによって新たな戦略領域に200人を投入する算段についてプレゼンしました。
財研氏 「地域経済を支えるために支援の幅を広げなさい」「その余力がないなら合併を考えなさい」と、金融庁が全国の金融機関に二択を迫ろうとしているようにも思える。
かやば氏 マイナンバーと預貯金口座を紐づける口座付番の動向も、気になっています。
財研氏 口座付番については、一時、義務化に向けた議論が盛り上がったが、結局は任意のままだ。
かやば氏 高市首相は何年も前から紐づけ義務化を主張してきました。制度を所管するデジタル庁の上層部からは、給付付き税額控除を検討する過程で議論が再燃することへの期待論も聞こえます。
かやば氏 マイナンバーカードに関しては、口座開設時の本人確認時の利用が原則として義務化される予定です。マイナンバーカードは「嫌われ者」みたいな雰囲気がありましたが、マイナ保険証への移行もあって普及が拡大すれば、金融機関にとってビジネス戦略上の重要度を一気に増す可能性があります。加えて、マイナポータルは足元で大規模なシステム改修が進められいて、「疎結合化」を進めた新システムが来年1月に稼働します。
大石氏 疎結合化って?
かやば氏 システム全体の建てつけをシンプルにすることで、金融事業者がマイナンバーカードをビジネスに取り込む独自の仕組みを作りやすくなる、ということです。マイナ関連サービスの競争が激化するかもしれません。
財研氏 うかっがた見方をすれば、国は地域金融機関を、政府の意向に沿って地域経済の効率化を推進しつつ、所得などに関する情報を管理する出先機関のようなものにしようとしている印象も受ける。もとより地域を支える気概に満ちた金融機関は多いはずなので、官民が足並みをそろえるため、新たなビジネスモデルの方向性を各行が具体的に描けるよう、当局にはしっかりサポートしてほしいところだ。